question
dict | answers
list | id
stringlengths 2
5
| accepted_answer_id
stringlengths 2
5
⌀ | popular_answer_id
stringlengths 2
5
⌀ |
|---|---|---|---|---|
{
"accepted_answer_id": "51438",
"answer_count": 1,
"body": "Spresense Arduino Library (バージョン1.1.2)\nのスケッチ例`Audio/application/pcm_capture.ino`,また`Audio/application/pcm_capture_objif.ino`を試用しています.\n\n本プログラムを実行しシリアルモニタを開くと,`pcm_capture`, `pcm_capture_objif`ともに, `\"Recording\nStart!\"` の後数秒間は `void signal_process(uint32_t size)` 内の `printf`\nが実行されているのが見えますが, `WARNING: Insufficient buffer area.` と出て終了してしまいます.\n\n 1. バッファのデータ構造について\n\nvoid signal_process(uint32_t size)\n\n内の\n\n```\n\n printf(\"Size %d [%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x ...]\\n\",\n size,\n s_buffer[0],\n s_buffer[1],\n s_buffer[2],\n s_buffer[3],\n s_buffer[4],\n s_buffer[5],\n s_buffer[6],\n s_buffer[7]);\n \n```\n\nにおいて,例えばMIC_Aの音の波形データが欲しければ,どのように読み取ればよいのでしょうか?\n\n```\n\n buffer_size = 6144; /*768sample,4ch,16bit*/\n \n```\n\nとあるので,`s_buffer[0]~[7]`のうち2bytesが`MIC_A`の1sampleを表していることは予想できますが,(FIFOオーバーフローのためか)サンプルプログラムが途中で終了してしまうため検証が難しいです.\n\n 2. 複数のマイクの音を収集し,リアルタイムにWi-FiでPCに送信するか,SPI通信で他のマイコンに送信したりしたいのですが,\n\nvoid signal_process(uint32_t size)\n\n内に処理を追加しても,同様に途中でプログラムが終了してしまうことが考えられます.ストリーミングで外部に波形データを取り出すための適切な方法はありますでしょうか.\n\n 3. また \"object if\" の \"if\" はインターフェースの意味なのでしょうか.\n\nよろしくお願いいたします.",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-21T08:28:07.737",
"favorite_count": 0,
"id": "51420",
"last_activity_date": "2018-12-22T09:37:02.527",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31544",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"arduino",
"spresense"
],
"title": "Spresense-Arduino のスケッチ例 pcm_capture が終了してしまう.音声波形データを外部に取り出したい",
"view_count": 308
} | [
{
"body": "void signal_process(uint32_t size) \n等を例にすると、 \nそのまま動かすコードではないと思います。\n\n一例ですが、48kHzサンプリングのデータを、 \nprintfするのは、馴染まない気がしますので、 \n例えば、1024回に1回だけ表示されるとかがいいと思います。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T09:37:02.527",
"id": "51438",
"last_activity_date": "2018-12-22T09:37:02.527",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31548",
"parent_id": "51420",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51420 | 51438 | 51438 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": ".NET Core のアプリケーションから .NET Framework のアセンブリを参照し実行することは可能でしょうか。 \nDLLを直接指定して参照設定を追加し、コンパイルすることは出来ましたが、実行はできませんでした。\n\n例)\n\n * コンソールアプリケーション(.NET Core 2.2)を作成\n * C:\\Program Files (x86)\\Reference Assemblies\\Microsoft\\Framework.NETFramework\\v4.6.1\\System.Runtime.Remoting.dll を参照設定\n * プラットフォームを `x86` に変更\n\nProgram.cs\n\n```\n\n var channel = new IpcServerChannel(\"SampleChannel\");\n \n```\n\nデバッグ実行すると エラーメッセージなどは表示されませんが、すぐにアプリケーションが終了します。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-21T11:24:30.130",
"favorite_count": 0,
"id": "51423",
"last_activity_date": "2018-12-21T14:37:07.353",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3925",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"c#",
".net",
".net-core"
],
"title": ".NET Core のアプリケーションから .NET Framework のアセンブリを参照する",
"view_count": 3504
} | [
{
"body": "詳細は理解しておらず、キーワードだけで探しましたが、こんなQ&Aがあります。\n\n[.net core classlibrary calling .net framework class\nlibrary](https://stackoverflow.com/q/37608032/9014308) \n2年前と古いのですが、解決した印があるので、参考になるかもしれません。以下は機械翻訳です。\n\n>\n> 通常の.NETライブラリとCoreプロジェクト間のコードを共有することは、共有プロジェクトを使用するだけでは機能しませんでした。なぜなら、Coreプロジェクトから参照できないためです。\n>\n> しかし、少しトリックで私はそれを動作させることができます。\n\n同じQのもう一つの回答で紹介されていたのが、これです。 \n[Sharing code across\nplatforms](https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2014/04/21/sharing-code-\nacross-platforms/)\n\n他にはこんなQ&Aもあります。 \n[Calling a .Net Framework 4 (or Mono) assembly from a .Net Core\napplication](https://stackoverflow.com/q/42718943/9014308)\n\nあと日本で何か関係があるかもしれないQ&Aがこれです。 \n[.NET\nCoreのコンソールアプリでdllを参照し,中身のクラスを利用すると例外が発生します](https://teratail.com/questions/96106)\n\n何かの助けになれば。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-21T14:37:07.353",
"id": "51426",
"last_activity_date": "2018-12-21T14:37:07.353",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51423",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51423 | null | 51426 |
{
"accepted_answer_id": "51436",
"answer_count": 1,
"body": "Rubyで記述されたプログラムを複数プロセスによる並列処理を行いたいです. \n`MPI`であれば,`mpirun`というコマンドがあります.\n\nRubyにも同様なコマンドがありますでしょうか?",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-21T12:08:03.127",
"favorite_count": 0,
"id": "51424",
"last_activity_date": "2018-12-22T07:23:24.427",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "30173",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ruby-on-rails",
"ruby"
],
"title": "Rubyにおけるジョブの投げ方を知りたい",
"view_count": 61
} | [
{
"body": "私が知る限り、一番「プロセス並列処理」に近い gem は [Parallel](https://github.com/grosser/parallel)\nです。\n\n```\n\n require 'parallel'\n Parallel.map([1,2,3]) do |i|\n heavy_task_on(i)\n end\n \n```\n\nこの形式で記述されたとき、この gem は何をやってくれるかというと、最大 CPU コア数分まで自身の複製 (fork) を作成し、引数の\nenumerable の各要素をそれぞれの複製に Serialize\nを経由して引き渡します。それぞれの複製は、個別のプロセスとして計算を進め、最終的にブロックの返り値を Serialize\nを経由し、親に返却します。親は、すべての要素に対してこれをおこない、最終的に得られた値たちを Array として返してくれる、便利な gem です。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T07:23:24.427",
"id": "51436",
"last_activity_date": "2018-12-22T07:23:24.427",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "754",
"parent_id": "51424",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51424 | 51436 | 51436 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "windows API user32 から SendInput や SendMessage , FindWindow\nなどを使って、VBAでExcelから他のアプリケーションソフト内にある複数のテキストボックスへコピペ作業を行おうと考えています。 \nただし、 \n①貼り付け先ウィンドウがアクティブでなくても貼り付けが行われること \n②コピペをしなければ他のアプリを操作していても問題ないこと \nという条件を付けたいです。 \nコピペ作業では、テキストボックス間の移動に、 \n③Tabでの移動 \n④Ctrl+Tabでのタブ切り替え \n⑤Ctrl+Alt+→でのリストボックス内移動 \n⑥Spaceでのボタン押下やチェックボックス切替、ラジオボタン切替 \n⑦矢印キーでのコンボボックスの値切替 \n⑧ボタン押下により出現したウィンドウへの移動、戻り \nが必要です。 \nこんなことできるのでしょうか?ヒントとなるキーワードだけでも教えて頂ければ幸いです。 \n特に②を満たすのが難しいのと、⑥の方法を探しても空白文字の方法しか見つからない、⑤の3つ同時押しの情報が見つからないなど、困ってます。",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-21T20:01:07.103",
"favorite_count": 0,
"id": "51427",
"last_activity_date": "2018-12-22T03:21:17.807",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "11053",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"windows",
"excel",
"vba",
"winapi"
],
"title": "VBAでRPAがしたいのでヒントをください",
"view_count": 377
} | [
{
"body": "自分ならwin32apiを使いたおしやすい他の言語(c,cpp,c#とか)でDLLを作りエクセルから呼ぶ \nvba側はできるだけ、大まかな制御と、エクセルとのやりとりをするだけにする \nvbaでwin32apiを駆使するのはシンドイかな、 \n細かい制御のネタはc言語系なら山盛りあると思います",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T03:21:17.807",
"id": "51432",
"last_activity_date": "2018-12-22T03:21:17.807",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31547",
"parent_id": "51427",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51427 | null | 51432 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "お世話になります。 \nタイトルの件、使い方について不明点があり質問させていただきました。\n\n先日CSSの参考書を見ていたところ、 \n下記コードにてテキストを画像に置換するテクニックを学びました。\n\n参考書以外に類似記事もあったので、 \nスタンダードなテクニックなのかなと思います。 \n<http://w3q.jp/t/1914>\n\n```\n\n text-indent: 100%;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n \n```\n\nただ、いままで画像を挿入は、 \n`background-image`,htmlでの`img`タグ等を利用しておりましたが、 \n上記だとどんなメリットがあるのか(どんなケースの場合に使うとよいのか)が分からず、 \nご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか。\n\nどうぞよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-21T22:58:07.270",
"favorite_count": 0,
"id": "51429",
"last_activity_date": "2020-04-18T16:06:30.897",
"last_edit_date": "2018-12-22T00:37:29.723",
"last_editor_user_id": "23994",
"owner_user_id": "19541",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"html",
"css"
],
"title": "CSSのテキスト→画像置換について",
"view_count": 372
} | [
{
"body": "backgroundに画像を仕込むことにより、CSSにて \n:hover(マウスオン)での変化をCSSのみで記述することができます。 \n※html5が勧告されている現在では、aタグの中にimgを複数仕込むことにより、ほぼ同じ挙動が実現できるようになりました\n\nまた、昔は検索エンジンによる情報取得の際に \n画像のaltに対する認識が弱いこともあり、 \n画像テキストなどではこのような処理が行われていたことも多かったようです。\n\nいわゆる過去の慣習のようなものですね。 \n現在は画像altの取得でも、css拡張の面でも \n改良され、無理にそのようなコーディングをする必要はありません。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-15T11:40:14.063",
"id": "51989",
"last_activity_date": "2019-01-15T11:40:14.063",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31792",
"parent_id": "51429",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51429 | null | 51989 |
{
"accepted_answer_id": "51431",
"answer_count": 1,
"body": "下記URLで、Windows向けダウンロードより、exeファイルを入手できてダブルクリックを押したのですがBitbucketにログインしないと先に進めないような形になってしまっています。\n\nSourceTreeのインストールの仕方のサイトを見ても、Bitbucketにログインするような画面がないように思うのですが、Bitbucketのアカウントを作ってログインできる状態にならなければSourceTreeのインストールはできないのでしょうか。\n\n<https://ja.atlassian.com/software/sourcetree>",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T02:35:40.950",
"favorite_count": 0,
"id": "51430",
"last_activity_date": "2020-08-19T02:26:36.957",
"last_edit_date": "2020-08-19T02:26:36.957",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "17348",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"sourcetree"
],
"title": "SourceTreeのインストールにログインは必要?",
"view_count": 4643
} | [
{
"body": "はい、2018年12月現在 SourceTree はインストール時に Atlassian アカウントでのログインが必要です。GitHub\n等の他サービスとの紐付けはその後行うことになります。\n\n参考\n\n * [Can sourcetree be used without atlassian account, e.g. for github?](https://community.atlassian.com/t5/Sourcetree-questions/Can-sourcetree-be-used-without-atlassian-account-e-g-for-github/qaq-p/782362)\n * [Install SourceTree without an Atlassian account?](https://stackoverflow.com/q/41385705/5989200)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T02:54:17.553",
"id": "51431",
"last_activity_date": "2018-12-22T04:26:14.453",
"last_edit_date": "2018-12-22T04:26:14.453",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "19110",
"parent_id": "51430",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51430 | 51431 | 51431 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "小さいサイズのメモリ環境(例RAM 10KB)でgzip圧縮できるライブラリと \nしてどのようなものがあるか知りたいです。\n\n目的:装置からサーバへのデータ送信時にデータサイズを小さくしたい。 \n(送信データサイズは圧縮前20kB程度) \nCPU:ARM Cortex-M4 \nこの処理で使えるRAMサイズ:15KB程度 \nその他:解凍処理は未実装でOK",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T04:34:28.257",
"favorite_count": 0,
"id": "51433",
"last_activity_date": "2018-12-22T04:52:38.993",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31548",
"post_type": "question",
"score": 2,
"tags": [
"gzip"
],
"title": "小さいサイズのメモリ環境(例RAM 10KB)でgzip圧縮できるライブラリ",
"view_count": 166
} | [
{
"body": "[zlib - Technical Details - Memory\nFootprint](https://zlib.net/zlib_tech.html)によると\n\n> The memory requirements for compression depend on two parameters,\n> **windowBits** and **memLevel** :\n```\n\n> deflate memory usage (bytes) = (1 << (windowBits+2)) + (1 <<\n> (memLevel+9))\n> \n```\n\nとのことですので、これを踏まえて`windowBits`(最低値8)と`memLevel`(最低値1)を適切に指定すればいいと思います。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T04:52:38.993",
"id": "51434",
"last_activity_date": "2018-12-22T04:52:38.993",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "4236",
"parent_id": "51433",
"post_type": "answer",
"score": 6
}
] | 51433 | null | 51434 |
{
"accepted_answer_id": "51579",
"answer_count": 1,
"body": "PHP と JavaScript を使用して地図を表示しているのですが、 \nMaps JavaScript API で、アプリケーションの制限 を IPアドレス にした時だけエラーになります。HTTP リファラー\nで設定するとエラーになりません。\n\n[IPアドレスの制限だけではうまくいかない](http://forum.basercms.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3085&forum=8&post_id=10620)のリンク先で \n[位置情報取得も、Javascriptに変更した](https://github.com/baserproject/basercms/commit/0587cf6f88286f00baeb67baeb9a2f88bc400dd8)と書いてあるのですが、どういう意味ですか?\n\nアプリケーションの制限 を IPアドレス にすると、何が影響を受けるのですか? \n・PHPコード? \n・JavaScriptコード? \n・それとも両方??\n\nBaserCMSもリンク先コードも使用していないのですが、PHPとJavaScriptを使用しているので何かヒントになるかもしれない、と思い質問しました",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T07:32:32.743",
"favorite_count": 0,
"id": "51437",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:58:53.333",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "7886",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"javascript",
"php",
"google-maps"
],
"title": "Maps JavaScript API で、アプリケーションの制限 を IPアドレス にした時だけエラーになる",
"view_count": 276
} | [
{
"body": "APIキーに利用制限をかけるということですか?\n\nJavaScriptは閲覧ユーザーのPCで実行されるため、 \nIP制限を許可する場合は閲覧する人のIPを登録する必要があります。\n\nWebにGoogle Mapを載せるのであれば、 \n制限はドメインにしたほうがいいと思います。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T07:58:53.333",
"id": "51579",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:58:53.333",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "20868",
"parent_id": "51437",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51437 | 51579 | 51579 |
{
"accepted_answer_id": "51442",
"answer_count": 2,
"body": "現在私は青空文庫というページにあるデータを入力とする機械学習モデルを作ろうと考えています。 \nそのモデルの入力として青空文庫(<https://www.aozora.gr.jp>)\nにある作品のテキストデータとその作品の初版発行年が必要なのですが、これらのデータを抽出する方法がわからず困っています。 \n青空文庫には様々な作家による小説が保存されていて、ブラウザで直接個別の作品にアクセスできます。 \n例えば、青空文庫のトップページから以下のように「ああ華族様だよ\nと私は嘘を吐くのであった」という作品のページに飛ぶとテキストデータをダウンロードでき、その末尾の底本情報に以下のように初版出版年などが書かれています。 \n[](https://i.stack.imgur.com/6MvjD.png) \n[](https://i.stack.imgur.com/yggaw.png) \n[](https://i.stack.imgur.com/dUBLv.png) \n[](https://i.stack.imgur.com/32bav.png)\n\n最初はスクレイピングでデータ抽出することを考えたのですが、githubで青空文庫のデータを一括ダウンロード(<https://github.com/aozorabunko/aozorabunko>)\nできることや野良APIであるPubserver(<https://qiita.com/ksato9700/items/48fd0eba67316d58b9d6>)\nを利用することができることも知りました。ただ、やはり青空文庫の全ての作品に対してテキストデータと初版発行年を抽出し、後で機械学習にかける入力として作品ごとのテキストデータと初版発行年の組をそれぞれ区別して保存する方法がわからずに混乱しています。 \n例えば、上にあげたgithubからデータをダウンロードする場合、cardsに入っている各ファイルの中にあるfilesからテキストデータと初版発行年が埋め込まれたzipファイルを全ての作品についてparseするのが良いのでしょうか? \n初心者的な質問で申し訳ないのですが、アドバイスをいただけると大変助かります。",
"comment_count": 10,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T09:38:11.697",
"favorite_count": 0,
"id": "51439",
"last_activity_date": "2018-12-22T11:41:22.013",
"last_edit_date": "2018-12-22T11:16:48.780",
"last_editor_user_id": "76",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"api",
"web-scraping"
],
"title": "青空文庫(https://www.aozora.gr.jp)における全作品のテキストデータと初版発行年の取得",
"view_count": 1190
} | [
{
"body": "GitHubのリポジトリで公開されているデータは、青空文庫ホームページのミラーなので、単にデータを抽出する目的だけを考えればどちらを元にしても同じかと思います。\n\nただし「全データ」を対象に取得を考えているなら、GitHubリポジトリからの取得を考えるべきです。 \n数件程度のピンポイントであればホームページに対してのスクレイピングでも構わないのかもしれませんが、全データを対象にリクエストを送ると相手先へのトラフィックで間違いなく負担をかけてしまいます。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T10:10:53.037",
"id": "51440",
"last_activity_date": "2018-12-22T10:10:53.037",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51439",
"post_type": "answer",
"score": 0
},
{
"body": "青空文庫テキストへのアクセスについては\n\n[公開中\n作家別作品一覧拡充版:全て(CSV形式、UTF-8、zip圧縮)](https://www.aozora.gr.jp/index_pages/list_person_all_extended_utf8.zip)\n\nを元に、`GitHub`からクローンしたローカルリポジトリー内のzipファイルのURLをスクリプト内で、`URL`→ローカルファイルパス変換(\"<https://www.aozora.gr.jp/>\"をローカルリポジトリーへのパスに置換する)事でトラフィックを押さえられると思います。\n\nまた\n\n * 圧縮ファイルの文字コードはいわゆるShift-JISなので、文字コード変換を事前にしておくと良い\n * 圧縮ファイルの中身のファイル名は圧縮ファイルのファイル名と異なるので、リネームしてzipファイルと同じにしておいた方が良い\n\nなどの問題もありますので、ご注意下さい。 \n(この辺、プログラムから利用する側にとことん優しくないシステムになっており、プログラムから使いやすい構成になるように、もう少し口出し出来れば良かったと後悔しています)\n\nファイルへの書き込みは別質問にされるようですのでここでは割愛させていただきます",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T11:41:22.013",
"id": "51442",
"last_activity_date": "2018-12-22T11:41:22.013",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14745",
"parent_id": "51439",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51439 | 51442 | 51440 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "下記のコードを実行するとエラーが発生します。\n\nそれぞれのオプションを個別に指定するとエラーになりません。 \n`headless` と `user-data-dir` は同時に指定できないのでしょうか。\n\n**実行したコード:**\n\n```\n\n var driverDirectory = Path.GetDirectoryName(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory);\n var options = new ChromeOptions();\n options.AddArgument(\"--headless\");\n options.AddArguments(\"user-data-dir=userdata\");\n var driver = new ChromeDriver(driverDirectory, options);\n \n```\n\n**エラーメッセージ:**\n\n```\n\n OpenQA.Selenium.WebDriverException\n HResult=0x80131500\n Message=The HTTP request to the remote WebDriver server for URL http://localhost:63525/session timed out after 60 seconds.\n Source=WebDriver\n スタック トレース:\n at OpenQA.Selenium.Remote.HttpCommandExecutor.MakeHttpRequest(HttpRequestInfo requestInfo)\n at OpenQA.Selenium.Remote.HttpCommandExecutor.Execute(Command commandToExecute)\n at OpenQA.Selenium.Remote.DriverServiceCommandExecutor.Execute(Command commandToExecute)\n at OpenQA.Selenium.Remote.RemoteWebDriver.Execute(String driverCommandToExecute, Dictionary`2 parameters)\n at OpenQA.Selenium.Remote.RemoteWebDriver.StartSession(ICapabilities desiredCapabilities)\n at OpenQA.Selenium.Remote.RemoteWebDriver..ctor(ICommandExecutor commandExecutor, ICapabilities desiredCapabilities)\n at OpenQA.Selenium.Chrome.ChromeDriver..ctor(ChromeDriverService service, ChromeOptions options, TimeSpan commandTimeout)\n \n```\n\n**開発環境:** \nChromeDriver 2.45.615291 \n.NET Core 2.2 コンソールアプリケーション",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T11:07:21.637",
"favorite_count": 0,
"id": "51441",
"last_activity_date": "2023-08-21T05:00:30.117",
"last_edit_date": "2022-03-22T01:26:41.297",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "3925",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"c#",
"selenium",
"selenium-webdriver",
".net-core",
"chromedriver"
],
"title": "chromedriver で headless と user-data-dir のオプションを同時に指定するとエラーが発生する",
"view_count": 2241
} | [
{
"body": "**全面改訂**\n\nSeleniumの版数が上がった(4.x系になった)せいなのか、両方指定してもOKになっていました。 \nただし、(Windowsでは?)ディレクトリの指定は絶対パスにしなければならないようです。\n\nこちらの記事を参考に、TargetFrameworkをnet6.0でコンソールアプリを作成してみました。 \n[【C#】Seleniumを使ってChromeを自動操作してみる](https://www.hanachiru-\nblog.com/entry/2020/03/12/120000) \n上記のmain関数内を以下のように書き変えてビルドし確認しています。 \nディレクトリはあらかじめ作成しています。\n\n```\n\n string DriverPath = Path.GetDirectoryName(Assembly.GetEntryAssembly().Location);\n ChromeOptions chromeOptions = new ChromeOptions();\n chromeOptions.AddArgument(\"--headless\");\n chromeOptions.AddArguments(\"--user-data-dir=C:\\\\Develop\\\\ChromeUserData\");\n \n IWebDriver driver = new ChromeDriver(DriverPath, chromeOptions);\n driver.Navigate().GoToUrl(@\"https://www.google.co.jp/\");// URLに移動します。\n \n Console.ReadKey();// なにかコンソールに文字を入力したらクロームを閉じる\n driver.Quit();\n \n```\n\n* * *\n\nなお、`chromeOptions.AddArguments(\"--user-data-\ndir=C:\\\\Develop\\\\ChromeUserData\");`の部分を`chromeOptions.AddArguments(\"--user-\ndata-\ndir=ChromeUserData\");`という風に相対パス指定すると、ディレクトリやいくつかのファイルは出来るのですが、以下のようなエラーになります。 \nつまり相対パス指定だと`C:\\Program Files\n(x86)`の`Chrome`のインストール先にディレクトリやファイルを作ろうとしてエラーになっているようです。 \nただし指定した`ChromeUserData`ディレクトリは、ビルドして動作させているアプリケーションの.exeのあるディレクトリにも作られているのが不思議ですが。\n\n```\n\n Starting ChromeDriver 99.0.4844.51 (d537ec02474b5afe23684e7963d538896c63ac77-refs/branch-heads/4844@{#875}) on port 65379\n Only local connections are allowed.\n Please see https://chromedriver.chromium.org/security-considerations for suggestions on keeping ChromeDriver safe.\n ChromeDriver was started successfully.\n \n DevTools listening on ws://127.0.0.1:65382/devtools/browser/bccc2591-2ceb-4f7f-9b1a-9307e9796b8e\n [0322/100832.023:ERROR:devtools_http_handler.cc(291)] Error writing DevTools active port to file\n [0322/100832.025:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\js\n [0322/100832.025:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\wasm\n [0322/100832.027:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\js\n [0322/100832.027:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\wasm\n [0322/100832.027:ERROR:simple_backend_impl.cc(735)] Simple Cache Backend: wrong file structure on disk: 1 path: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\js\n [0322/100832.027:ERROR:simple_backend_impl.cc(735)] Simple Cache Backend: wrong file structure on disk: 1 path: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\wasm\n [0322/100832.028:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\js\n [0322/100832.029:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\wasm\n [0322/100832.030:ERROR:disk_cache.cc(185)] Unable to create cache\n [0322/100832.030:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\js\n [0322/100832.030:ERROR:simple_backend_impl.cc(80)] Failed to create directory: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\wasm\n [0322/100832.031:ERROR:shader_disk_cache.cc(612)] Shader Cache Creation failed: -2\n [0322/100832.031:ERROR:simple_backend_impl.cc(735)] Simple Cache Backend: wrong file structure on disk: 1 path: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\js\n [0322/100832.032:ERROR:simple_backend_impl.cc(735)] Simple Cache Backend: wrong file structure on disk: 1 path: C:\\Program Files (x86)\\Google\\Chrome\\Application\\99.0.4844.74\\ChromeUserData\\Default\\Code Cache\\wasm\n [0322/100832.032:ERROR:disk_cache.cc(185)] Unable to create cache\n [0322/100832.033:ERROR:disk_cache.cc(185)] Unable to create cache\n Unhandled exception. OpenQA.Selenium.WebDriverException: The HTTP request to the remote WebDriver server for URL http://localhost:65379/session timed out after 60 seconds.\n ---> System.Threading.Tasks.TaskCanceledException: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 60 seconds elapsing.\n ---> System.TimeoutException: The operation was canceled.\n ---> System.Threading.Tasks.TaskCanceledException: The operation was canceled.\n ---> System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: スレッドの終了またはアプリケーションの要求によって、I/O 処理は中止されました。.\n ---> System.Net.Sockets.SocketException (995): スレッドの終了またはアプリケーションの要求によって、I/O 処理は中止されました。\n --- End of inner exception stack trace ---\n at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.ThrowException(SocketError error, CancellationToken cancellationToken)\n at System.Net.Sockets.Socket.AwaitableSocketAsyncEventArgs.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Int32>.GetResult(Int16 token)\n at System.Net.Http.HttpConnection.InitialFillAsync(Boolean async)\n at System.Net.Http.HttpConnection.SendAsyncCore(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)\n --- End of inner exception stack trace ---\n at System.Net.Http.HttpConnection.SendAsyncCore(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)\n at System.Net.Http.HttpConnectionPool.SendWithVersionDetectionAndRetryAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, Boolean doRequestAuth, CancellationToken cancellationToken)\n at System.Net.Http.RedirectHandler.SendAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)\n at System.Net.Http.HttpClient.<SendAsync>g__Core|83_0(HttpRequestMessage request, HttpCompletionOption completionOption, CancellationTokenSource cts, Boolean disposeCts, CancellationTokenSource pendingRequestsCts, CancellationToken originalCancellationToken)\n --- End of inner exception stack trace ---\n --- End of inner exception stack trace ---\n at System.Net.Http.HttpClient.HandleFailure(Exception e, Boolean telemetryStarted, HttpResponseMessage response, CancellationTokenSource cts, CancellationToken cancellationToken, CancellationTokenSource pendingRequestsCts)\n at System.Net.Http.HttpClient.<SendAsync>g__Core|83_0(HttpRequestMessage request, HttpCompletionOption completionOption, CancellationTokenSource cts, Boolean disposeCts, CancellationTokenSource pendingRequestsCts, CancellationToken originalCancellationToken)\n at OpenQA.Selenium.Remote.HttpCommandExecutor.MakeHttpRequest(HttpRequestInfo requestInfo)\n at OpenQA.Selenium.Remote.HttpCommandExecutor.Execute(Command commandToExecute)\n --- End of inner exception stack trace ---\n at OpenQA.Selenium.Remote.HttpCommandExecutor.Execute(Command commandToExecute)\n at OpenQA.Selenium.Remote.DriverServiceCommandExecutor.Execute(Command commandToExecute)\n at OpenQA.Selenium.WebDriver.Execute(String driverCommandToExecute, Dictionary`2 parameters)\n at OpenQA.Selenium.WebDriver.StartSession(ICapabilities desiredCapabilities)\n at OpenQA.Selenium.WebDriver..ctor(ICommandExecutor executor, ICapabilities capabilities)\n at OpenQA.Selenium.Chromium.ChromiumDriver..ctor(ChromiumDriverService service, ChromiumOptions options, TimeSpan commandTimeout)\n at OpenQA.Selenium.Chrome.ChromeDriver..ctor(ChromeDriverService service, ChromeOptions options, TimeSpan commandTimeout)\n at OpenQA.Selenium.Chrome.ChromeDriver..ctor(String chromeDriverDirectory, ChromeOptions options, TimeSpan commandTimeout)\n at OpenQA.Selenium.Chrome.ChromeDriver..ctor(String chromeDriverDirectory, ChromeOptions options)\n at SeleniumTest.MainClass.Main(String[] args) in C:\\Develop\\CSharpSelenium\\CSharpSelenium\\Program.cs:line 34\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T13:16:53.173",
"id": "51445",
"last_activity_date": "2022-03-22T01:23:15.550",
"last_edit_date": "2022-03-22T01:23:15.550",
"last_editor_user_id": "26370",
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51441",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51441 | null | 51445 |
{
"accepted_answer_id": "51449",
"answer_count": 1,
"body": "swift(device target11以上)でiOSアプリで横画面のみの表示をしたいと感がています。 \niPhoneの場合、 \n[](https://i.stack.imgur.com/N6POl.png)\n\nのように「Landscape Left」と「Landscape\nRight」のチェックを入れれば希望の動作をしれるのですが、iPadの場合は有効ではないようです。\n\nどうすれば横画面固定(ホームボタンが左or右)にできるのでしょうか。 \nご存知の方、ご教示いただけると幸いです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T12:53:17.593",
"favorite_count": 0,
"id": "51444",
"last_activity_date": "2018-12-22T20:53:09.120",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "8593",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ios"
],
"title": "swift iOSアプリで横画面のみの表示をしたい",
"view_count": 128
} | [
{
"body": "プロジェクト画面の`General`→`Deployment info`の上から2番目に`Devices`というポップアップがあります。 \nここの`iPhone`, `iPad`, `Universal`をそれぞれ選んで、 \n全デバイス種ごとにその下の`Device Orientation`から`Portrait`と`Updide\nDown`のチェックをはずし、`Landscape Left`と`Landscape\nRight`のみにチェックが入っている状態にすれば良いのでは無いでしょうか",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T20:53:09.120",
"id": "51449",
"last_activity_date": "2018-12-22T20:53:09.120",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14745",
"parent_id": "51444",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51444 | 51449 | 51449 |
{
"accepted_answer_id": "51453",
"answer_count": 1,
"body": "以前に青空文庫からのデータの取得の方法について質問をさせていただき回答を頂いたのですが([青空文庫(https://www.aozora.gr.jp)における全作品のテキストデータと初版発行年の取得](https://ja.stackoverflow.com/questions/51439/%E9%9D%92%E7%A9%BA%E6%96%87%E5%BA%AB-\nhttps-www-aozora-gr-\njp-%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%85%A8%E4%BD%9C%E5%93%81%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A8%E5%88%9D%E7%89%88%E7%99%BA%E8%A1%8C%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97))、私自身gitの扱いに不慣れなため上のリンクで述べられている\"GitHubからクローンしたローカルリポジトリー内のzipファイルのURLをスクリプト内で、URL→ローカルファイルパス変換(\"<https://www.aozora.gr.jp/>\"をローカルリポジトリーへのパスに置換)\"する方法がわかりません。 \nもしかすると次の質問はSOにおいて適していないかもしれませんが、上の作業を実現するコードをどなたかに教えていただけると助かります。 \nまたは、上の課題は私が本を読めばすぐに解決する可能性があるので、なるべく以前した質問([プログラミングにおいてオススメの資料・本など](https://ja.meta.stackoverflow.com/questions/2871/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%96%99-%E6%9C%AC%E3%81%AA%E3%81%A9))\nの反省を踏まえたつもりで書くのですが、上のコードを実現する簡潔な記述があるgitの参考書を教えていただけると助かります。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T14:07:52.163",
"favorite_count": 0,
"id": "51446",
"last_activity_date": "2018-12-23T04:15:10.197",
"last_edit_date": "2018-12-22T14:23:13.653",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": -1,
"tags": [
"git",
"url"
],
"title": "公開中 作家別作品一覧拡充版:全て(CSV形式、UTF-8、zip圧縮)の「テキストファイルURL」をローカルファイルパス変換する方法",
"view_count": 279
} | [
{
"body": "### 青空文庫の全データをZIPでダウンロードする方法\n\n<https://github.com/aozorabunko/aozorabunko>\n\n上記 GitHub リポジトリの中身を git 無しに GitHub から直接ダウンロードできます。下のスクリーンショットにある \"Download\nZIP\" を参考にしてください。\n\n[](https://i.stack.imgur.com/CH4jV.png)\n\nこのリポジトリの、特に `cards` フォルダの中に全ての作品が格納されています。ただし全て HTML\nなど表示用ファイルなので、機械的な処理がやや難しいです。以前の回答で紹介されていた CSV ファイルを使うことで処理を簡素化できます。\n\n### URL をファイルパスに変換してデータベースにする方法\n\nlist_person_all_extended_utf8.zip に入っているのは作品を網羅した CSV ファイルです。この CSV\nファイルを使うことで、たとえば作品名から `cards` の番号に紐づけることができます。\n\nただし CSV に格納されているのはウェブ上の青空文庫サイトへの URL なので、このままだと手元にある青空文庫のコピー用には使えません。そこで、CSV\nから読み取った `https://www.aozora.gr.jp/cards/ほにゃらら`\nというデータの先頭の部分を自分用に処理するなどする必要があります。\n\nここはその後どのように処理するかによって変わります。たとえばの例をひとつ挙げてみます。作品 ID から作品名と手元のテキストデータへのリンクを新しい CSV\nとして書き出してみましょう。\n\n 1. list_person_all_extended_utf8.csv を(たとえば辞書型の値や連想配列として)一行ずつ読み込む。特に CSV に「作品ID」「作品名」「テキストファイルURL」「テキストファイル符号化方式」というフィールドがあるので、ここを読み込む。主要なプログラミング言語には CSV を読み込むための有名なライブラリが知られていることが多いので、それを利用する。\n 2. 「テキストファイルURL」を適切に変換する。先頭が全て同じだと仮定して固定文字数削ったり、正規表現で処理したりするなど。\n 3. テキストファイルが圧縮されていることがあるので、必要であれば伸張する。\n 4. テキストファイルのエンコーディングがファイルによってまちまちなので、必要であれば固定のエンコーディングに直す。Unix 系 OS であれば `nkf` コマンドを使うなど。\n 5. 上の処理をしているならテキストファイルのパスが変わっているので適切に変更する。\n 6. 新しい CSV ファイルに「作品ID」「作品名」「テキストファイルへのパス」を出力する。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T04:15:10.197",
"id": "51453",
"last_activity_date": "2018-12-23T04:15:10.197",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "19110",
"parent_id": "51446",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51446 | 51453 | 51453 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "以下のような3次元配列をplotしたい場合、pythonですと\n\n```\n\n stage= 3×3×3 Array{Int8,3}:\n [:, :, 1] =\n 1 1 1\n 1 0 1\n 1 1 1\n \n [:, :, 2] =\n 1 0 1\n 0 0 0\n 1 0 1\n \n [:, :, 3] =\n 1 1 1\n 1 0 1\n 1 1 1\n \n```\n\nの場合は\n\n```\n\n r_list = [i for i in range(0,4)]\n X,Y,Z = np.meshgrid(r_list,r_list,r_list)\n ax.scatter(X,Y,Z,stage)\n \n```\n\nのようにmeshgridですべての座標を用意して書けますが(厳密には書いていません)、Juliaにはそういった機能はあるのでしょうか? \nネットで調べた範囲ですと、ngridが....と書いてあるところもありますが、直接的な答えは得られず質問させていただきました。\n\nご指導ご鞭撻のほどお願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T14:20:10.983",
"favorite_count": 0,
"id": "51447",
"last_activity_date": "2018-12-22T14:33:22.210",
"last_edit_date": "2018-12-22T14:33:22.210",
"last_editor_user_id": "29111",
"owner_user_id": "29111",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"python3",
"julia"
],
"title": "Juliaで3次元配列をプロットしたい(4Dplot)",
"view_count": 215
} | [] | 51447 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "LaTeXで文書の作成をしています。wrapfigure環境を用いて\n\n```\n\n \\begin{wrapfigure}{l}{.5\\hsize}\n \\begin{center}\n \\includegraphics[width=\\hsize,bb=? ? ? ?]{??.jpg}\n \\caption{???}\n \\end{center}\n \\end{wrapfigure}\n \n```\n\nのように記述すると図に文章を回り込ませることができます。また、flushleft環境を用いて\n\n```\n\n \\begin{flushleft}\n 本文\n \\end{flushleft}\n \n```\n\nとすることで、文章を左寄せにできます。 \nしかしながら、flushleft環境内でwrapfigure環境を使うと文章が回り込まなくなってしまいます。左寄せで、かつ文章を回り込ませるようにするにはどうしたらいいでしょうか。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-22T15:30:03.283",
"favorite_count": 0,
"id": "51448",
"last_activity_date": "2018-12-22T15:30:03.283",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29754",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"latex"
],
"title": "LaTeXにおいてwrapfigureとflushleftを同時に使うとwrapfigureが効かなくなることについて",
"view_count": 472
} | [] | 51448 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "整数を素因数分解する関数 factorize() を作ろうとしていて \nテンプレートの使い方で詰まっています。\n\nfactorize() を以下のように作りました。\n\n```\n\n int[] factorize(int n) {\n assert(n > 0);\n if (n == 1) return [1];\n int[] ps;\n while (n % 2 == 0) {\n ps ~= 2;\n n /= 2;\n }\n for (int i = 3; i * i <= n; i += 2) {\n while (n % i == 0) {\n ps ~= i;\n n /= i;\n }\n }\n if (n > 1) ps ~= n;\n return ps;\n }\n \n```\n\nここで引数 n を int に制限するのではなく long でも使いたいと考えています。 \nしかし、int に収まる場合は int で計算して欲しいです。 \nそのためにテンプレートを使いました。\n\n```\n\n T[] factorize(T)(T n) {\n // 略\n }\n \n```\n\n実行するとうまく動作しているように見えます。\n\n```\n\n writeln(factorize(30)); // [2, 3, 5]\n writeln(factorize(2L^^35).length); // 35\n \n```\n\nしかし、const 値を渡すとコンパイルエラーになります。\n\n```\n\n const n = 12;\n writeln(factorize(n)); // コンパイルエラー(cannot modify const expression n)\n \n```\n\n定数なので値を変更できないのが理由なので \nいったん変数で受けたいのですが書き方がわからないです。\n\nこの場合、テンプレート引数をどのように書けばよいでしょうか?",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T03:15:57.833",
"favorite_count": 0,
"id": "51452",
"last_activity_date": "2018-12-23T03:15:57.833",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "13856",
"post_type": "question",
"score": 2,
"tags": [
"d"
],
"title": "int または long 型となるテンプレート引数の書き方",
"view_count": 66
} | [] | 51452 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "mac(Mojave)を使っています。 \njarファイルは`/Library/Java/Extensions/`に置けば読み込まれるという記事*を見かけたのですが、読み込まれません。\n\n`/Library/Java/Extensions/`が参照されるようにするにはどうすればいいですか。 \n \n \n \n\n### 追記\n\n*の記事 \n<http://kuwwta.hatenablog.com/entry/2016/05/12/184608> \n<https://biojava.org/wiki/BioJava%3AGetStarted>\n\nJDKはOracleのホームページからdmgを使ってインストールしました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T07:10:33.463",
"favorite_count": 0,
"id": "51455",
"last_activity_date": "2018-12-23T16:14:29.060",
"last_edit_date": "2020-06-17T08:14:45.997",
"last_editor_user_id": "-1",
"owner_user_id": "31557",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"java",
"macos"
],
"title": "Java11でライブラリが読み込めません。",
"view_count": 596
} | [
{
"body": "${JAVA_HOME/ext配下を拡張クラスローダに載せられるのはJava 8までの仕様です。 \nMACではjava.ext.dirsシステムプロパティあたりを利用して/Library/Java/Extensions/に変更しているのでしょうか?→他サイトも含めて古い記述のようですので、拡張クラスローダのことだと理解。\n\nJAVA\n9ではモジュールシステムの導入にあわせて、廃止されていますのでここにJARファイルを置いたからといってクラスローダにのりません。環境変数CLASSPATHに乗せておくか起動時に-\ncpを利用して指定してください。依存関係もまとめて設定するのなら、maven/gradelなどを利用すると楽です。\n\n詳細は以下を参照ください。 \n<https://docs.oracle.com/javase/jp/9/migrate/toc.htm>",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T16:14:29.060",
"id": "51463",
"last_activity_date": "2018-12-23T16:14:29.060",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "10174",
"parent_id": "51455",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51455 | null | 51463 |
{
"accepted_answer_id": "51492",
"answer_count": 2,
"body": "int型変数に標準入力で数字を入力して変数に入れますが、エンターキーを入力した場合に \n無視されてまた入力を受け付ける方法を知りたいのですが教えてくれますでしょうか? \nwhile()の条件の式など思いつかないのでその辺も知りたいです。\n\n```\n\n static void Main(string[] args)\n {\n \n Console.Write(\">: \");\n int x = int.Parse(Console.ReadLine());\n Console.WriteLine(x);\n \n Console.ReadKey();\n \n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T12:11:25.907",
"favorite_count": 0,
"id": "51458",
"last_activity_date": "2018-12-25T02:19:22.323",
"last_edit_date": "2018-12-23T15:02:18.833",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c#"
],
"title": "標準入力でエンターキーの入力を無視したい。",
"view_count": 643
} | [
{
"body": "回答になってるかな?\n\n```\n\n static void Main(string[] args)\n {\n Console.Write(\">: \");\n string input;\n while ((input = Console.ReadLine().Trim()) == \"\")\n {}\n int x = int.Parse(input);\n Console.WriteLine(x);\n Console.ReadKey();\n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T04:26:57.377",
"id": "51470",
"last_activity_date": "2018-12-24T04:26:57.377",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31566",
"parent_id": "51458",
"post_type": "answer",
"score": 0
},
{
"body": "エンターキーを押したときに処理を続行するならば、特定の条件になるまでループします。\n\n下記のコードは`Console.ReadLine()`を使って数字が入力される限りループする方法と、`Console.Read()`を使って複数行の入力を受け付ける方法を例示しています。 \n`Console.ReadKey()`を使えばさらに柔軟に入力を受け付けますが、柔軟すぎてバックスペースやエンターキーによる表示の更新を自前で行う必要があるため、コードから除外しました。\n\n```\n\n using System;\n using System.Collections.Generic;\n \n namespace ConsoleApplication1\n {\n class Program\n {\n static void Main(string[] args)\n {\n // 1.単純にEnterを無視\n while (true)\n {\n Console.Write(\">: \");\n int x;\n var s = Console.ReadLine();\n if (int.TryParse(s, out x))\n {\n Console.WriteLine(string.Format(\"{0}が入力されました。\", x));\n }\n else\n {\n Console.WriteLine(string.Format(\"{0}は数字ではありません。\", s));\n break;\n }\n }\n Console.WriteLine(\"\");\n \n // 2.Console.ReadでEnterにかかわらず処理を続ける\n Console.Write(\"qで切断 >: \");\n var chars = new List<char>();\n var xs = new List<int>();\n var c = (char)Console.Read();\n while (c != 'q' && c != 'Q')\n {\n if (c == '\\n' && chars.Count > 0)\n {\n xs.Add(int.Parse(string.Concat(chars)));\n chars.Clear();\n }\n else if ('0' <= c && c <= '9')\n {\n chars.Add(c);\n }\n c = (char)Console.Read();\n }\n Console.WriteLine(\"以下の数値が入力されました。\");\n xs.ForEach(Console.WriteLine);\n \n Console.ReadKey();\n }\n }\n }\n \n```\n\n**入出力例**\n\n> >: 2099 \n> 2099が入力されました。 \n> >: 20XX \n> 20XXは数字ではありません。\n>\n> qで切断 >: 114514 \n> 11yoko14! \n> q \n> 以下の数値が入力されました。 \n> 114514 \n> 1114\n\nエンターキーを入力した時にどのような挙動を期待するのかによって回答が変わりますので、上記のコードが意図した内容でなければ質問に追記をお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T02:19:22.323",
"id": "51492",
"last_activity_date": "2018-12-25T02:19:22.323",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51458",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51458 | 51492 | 51492 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "swiftで画面回転時にあるUIView(view1)のサイズがconstraintにより変更します。 \nしかし、そのUIViewにaddSublayerで追加したAVPlayerLayerのサイズが自動的に変更しません。\n\n```\n\n // 下記、ソースの一部\n // Viewを生成.\n let videoPlayerView = AVPlayerView(frame: view1.bounds)\n // UIViewのレイヤーをAVPlayerLayerにする.\n let layer = videoPlayerView.layer as! AVPlayerLayer\n layer.videoGravity = AVLayerVideoGravity.resizeAspect\n layer.player = videoPlayer\n // レイヤーを追加する.\n view1.layer.addSublayer(layer)\n \n```\n\n上記ソースのlayerをUIview(view1)が変わったら変更させたいと思っています。画面回転時は、\n\n```\n\n override var shouldAutorotate: Bool {}\n override var supportedInterfaceOrientations: UIInterfaceOrientationMask {}\n \n```\n\nで処理できると思いますが、addSubLayerで追加したAVPlayerLayerのサイズはどうやって変更させたらいいのでしょうか?\n\nご存知の方、ご教示お願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T14:11:18.237",
"favorite_count": 0,
"id": "51460",
"last_activity_date": "2018-12-23T21:30:08.337",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "8593",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"swift"
],
"title": "画面回転時にUIViewのサイズ変更に伴いaddSublayerしたAVPlayerLayerもサイズ変更するには",
"view_count": 255
} | [
{
"body": "上記ソースだと、`AVPlayerView`の`layer`プロパティは`videoPlayerView`に紐付いているのではないでしょうか?\n\nなので、わざわざレイヤーだけを取り出して`addSubLayer`せずに、素直に`view1`に`addSubView`して、上下左右の`NSLayoutConstraint`を作成、適用するか、`InterfaceBuilder`で`view1`に`AVPlayerView`を`view1`と同じサイズにAutoLayoutを設定して`@IBOutlet`にすればいい気がします(`view1`がそもそも`AVPlayerView`でも問題無いならそのほうがいい気もします)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T21:30:08.337",
"id": "51465",
"last_activity_date": "2018-12-23T21:30:08.337",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14745",
"parent_id": "51460",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51460 | null | 51465 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "表題の通り、windows7(64bit)でCaboChaをどうしてもバインディングできません。関連Qiita記事を何度も読み直し、必要なVisual\nStudio(14.1)を導入するなどをして何度もトライしていますが、画像の通りエラーが出て一向に成功しません。\n\n環境は下記の通りです。\n\n * Python3.7.1(32bit)\n * MeCab0.996(公式の32bit)\n * CaboCha0.69\n\nどうか皆様のお力をお借りできればと思います。 \n何卒よろしくお願い致します。\n\n### 追記\n\nインストール手順ですが、\n\n 1. もしやAnacondaなので不具合が起こるのかと思い、Anaconda、mecab、cabochaをアンインストール。\n 2. python3.7.1(32bit)をインストールしPATH等も上書き。\n 3. MeCabをインストールしました。Python上でも使用可能なようdllをpython/Lib/site-packagesへコピーし、cmdからpip installコマンドでmecab-python-windowsをインストール。MeCabの動作はPython上でも全く問題ありません。\n 4. CaboCha0.69とソース(CaboCha0.69tar.bz2)を公式サイトからダウンロードし、それぞれ実行とデスクトップに解凍をしました。CaboCha単体では動作は問題ないです。\n 5. Qiita等の記事を読みつつ必要なコンパイラ等をインストールしました。\n 6. ソース内のpython/python.pyを書き換え、画像の通り実行してみてもなかなか上手くいきません。\n\n```\n\n C:\\Users\\sorshall\\Desktop\\cabocha-0.69\\python>python setup.py install\n running install\n running build\n running build_py\n running build_ext\n building '_CaboCha' extension\n C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio\\2017\\BuildTools\\VC\\Tools\\MSVC\\14.16.27023\\bin\\HostX86\\x86\\cl.exe /c /nologo /0x /W3 /GL /DNDEBUG /MD \"-IC:\\Program Files (x86)\\CaboCha\\sdk\" -IC:\\python371_32\\include -IC:\\python371_32\\include \"-IC:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio\\2017\\BuildTools\\VC\\Tools\\MSVC\\14.16.27023\\ATLMFC\\include\" \"-IC:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio\\2017\\BuildTools\\VC\\Tools\\MSVC\\14.16.27023\\include\" \"-IC:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio 9.0\\VC\\include\" \"-IC:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio\\2017\" -IC:\\python371_32\\include \"-IC:\\Program Files (x86)\\Microsoft Visual Studio\\2017\\BuildTools\\VC\\Tools\\MSVC\\14.16.27023\\include\" /EHsc /TpCaboCha_wrap.cxx /Fo build\\temp.win32-3.7\\Release\\CaboCha_wrap.obj\n CaboCha_wrap.cxx\n c:\\python371_32\\include\\pyconfig.h(59): fatal error C1083: include ファイルを開けません。'io.h':No such file or directory\n error: command 'C:\\\\Program Files (x86)\\\\Microsoft Visual Studio\\\\2017\\\\BuildTools\\\\VC\\\\Tools\\\\MSVC\\\\14.16.27023\\\\bin\\\\HostX86\\\\x86\\\\cl.exe' failed with exit status 2\n \n```\n\n### 関連記事\n\nwindowsでCaboCha-Python3バインディング \n<https://qiita.com/ayuchiy/items/d8afcffb27fcc10f6947>\n\nWindowsにCabocha 0.68をいれてPythonで係り受けを解析してみる \n<https://qiita.com/mima_ita/items/161cd869648edb30627b>",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T14:12:12.690",
"favorite_count": 0,
"id": "51461",
"last_activity_date": "2019-01-11T03:16:43.170",
"last_edit_date": "2019-01-11T03:16:43.170",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31561",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"python",
"python3",
"mecab",
"cabocha"
],
"title": "windows環境でCaboChaをPython3にバインディング出来ません。",
"view_count": 1147
} | [] | 51461 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "VirtualBoxの再インストールができなくなりました。\n\nCentOS7をゲストOSとして使っていたのですが、解像度が変更できなくなり、アンインストールをして再インストールをしたのですが、`VBoxDrv.sysをコピーできません。`と表示されました。\n\nその後も、`VBoxUSBMon.sys`,`VBoxAdp6.sys`,`VBoxNetLwf.sys`がコピーできないとなって、リブートし、CentOSを起動すると、`NtCreatFile(¥Device¥VBoxDrvStub)failed:0xc0000034`がメッセージがでて、先に進めなくなりました。\n\n対処方法を教えてください。よろしくお願いします。\n\nOS: Windows 7 \nVirtualBox: 5.12",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-23T23:44:04.993",
"favorite_count": 0,
"id": "51466",
"last_activity_date": "2018-12-24T09:21:29.413",
"last_edit_date": "2018-12-24T09:21:29.413",
"last_editor_user_id": "3068",
"owner_user_id": "31565",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"windows",
"centos",
"virtualbox"
],
"title": "VitualBoxがインストールできない",
"view_count": 151
} | [
{
"body": "再インストールの対象が仮想マシンではなく「VirtualBox」アプリ本体だとして、\n\n * 管理者権限でインストール/アンインストールを行っているか確認してください。\n * もう一度インストーラを起動してみてください。インストールされている状態なら「Repair(修復)」「Remove(削除)」の選択肢が出るはずなので、どちらかを実行してみてください。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T02:12:34.103",
"id": "51467",
"last_activity_date": "2018-12-24T02:12:34.103",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51466",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51466 | null | 51467 |
{
"accepted_answer_id": "51471",
"answer_count": 2,
"body": "LaTeX(TeX Live\n2018)の環境で、`\\csname`を用いてコントロールシーケンストークンを動的に作成したいと考えていますが、思った通りに動作しません。\n\n```\n\n \\documentclass[a4paper]{article}\n \n \\begin{document}\n \n \\def\\anaconda{OK}\n \\def\\a{a}\n % 下記のすべてsnakeと出力させたい\n 1. \\csname anaconda \\endcsname \\\\ % OKと出力されない\n 2. \\csname anacond\\a \\endcsname \\\\ % OKと出力される\n 3. \\csname \\a naconda \\endcsname \\\\ % OKと出力されない\n \n \\end{document}\n \n```\n\n`\\csname`の使い方が間違っていますでしょうか? \nネットの情報はほとんどが`\\expandafter\\def\\csname ...\n\\endcsname`の例であり、`\\csname`そのものの挙動について理解したいと思っています。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T04:11:34.887",
"favorite_count": 0,
"id": "51469",
"last_activity_date": "2018-12-24T11:48:57.130",
"last_edit_date": "2018-12-24T06:48:57.267",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "31566",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"tex"
],
"title": "csnameの挙動について",
"view_count": 392
} | [
{
"body": "`\\csname...\\endcsname` を使えば,スペースを含む制御綴を生成できます。よって,1.と3.では,`\\anaconda␣`\nという制御綴が生成・使用されています。`\\csname...\\endcsname` の場合,存在しない制御綴が呼び出されても Undefined\ncontrol sequence のエラーは出ず,`\\relax` と同等に定義されます。\n\nそれに対し,2. の例では `\\a` の後のスペースが制御綴直後のスペースということで消えるため,`\\anaconda`\nという制御綴が意図通りに呼び出せています。\n\n1.と3.においては,`a` の後のスペースを消せば,意図通りの動きをするでしょう。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T04:36:41.207",
"id": "51471",
"last_activity_date": "2018-12-24T04:36:41.207",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "2663",
"parent_id": "51469",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "これはつまり、\\csname の挙動を理解するという問題というよりは、まずは TeX\nが読み込みファイル(文字コードの羅列)からトークン列を生成するプロセスについて理解する必要があるということですよね。 \nこの辺りの情報はウェブにはあまりないので、『The TeXbook』(邦訳は『TeXブック』)や『TeX by\nTopic』などの書籍を読むのが良いでしょう。(絶版のものもありますが、大学図書館などには入っていると思います) \nウェブでは「TeX Wiki」の「マクロの作成」というページに少し解説があります。 \n<https://texwiki.texjp.org/?TeX%E5%85%A5%E9%96%80%2F%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90>",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T06:21:34.947",
"id": "51474",
"last_activity_date": "2018-12-24T06:21:34.947",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31567",
"parent_id": "51469",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51469 | 51471 | 51471 |
{
"accepted_answer_id": "51478",
"answer_count": 1,
"body": "以下リンク先で行った質問内容が抽象的だったので、こちらでより具体的な質問をさせていただきたく存じます。 \n[公開中\n作家別作品一覧拡充版:全て(CSV形式、UTF-8、zip圧縮)の「テキストファイルURL」をローカルファイルパス変換する方法](https://ja.stackoverflow.com/q/51446/3060)\n\nPython3によるコードで多数の`https://www.aozora.gr.jp/xxx`といったurlを全て`/Users/mmm/Documents/bunko_data/aozorabunko-\nmaster/xxx`という形式に変換したいのですが、どのようなコードが最も効率的に書けますか?\n\n教えていただけると助かります。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T07:22:03.710",
"favorite_count": 0,
"id": "51475",
"last_activity_date": "2022-06-16T07:23:52.817",
"last_edit_date": "2022-06-15T14:34:05.383",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"python3",
"正規表現",
"url"
],
"title": "Pythonによる複数のurlの変換方法",
"view_count": 180
} | [
{
"body": "質問からすれば正規表現無しの単純置換で出来そうな気がします。例: \n`hoge.replace('https://www.aozora.gr.jp/',\n'/Users/mmm/Documents/bunko_data/aozorabunko-master/')`",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T10:10:53.527",
"id": "51478",
"last_activity_date": "2022-06-16T07:23:52.817",
"last_edit_date": "2022-06-16T07:23:52.817",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "29212",
"parent_id": "51475",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51475 | 51478 | 51478 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "Anaconda Navigatorが起動しなくなりました。 \nアイコンをクリックしても砂時計が出るだけですぐに消えてしまう状況です。 \nOSはWindows、Anaconda Navigatorのバージョンは最新です。 \nご回答、何卒宜しくお願い致します。\n\n以下は Anaconda Prompt で試したログです。\n\n```\n\n (base) C:\\Users\\owner>anaconda navigator --reset\n usage: anaconda [-h] [--disable-ssl-warnings] [--show-traceback] [-v] [-q]\n [-V] [-t TOKEN] [-s SITE]\n ...\n anaconda: error: argument : invalid choice: 'navigator' (choose from 'auth', 'label', 'channel', 'config', 'copy', 'download', 'groups', 'login', 'logout', 'move', 'notebook', 'package', 'remove', 'search', 'show', 'upload', 'whoami')\n \n (base) C:\\Users\\owner>\n \n```\n\n## 追記\n\nハイフンを入れてやってみたのですが、上手くいきませんでした。\n\n```\n\n (base) C:\\Users\\owner>anaconda-navigator --reset\n Traceback (most recent call last):\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\qtpy\\__init__.py\", line 166, in <module>\n from PySide import __version__ as PYSIDE_VERSION # analysis:ignore\n ModuleNotFoundError: No module named 'PySide'\n \n During handling of the above exception, another exception occurred:\n \n Traceback (most recent call last):\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\Scripts\\anaconda-navigator-script.py\", line 6, in <module>\n from anaconda_navigator.app.main import main\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\anaconda_navigator\\app\\main.py\", line 22, in <module>\n from anaconda_navigator.utils.conda import is_conda_available\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\anaconda_navigator\\utils\\__init__.py\", line 15, in <module>\n from qtpy.QtGui import QIcon\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\qtpy\\__init__.py\", line 172, in <module>\n raise PythonQtError('No Qt bindings could be found')\n qtpy.PythonQtError: No Qt bindings could be found\n \n (base) C:\\Users\\owner>\n \n```\n\n##またまた追記\n\n①全てをアップデートしました。 \n②その上でresetを試みましたが前と同じエラーが出ました。 \n③anaconda-navigatorとコマンドを打つと、下のようなエラーが出ました。\n\n```\n\n (base) C:\\Users\\owner>anaconda-navigator\n Traceback (most recent call last):\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\qtpy\\__init__.py\", line 199, in <module>\n from PySide import __version__ as PYSIDE_VERSION # analysis:ignore\n ModuleNotFoundError: No module named 'PySide'\n \n During handling of the above exception, another exception occurred:\n \n Traceback (most recent call last):\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\Scripts\\anaconda-navigator-script.py\", line 6, in <module>\n from anaconda_navigator.app.main import main\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\anaconda_navigator\\app\\main.py\", line 22, in <module>\n from anaconda_navigator.utils.conda import is_conda_available\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\anaconda_navigator\\utils\\__init__.py\", line 15, in <module>\n from qtpy.QtGui import QIcon\n File \"C:\\Users\\owner\\Anaconda3\\lib\\site-packages\\qtpy\\__init__.py\", line 205, in <module>\n raise PythonQtError('No Qt bindings could be found')\n qtpy.PythonQtError: No Qt bindings could be found\n \n```\n\n④conda list anaconda-navigatorを実行すると下のようになりました。\n\n```\n\n (base) C:\\Users\\owner>conda list anaconda-navigator\n # packages in environment at C:\\Users\\owner\\Anaconda3:\n #\n # Name Version Build Channel\n anaconda-navigator 1.9.6 py36_0\n \n```\n\n⑤conda list qtを実行すると下のようになりました。\n\n```\n\n (base) C:\\Users\\owner>conda list qt\n # packages in environment at C:\\Users\\owner\\Anaconda3:\n #\n # Name Version Build Channel\n pyqt 5.9.2 py36h6538335_2\n qt 5.9.7 vc14h73c81de_0\n qtawesome 0.5.3 py36_0\n qtconsole 4.4.3 py36_0\n qtpy 1.5.2 py36_0\n \n```\n\n⑥conda list pysideを実行すると下のようになりました。\n\n```\n\n (base) C:\\Users\\owner>conda list pyside\n # packages in environment at C:\\Users\\owner\\Anaconda3:\n #\n # Name Version Build Channel\n \n```",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T09:02:57.350",
"favorite_count": 0,
"id": "51476",
"last_activity_date": "2020-07-04T11:50:10.193",
"last_edit_date": "2020-07-04T11:50:10.193",
"last_editor_user_id": "-1",
"owner_user_id": "31568",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"python3",
"anaconda"
],
"title": "Anaconda Navigatorが開けない",
"view_count": 4936
} | [
{
"body": "## コマンド名について\n\n`anaconda navigator` でなくて `anaconda-navigator` (間にハイフンが入る) です。\n\n## `No module named 'PySide'` について\n\nこのエラーは、Anaconda Navigator\nが使っている依存ライブラリのバージョンの齟齬が上手くとれなかったときに出ることがあるようです。同時に出ているエラーメッセージ `No Qt bindings\ncould be found` を見ると、特に GUI を管理する Qt\nというライブラリのバージョンがどこかのタイミングで古くなってしまい、Anaconda Navigator\nから使えなくなってしまった可能性があります。たとえば conda-forge から PySide をインストールすると Qt 5 ではなく Qt 4\nがインストールされてしまってこのエラーが出るようです。\n\nそこで、まずは `conda info` コマンドを Anaconda Prompt 上で打って、バージョンを確認してみてください。古ければ `conda\nupdate` でアップデートしてください。面倒くさければ、以下のコマンドで全てのライブラリのバージョンを一気に上げることができます。\n\n```\n\n conda update conda\n conda update --all\n \n```\n\n同様のエラーは Anaconda Navigator のバグ報告ページに\n[い](https://github.com/ContinuumIO/anaconda-issues/issues/9916)\n[く](https://github.com/ContinuumIO/anaconda-issues/issues/9072)\n[つ](https://github.com/ContinuumIO/anaconda-issues/issues/9158)\n[も](https://github.com/ContinuumIO/anaconda-issues/issues/10118)\n上げられているため、ハマる人の多いエラーのようです。上のコマンドで解決しなければ、[バグ報告ページ](https://github.com/ContinuumIO/anaconda-\nissues/issues)からエラーメッセージで検索してみて、他の解決策を探ってみてください。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T09:42:36.013",
"id": "51477",
"last_activity_date": "2018-12-26T10:42:29.933",
"last_edit_date": "2018-12-26T10:42:29.933",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "19110",
"parent_id": "51476",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51476 | null | 51477 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "ASP.NET Core でのセッションとアプリの状態 \n<https://docs.microsoft.com/ja-jp/aspnet/core/fundamentals/app-\nstate?view=aspnetcore-2.2>\n\nサンプルソース \n<https://github.com/aspnet/Docs/tree/master/aspnetcore/fundamentals/app-\nstate/samples/2.x/SessionSample>\n\n上記のチュートリアルとサンプルソースを参考にしていますが、セッションが有効になりません。 \n・リクエストをまたいでセッションの値が保持されていない \n・Cookie にセッションIDが設定されていない \nサンプルソースをそのまま実行しても同様です。 \n何か設定等が足りないのでしょうか?",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T11:12:01.143",
"favorite_count": 0,
"id": "51480",
"last_activity_date": "2022-05-31T07:06:40.717",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3925",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"asp.net",
"cookie",
"session",
"asp.net-core"
],
"title": "ASP.NET Core でのセッションの利用",
"view_count": 673
} | [
{
"body": "理由はよくわかりませんが、 \n以下の行をコメントアウトすることでセッションを使用できるようになりました。\n\nStartup.cs\n\n```\n\n options.CheckConsentNeeded = context => true;\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T12:40:42.463",
"id": "51509",
"last_activity_date": "2018-12-25T12:40:42.463",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3925",
"parent_id": "51480",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51480 | null | 51509 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "Qiitaなどで一通り確認した上でご質問します。 \n5.0.0.1から5.2を導入時に、bootsnapを入れました。それによって、以下の状況が起きており、bootsnapを外すとbootsnapが無いと表示されます。\n\nbootsnapのキャッシュもクリアしましたが無理でした。 \nお知恵をおかしください。\n\n```\n\n => Booting Puma\n => Rails 5.2.2 application starting in development \n => Run `rails server -h` for more startup options\n Exiting\n Traceback (most recent call last):\n 51: from bin/rails:4:in `<main>'\n 50: from bin/rails:4:in `require'\n 49: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands.rb:18:in `<top (required)>'\n 48: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/command.rb:46:in `invoke'\n 47: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/command/base.rb:65:in `perform'\n 46: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor.rb:387:in `dispatch'\n 45: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor/invocation.rb:126:in `invoke_command'\n 44: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor/command.rb:27:in `run'\n 43: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands/server/server_command.rb:142:in `perform'\n 42: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands/server/server_command.rb:142:in `tap'\n 41: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands/server/server_command.rb:147:in `block in perform'\n 40: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands/server/server_command.rb:51:in `start'\n 39: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands/server/server_command.rb:89:in `log_to_stdout'\n 38: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/server.rb:354:in `wrapped_app'\n 37: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/commands/server/server_command.rb:27:in `app'\n 36: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/server.rb:219:in `app'\n 35: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/server.rb:319:in `build_app_and_options_from_config'\n 34: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/builder.rb:40:in `parse_file'\n 33: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/builder.rb:49:in `new_from_string'\n 32: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/builder.rb:49:in `eval'\n 31: from config.ru:in `<main>'\n 30: from config.ru:in `new'\n 29: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/builder.rb:55:in `initialize'\n 28: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/rack-2.0.6/lib/rack/builder.rb:55:in `instance_eval'\n 27: from config.ru:3:in `block in <main>'\n 26: from config.ru:3:in `require_relative'\n 25: from /Users/hogetaro/Documents/GitHub/fictapg/config/environment.rb:5:in `<top (required)>'\n 24: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/application.rb:361:in `initialize!'\n 23: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'\n 22: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:205:in `tsort_each'\n 21: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:226:in `tsort_each'\n 20: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:347:in `each_strongly_connected_component'\n 19: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:347:in `call'\n 18: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:347:in `each'\n 17: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:349:in `block in each_strongly_connected_component'\n 16: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:431:in `each_strongly_connected_component_from'\n 15: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:350:in `block (2 levels) in each_strongly_connected_component'\n 14: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/tsort.rb:228:in `block in tsort_each'\n 13: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'\n 12: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'\n 11: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'\n 10: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/devise-4.5.0/lib/devise/rails.rb:37:in `block in <class:Engine>'\n 9: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/devise-4.5.0/lib/devise/secret_key_finder.rb:12:in `find'\n 8: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/application.rb:399:in `secrets'\n 7: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/secrets.rb:26:in `parse'\n 6: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/secrets.rb:26:in `each_with_object'\n 5: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/secrets.rb:26:in `each'\n 4: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.2/lib/rails/secrets.rb:29:in `block in parse'\n 3: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/erb.rb:876:in `result'\n 2: from /Users/hogetaro/.rbenv/versions/2.5.3/lib/ruby/2.5.0/erb.rb:876:in `eval'\n 1: from (erb):22:in `<main>'\n (erb):22:in `[]': no implicit conversion of Symbol into String (TypeError)\n \n```",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T11:40:59.867",
"favorite_count": 0,
"id": "51481",
"last_activity_date": "2018-12-24T11:40:59.867",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ruby-on-rails"
],
"title": "Rails5.0.0.1からRails5.2にアップグレードしたらPumaが立ち上がらない。",
"view_count": 113
} | [] | 51481 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "python3でBeautifulSoup4を利用して体育館の予約空き状況を確認したいのですが、ログイン方法が分かりません。手掛かりを教えて頂けないでしょうか?\n\nここにログインして→<https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/user/view/user/mypIndex.html>\n\n```\n\n <form id=\"childForm\" name=\"layoutChildBody:childForm\" method=\"post\" \n \n enctype=\"application/x-www-form-urlencoded\"\n autocomplete=\"off\" action=\"/user/view/user/mypIndex.html\">\n <input type=\"hidden\" id=\"loginJKey\" name=\"layoutChildBody:childForm:loginJKey\" value=\"??????????????\">\n <table width=\"610\" cellpadding=\"0\" class=\"tablebg2\" border=\"0\" cellspacing=\"1\">\n <tbody>\n <tr height=\"35\">\n <td colspan=\"1\" height=\"35\" width=\"150\" class=\"s-241m\" rowspan=\"1\">\n <div align=\"center\">\n <br clear=\"none\">\n <b>利用者ID</b> <font class=\"font-red\">(必須)</font><br clear=\"none\">\n <br clear=\"none\">\n </div>\n </td>\n <td colspan=\"1\" height=\"35\" class=\"s-243m\" rowspan=\"1\">\n <input type=\"text\" id=\"userid\" name=\"layoutChildBody:childForm:userid\" value=\"?????\" title=\"利用者ID\"\n maxlength=\"8\" size=\"40\"> <font class=\"font-red\">(半角数字)</font>\n </td>\n </tr>\n <tr height=\"35\">\n <td colspan=\"1\" height=\"35\" width=\"150\" class=\"s-241m\" rowspan=\"1\">\n <div align=\"center\">\n <br clear=\"none\">\n <b>パスワード</b> <font class=\"font-red\">(必須)</font><br clear=\"none\">\n <br clear=\"none\">\n </div>\n </td>\n <td colspan=\"1\" height=\"35\" class=\"s-243m\" rowspan=\"1\">\n <input type=\"password\" id=\"passwd\" name=\"layoutChildBody:childForm:passwd\" value=\"?????\" title=\"パスワード\"\n maxlength=\"8\" autocomplete=\"off\" size=\"40\"> \n <span id=\"isAlphaFlg\">\n <font class=\"font-red\">(半角英数字)</font>\n </span>\n \n <br clear=\"none\"><input id=\"passchk\" type=\"checkbox\">パスワードを表示する\n </td>\n </tr>\n </tbody>\n </table>\n <input type=\"hidden\" name=\"layoutChildBody:childForm/view/user/mypIndex.html\" value=\"layoutChildBody:childForm\"><span\n style=\"display: none; position: absolute;\"><input type=\"hidden\" name=\"te-conditions\" value=\"??????\"></span>\n </form>\n \n```\n\nここを表示したい→<https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/user/view/user/mypMain.html>\n\n以下のようなコードを実行してみたのですが、ログイン後のHTMLはいただけませんでした。\n\n```\n\n # -*- coding: utf-8 -*-\n import requests\n from bs4 import BeautifulSoup\n from urllib.parse import urljoin \n \n \n # メールアドレスとパスワードの指定\n USER = \"???????\"\n PASS = \"?????\"\n \n # セッションを開始\n session = requests.session()\n \n # ログイン\n login_info = {\n \"userid\":USER,\n \"passwd\":PASS,\n \"back\":\"/user/view/user/mypIndex.html\"\n }\n \n # アクション\n url_login = \"https://www.e-shisetsu.e-aichi.jp/user/view/user/mypMain.html\"\n res = session.post(url_login, data=login_info)\n res.raise_for_status() # エラーならここで例外を発生させる\n \n print(res.text)\n \n```",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T14:31:31.403",
"favorite_count": 0,
"id": "51484",
"last_activity_date": "2018-12-24T15:40:06.900",
"last_edit_date": "2018-12-24T15:40:06.900",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "11053",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"python3",
"beautifulsoup"
],
"title": "python3でBeautifulSoup4を利用して体育館の予約空き状況を確認したいがログインできない",
"view_count": 134
} | [] | 51484 | null | null |
{
"accepted_answer_id": "51490",
"answer_count": 1,
"body": "コードここですの部分なのですが。Taskで関数から配列が帰ってきてそれを画面に一つずつ出力したいのですがなぜエラーになるのでしょうか見当がつかないので教えてくれますでしょうか?\n\n```\n\n static async Task<sync_test[]> Thread_class(sync_test[] c,int n,string x)\n {\n if(n == 0)\n {\n return null;\n }\n \n await Task.Run(() => \n {\n \n for(int i =0; i<n; i++)\n {\n c[i].str = x;\n }\n \n });\n \n \n return c;\n }\n \n static void Main(string[] args)\n {\n string s = \"test\";\n sync_test[] ss = new sync_test[5] \n {\n new sync_test(), new sync_test(),\n new sync_test(), new sync_test(),\n new sync_test()\n }; \n \n int n = ss.Length;\n Task<sync_test[]> s2 = Thread_class(ss,n,s);\n \n \n for(int i=0; i<n; i++)\n {\n s2[i].str;//ココのコード\n \n //Console.WriteLine(s2[i].str);\n }\n \n \n //sync_test sy = new sync_test();\n //int n = sy.Lengt;\n \n Task<sync_test[]> t = Thread_class(ss,n,s);\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T14:40:53.587",
"favorite_count": 0,
"id": "51485",
"last_activity_date": "2018-12-25T00:56:42.737",
"last_edit_date": "2018-12-24T23:46:15.463",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": -1,
"tags": [
"c#"
],
"title": "Task配列の使い方が知りたい。",
"view_count": 928
} | [
{
"body": "`s2`は`Task<sync_test[]>`なので配列のタスククラスです。 \nタスクに対して直接`s2[i].str`を指定して値を取得することはできません。\n\nなぜならタスクは`<ジェネリック>`クラスの処理状況を監視するクラスとして`Status`や`IsCompleted`などのプロパティが用意されているからです。 \nタスクには処理結果を取得する`Result`プロパティも用意されているので、ココのコードを下記のように書き換えるとエラーが解消されます。\n\n```\n\n Console.WriteLine(s2.Result[i].str);\n \n```\n\nところで`Thread_class`というメソッド名は、クラス名と誤解されそうです。 \n`RunSyncTests`のように動詞から始まる名称を検討された方がよろしいかと存じます。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T00:56:42.737",
"id": "51490",
"last_activity_date": "2018-12-25T00:56:42.737",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51485",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51485 | 51490 | 51490 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "API GatewayとLambdaを利用して、RESTfulなapiを開発しているのですが、URLに日本語を含んだリクエストが文字化けしてしまいます。 \nCloudWatchのログを見ると、API Gatewayの時点で文字化けしているようです。\n\n例えば、GETで\"/list/q/画像\"にアクセスすると、CloudWatchの方では\"GET /list/q/ç»å\"というアクセスログが残っています。\n\nEC2でapacheを使ってデプロイした時は大丈夫だったのですが、API GatewayとLambdaにデプロイしたらこうなってしまいました。 \n解決策をお教えいただけないでしょうか。 \nよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T19:21:06.737",
"favorite_count": 0,
"id": "51487",
"last_activity_date": "2023-01-25T23:55:19.323",
"last_edit_date": "2023-01-25T23:55:19.323",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "12785",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"aws",
"aws-lambda",
"rest",
"aws-api-gateway"
],
"title": "API GatewayでURLに日本語を含んだリクエストが文字化けしてしまう",
"view_count": 1102
} | [] | 51487 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 2,
"body": "大変お世話になっております。\n\nあるサイト①から他のサイト②を開く際に①の値をget送信し、その開いたサイト②にて、urlから値を取得し、更に他のサイト③にその値を送信するために、その値を②にて代入する以下の様な設定が機能しております。\n\nこれをget送信でなく、method=\"post\"の様にpost送信にした場合、サイト②ではどのように取得し、値を代入すれば宜しいかご教授頂けませんでしょうか。\n\nつまり、以下のサイト①でmethod=\"post\"を使用した場合のサイト②内でのjavascriptの記述方法をご教授頂けませんでしょうか。\n\n```\n\n サイト①\n <form name=\"reserve\" method=\"get\" action=\"http://xxxx.com/send.html\">\n <input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"{$product.id}\" />\n <input type=\"submit\" value=\"送信する\" class=\"sendButton\">\n </form>\n \n \n サイト②\n http://xxxx.com/send.html?id=7\n \n <script type=\"text/javascript\"> \n const url = new URL(location.href);\n const id = url.searchParams.get(\"id\");\n </script>\n \n <script type=\"text/javascript\">\n document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {\n document.getElementById('id').value = id;\n });\n </script>\n \n <form id=\"Form\" method=\"post\" action=\"xxxxxxx\">\n <input name=\"id\" id=\"id\" type=\"hidden\" value=\"\" />\n <input type=\"submit\" value=\"送信する\" class=\"sendButton\">\n </form>\n \n```\n\n追記:\n\n```\n\n サイト①\n php:\n <?php\n $post_json_data = json_encode($_POST);\n ?>\n \n \n <form name=\"reserve\" method=\"post\" action=\"http://xxxx.com/send.html\">\n <input type=\"hidden\" name=\"id\" value=\"{$product.id}\" />\n <input type=\"hidden\" name=\"cusotmer_id\" value=\"{$smarty.get.cusotmer_id}\" />\n <input type=\"submit\" value=\"送信する\" class=\"sendButton\">\n </form>\n \n \n サイト②\n http://xxxx.com/send.html\n \n <script type=\"text/javascript\"> \n const post_data = <?php echo $post_json_data; ?>;\n </script>\n \n ***\n <h1><input type=\"text\" disabled name=\"cusotmer_id\" id=\"cusotmer_id\" value=\"\"></h1>\n \n <form id=\"Form\" method=\"post\" action=\"xxxxxxx\">\n <input name=\"id\" id=\"id\" type=\"hidden\" value=\"\" />\n <input name=\"customer_id\" id=\"customer_id\" type=\"hidden\" value=\"\" />\n <input type=\"submit\" value=\"送信する\" class=\"sendButton\">\n </form>\n \n```\n\n頂きました記述をもとに、json_encode、およびもう一方の個々に取得する方法の両者を試しておりますが、どうしても両者とも値を取得、そして設定できません。\n\n実際は、値が複数存在しますので、json_encodeで試した記述を追記に補足しました。サイト②のjavascriptで取得した値であるpost_dataはどのようにhtml上でそれぞれのvalueに設定されるのでしょうか。試しにサイト②の***でcusotmer_idを表示させてみると[object\nHTMLCollection] と表示されます。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-24T19:57:14.060",
"favorite_count": 0,
"id": "51488",
"last_activity_date": "2019-01-09T07:04:01.443",
"last_edit_date": "2018-12-25T12:55:21.983",
"last_editor_user_id": "19211",
"owner_user_id": "19211",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"javascript",
"php",
"html",
"form"
],
"title": "値をpost送信した際の送信先でのjavascriptを使用した取得、設定方法",
"view_count": 9658
} | [
{
"body": "PHPからHTML側のJavascriptにサーバ側のデータを渡す方法はいくつかありますが、 \n一般的には[json_encode](http://php.net/manual/ja/function.json-\nencode.php)を利用することが多いと思います。\n\n```\n\n <?php\n $post_json_data = json_encode($_POST);\n ?><html>\n <head>\n <head>\n <body>\n <script type=\"text/javascript\"> \n const post_data = <?php echo $post_json_data; ?>;\n </script>\n <body>\n <html>\n \n```\n\nただ今回の場合のように特定の値一つだけで、値の無害化を **確実にもれなく十分に** 実行できるような場合は直接渡してしまっても良いとは思います。\n\n```\n\n <?php\n //例として必ずidにはint型しか入らないという前提の弱い無害化\n $id = (int)$_POST[\"id\"];\n ?><html>\n <head>\n <head>\n <body>\n <script type=\"text/javascript\"> \n const id = <?php echo $id;?>;\n </script>\n <body>\n <html>\n \n```\n\n以下はWebのサーバとクライアントの基礎知識です。 \nもしご存知の場合は、飛ばして頂いてOKです。\n\nクライアントはサーバにリクエストします。 \nサーバはリクエストに対してレスポンスを返します。\n\nPHPはサーバサイドの言語、HTML側のJavascriptはクライアントサイドの言語です。 \nそしてPOSTとはクライアントサイドからリクエストする方式の一つです\n\nそのためイメージとしては \n(HTML+Javascript)→(PHP)→(HTML+Javascript)→(PHP)→(HTML+Javascript)→… \nとデータをクライアントに返す、データをサーバに送るを繰り返します。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T00:37:31.657",
"id": "51489",
"last_activity_date": "2018-12-25T00:37:31.657",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "22665",
"parent_id": "51488",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "単純にpostで'data1=a1&data2=a2&data3=a3&data4=a4'を送り、サーバからの結果をjsonで受けるサンプルを書いて見ました。\n\n```\n\n <!DOCTYPE html>\n <html>\n <head>\n <meta charset=\"UTF-8\">\n <title>Title</title>\n </head>\n <body>\n <script type=\"text/javascript\">\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n \n xhr.onreadystatechange = function() {\n if (xhr.readyState === 4) {\n if (xhr.status === 200) {\n console.log(xhr.response);\n var datas = xhr.response;\n console.log(' data1:'+datas.data1);\n console.log(' data2:'+datas.data2);\n console.log(' data3:'+datas.data3);\n console.log(' data4:'+datas.data4);\n \n } else {\n console.log(\"status = \" + xhr.status);\n }\n }\n };\n \n var senddata = 'data1=a1&data2=a2&data3=a3&data4=a4';\n \n xhr.open(\"POST\", 'index.php');\n xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');\n xhr.responseType = \"json\";\n xhr.send(senddata);\n </script>\n </body>\n </html>\n \n```\n\n**index.phpは**\n\n```\n\n <?php\n \n $data1 = $_POST['data1'];\n $data2 = $_POST['data2'];\n $data3 = $_POST['data3'];\n $data4 = $_POST['data4'];\n \n $arr_data = array('data1'=>$data1,'data2'=>$data2,'data3'=>$data3,'data4'=>$data4);\n \n $json_str = json_encode($arr_data);\n \n echo $json_str;\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T02:18:14.813",
"id": "51516",
"last_activity_date": "2018-12-26T02:18:14.813",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "22793",
"parent_id": "51488",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51488 | null | 51489 |
{
"accepted_answer_id": "51510",
"answer_count": 1,
"body": "タイトルの件、Visual Studio2015のプロジェクトで参照にVBIDEというものを加えて開発していますが、このdllは.NET\nFramework標準で利用できるものと考えてよろしでしょうか? \n(.NET Frameworkがインストールされていれば利用できますか?)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T02:59:16.720",
"favorite_count": 0,
"id": "51493",
"last_activity_date": "2018-12-25T13:56:19.807",
"last_edit_date": "2018-12-25T03:28:25.650",
"last_editor_user_id": "76",
"owner_user_id": "9228",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c#",
".net"
],
"title": "VBIDEを参照した場合、.NET Framework以外に何か必要になりますか?",
"view_count": 2835
} | [
{
"body": "「何か必要になりますか?」ではなく、ライセンスや使用方法などを考慮・検討して使用するライブラリを選定するべきだと思うのですが…?\n\n* * *\n\n質問文では「VBIDE」と書かれていますが、実際のライブラリの正式名称は「Microsoft Visual Basic for Applications\nExtensibility 5.3」と思われます。 \n.NETアプリケーションがCOM参照を行う場合、[`Tlbimp.exe`](https://docs.microsoft.com/ja-\njp/dotnet/framework/tools/tlbimp-exe-type-library-\nimporter)を用いてCOMタイプライブラリを元に同等のアセンブリを生成します。今回の場合ファイル名は`Microsoft.Vbe.Interop.dll`となっているはずです。更に[型情報の埋め込み](https://docs.microsoft.com/ja-\njp/previous-versions/visualstudio/visual-\nstudio-2010/ee317478\\(v%3Dvs.100\\))機能により、`Microsoft.Vbe.Interop.dll`の中で使用している型情報だけをピックアップしてアセンブリに埋め込むことができます(Visual\nStudio上で操作した場合、デフォルトで埋め込まれる設定となっているはずです)。 \n結果的に、.NET部分に関しては追加で必要となるモジュールはありません。\n\nただし、本体となるCOM側の「Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility\n5.3」は別途必要です。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T13:56:19.807",
"id": "51510",
"last_activity_date": "2018-12-25T13:56:19.807",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "4236",
"parent_id": "51493",
"post_type": "answer",
"score": 4
}
] | 51493 | 51510 | 51510 |
{
"accepted_answer_id": "51496",
"answer_count": 1,
"body": "私は現在、以下のようなserval_process.csvというファイル中のカラム「テキストファイルURL」を参照して、そのリンク先のzipファイルの中にあるテキストファイルを読み込もうとしています。 \nserval_process.csvと同じディレクトリ内に以下のようなpythonファイルを書いて、テキストファイルの読み込みを実践しようとしていたのですが、下のコードをどのように修正すれば目的を達成できるのかわからなくなってしまいました。\n\n```\n\n import csv\n import zipfile\n with open('serval_process.csv', 'r') as f:\n reader = csv.reader(f)\n header = next(reader) # ヘッダーを読み飛ばしたい時\n \n for row in reader:# 1行づつ取得できる\n local = row[2] #localでzipファイルのある場所\n zf = zipfile.ZipFile(local,'r') #zipファイルを読む\n fp = zf.open('***.txt','r') #アーカイブ内のテキストを読みたいが、テキストの名前***が事前にはわからない...!?\n bindata = fp.read()\n text = bindata.decode(row[3])\n #この後テキストデータを整形した上で保存したい。\n \n```\n\nどなたか最も効率的な方法をご存知の方がいれば、教えていただけると助かります。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T04:56:37.693",
"favorite_count": 0,
"id": "51494",
"last_activity_date": "2022-06-15T16:24:34.067",
"last_edit_date": "2022-06-15T16:24:34.067",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"python3",
"テキストファイル",
"圧縮"
],
"title": "Pythonを用いてzipファイル内のテキストファイル名がわからない場合に、テキストファイルを読み込むには?",
"view_count": 391
} | [
{
"body": "`zf.infolist()`でファイル一覧を取得できますので、そこからテキストファイルを取得してはいかがでしょうか。\n\n```\n\n import zipfile\n with zipfile.ZipFile('test.zip', 'r') as zf:\n files = [info.filename for info in zf.infolist() if info.filename.endswith('.txt')]\n for f in files:\n print(zf.read(f))\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T05:50:27.117",
"id": "51496",
"last_activity_date": "2018-12-25T05:50:27.117",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51494",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51494 | 51496 | 51496 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 2,
"body": "FacebookのSPRESENSEグループとの二重投稿です( _\\- -)(_ _ _)ペコリ\n\nrsp_sample.inoのメインスケッチをAdafruit GFX\nLibraryのサンプルスケッチのmock_ili9341.inoで入替えたものです。 \n最初の様々なパターンの描画は問題なく実行されますが、最後のloop()処理の繰返して下記のような例外が発生します。 \n(loop() 38回目を終了した後に発生します) \n何かのセマフォ獲得に失敗しているように思えますが、 \n・どのような例外なのでしょうか? \n・例外発生を取除く方策はありますか?\n\nハードウェア構成:SPRESENSE Main board + CXD5602PWBEXT1 + 2.8\" Adafruit TFT\nshield(ILI9341 SPI) \n実行時のシリアルコンソール表示\n\n```\n\n ILI9341 Test!\n Display Power Mode: 0xCA\n MADCTL Mode: 0xA4\n Pixel Format: 0x82\n Image Format: 0xC0\n Self Diagnostic: 0x80\n Benchmark Time (microseconds)\n Screen fill 160184\n Text 93901\n Lines 1018494\n Horiz/Vert Lines 20293\n Rectangles (outline) 15838\n Rectangles (filled) 335584\n Circles (filled) 255061\n Circles (outline) 446452\n Triangles (outline) 218124\n Triangles (filled) 234086\n Rounded rects (outline) 141263\n Rounded rects (filled) 446006\n Done!\n up_assert: Assertion failed at file:semaphore/sem_post.c line: 118 task: init\n up_dumpstate: sp: 0d04cc0c\n up_dumpstate: IRQ stack:\n up_dumpstate: base: 0d044600\n up_dumpstate: size: 00000800\n up_dumpstate: used: 000000f8\n up_dumpstate: User stack:\n up_dumpstate: base: 0d04ccb8\n up_dumpstate: size: 00001fec\n up_dumpstate: used: 000002b8\n up_stackdump: 0d04cc00: 0000007c 00000098 00000001 00000014 00000000 0d007fb7 0d03f4c8 0d011d09\n up_stackdump: 0d04cc20: 0d042a40 0d004e2d 0d0429c4 0d00185f 000007e0 000007e0 00000001 0d001805\n up_stackdump: 0d04cc40: 0d0382d2 0d0429c4 0d0382bd 0d005759 000f4240 0d0429c4 0d0429c4 0d000000\n up_stackdump: 0d04cc60: 0d03cb68 0d005795 000f4240 0d0429c4 0c295529 0d002e71 00000000 00000001\n up_stackdump: 0d04cc80: 0d042690 0d002ee7 0d053a98 0d03cb7c 0d03cb7c 0d0053c9 0d01fcdf 00000101\n up_stackdump: 0d04cca0: 00000000 00000000 00000000 0d008763 00000000 00000000 deadbeef 0d04ccc4\n up_taskdump: Idle Task: PID=0 Stack Used=0 of 0\n up_taskdump: hpwork: PID=1 Stack Used=584 of 2028\n up_taskdump: lpwork: PID=2 Stack Used=352 of 2028\n up_taskdump: lpwork: PID=3 Stack Used=352 of 2028\n up_taskdump: lpwork: PID=4 Stack Used=352 of 2028\n up_taskdump: init: PID=5 Stack Used=696 of 8172\n up_taskdump: cxd56_pm_task: PID=6 Stack Used=320 of 996\n up_taskdump: <pthread>: PID=7 Stack Used=312 of 1020\n \n```\n\nよろしくお願いします。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T05:19:16.580",
"favorite_count": 0,
"id": "51495",
"last_activity_date": "2018-12-27T11:11:43.457",
"last_edit_date": "2018-12-25T05:33:16.320",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31574",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"spresense"
],
"title": "例外の発生(up_assert: Assertion failed at file:semaphore/sem_post.c)",
"view_count": 462
} | [
{
"body": "> up_assert: Assertion failed at file:semaphore/sem_post.c line: 118 task:\n> init\n\nとのメッセージが出ているのですから、semaphore/sem_post.cというファイルの118行目に書かれている\nassert文の内容を確認してください。\n\nそして、その前提(Assertion)が成り立たなかった原因を調べていくと、問題解決の糸口が捕まえられると思います。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T05:50:43.887",
"id": "51497",
"last_activity_date": "2018-12-25T05:50:43.887",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "217",
"parent_id": "51495",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "ソニーのSPRESENSEサポート担当です。 \nお問い合わせいただきました件について、調査をいたしました。\n\n問題の原因は、ハンズオンで配布した LCDライブラリにありました。\n\n配布したファイルの中の \"Adafruit_SPITFT_Macros.h\"の 134行目~143行目の、次の記述を\n\n* * *\n```\n\n #if defined(ARDUINO_ARCH_SPRESENSE)\n #undef HSPI_BEGIN_TRANSACTION\n #define HSPI_BEGIN_TRANSACTION() HSPI_SET_CLOCK(); SPI_OBJECT.setBitOrder(MSBFIRST); SPI_OBJECT.setDataMode(SPI_MODE3)\n \n #undef SPI_BEGIN\n #define SPI_BEGIN() if(_sclk < 0){SPI_OBJECT.begin(); HSPI_BEGIN_TRANSACTION();}\n \n #undef SPI_BEGIN_TRANSACTION\n #define SPI_BEGIN_TRANSACTION()\n #endif\n \n```\n\n* * *\n\n以下のように2行追加してください。\n\n* * *\n```\n\n #if defined(ARDUINO_ARCH_SPRESENSE)\n #undef HSPI_BEGIN_TRANSACTION\n #define HSPI_BEGIN_TRANSACTION() HSPI_SET_CLOCK(); SPI_OBJECT.setBitOrder(MSBFIRST); SPI_OBJECT.setDataMode(SPI_MODE3)\n \n #undef SPI_BEGIN\n #define SPI_BEGIN() if(_sclk < 0){SPI_OBJECT.begin(); HSPI_BEGIN_TRANSACTION();}\n \n #undef SPI_BEGIN_TRANSACTION\n #define SPI_BEGIN_TRANSACTION()\n \n #undef SPI_END_TRANSACTION\n #define SPI_END_TRANSACTION()\n #endif\n \n```\n\n* * *\n\nこれで問題は解決いたします。 \nこの度は、ご報告ありがとうございました。\n\n引き続き、Spresense をよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T11:05:18.417",
"id": "51561",
"last_activity_date": "2018-12-27T11:11:43.457",
"last_edit_date": "2018-12-27T11:11:43.457",
"last_editor_user_id": "29520",
"owner_user_id": "29520",
"parent_id": "51495",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51495 | null | 51497 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "linux のメモリのスワップアウト・スワップインの単位は何で行われますか?\n\n * ページ単位(だいたい 4kb) でしょうか?\n * それとも、もうちょっと大きな、メモリ管理まわりの内部構造体の単位でしょうか?\n\nというのも、スクリプト言語を扱っていると、ヒープのフラグメンテーションが発生すると思っています。フラグメンテーションであっても、スワップが上手く効いてくれれば、そこまで問題にはならないのではないか、と思いました。(十分にスワップを積む場合)その場合、\nOS が何の単位でスワップするべき領域を決定しているのかがわりと重要になると思い、質問しています。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T06:00:27.373",
"favorite_count": 0,
"id": "51498",
"last_activity_date": "2019-06-16T10:03:15.890",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "754",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"linux",
"メモリ管理",
"スワップ"
],
"title": "linux のメモリのスワップアウト・スワップインの単位は?",
"view_count": 281
} | [
{
"body": "> linux のメモリのスワップアウト・スワップインの単位\n\nページ単位です。\n\n`sar -W` というコマンドにより、1秒辺りのスワップイン・スワップアウトの数が計測できるので、参考になるかと存じます。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T07:08:48.887",
"id": "51501",
"last_activity_date": "2018-12-25T07:08:48.887",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29826",
"parent_id": "51498",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51498 | null | 51501 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "XCodeの補完機能の使い方で質問があります。 \n[](https://i.stack.imgur.com/tFhW9.png)\n\nのように補完機能で「AVPlayerItem?」を入力し終えます。 \nその後、 \n1\\. 「▶︎」ボタンで\")\"の右側にカーソルを移動させる \n2\\. マウスポインタで\")\"の右側にカーソルを移動させる \nの方法で入力は終了しますが、なんとなくスマートではないかと感じています。 \n特にプレースホルダーの後に文字列があるような場合に、特にスマートでは無いと感じています。\n\nもっといい方法で補完機能を使えるような方法をご存知の方は、ご教授いただきたくよろしくお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T06:57:55.600",
"favorite_count": 0,
"id": "51500",
"last_activity_date": "2018-12-25T10:44:46.243",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "8593",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"xcode"
],
"title": "XCodeの補完機能の使い方",
"view_count": 95
} | [
{
"body": "placeholderがハイライトしている状態でリターンキーを叩くとそのままでいいアイテムの場合にはプレースホルダーだった文字列が、平文になります。 \nクロージャーの展開なんかはこれで充分ですよね。\n\n自分が意図した文字列(変数名)の場合はプレースホルダーがハイライトしている状態でその文字列の先頭文字を打ち始めれば、プレースホルダー文字列だったところに打ち始めた文字で始まる変数/メソッドへの補完が始まります。\n\n移動は、`option`+(`◀`|`▶︎`)\n又は`option`+`ctrl`+(`b`|`f`)で、単語境界毎に移動するので、カーソル左右移動キーを押す際に`option`キーを押しながらにすれば大抵は事足りるのではないでしょうか? \n同様に行末、行頭に移動するのであれば、`command`+(`◀`|`▶︎`)で移動可能です。\n\nXcode 10からは、`option`+`click`だけでなくキー操作でもマルチカーソルが使えるようになったらしいですが、まだ試していません",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T10:44:46.243",
"id": "51505",
"last_activity_date": "2018-12-25T10:44:46.243",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14745",
"parent_id": "51500",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51500 | null | 51505 |
{
"accepted_answer_id": "51507",
"answer_count": 1,
"body": "定義コードの「ここ」部分なのですがそこに特定のキーではない場合ループを続けるといって処理を書きたくて実装に困っています \nC言語の入門問題である[getchar()がEOFじゃないとき無限に文字を入力し続けるプログラム] \nのC#版を書きたくて困っています。\n\n```\n\n namespace ConsoleApp1\n {\n class Program\n {\n \n static void Main(string[] args)\n {\n System.ConsoleKeyInfo c;\n \n c = Console.ReadKey();\n \n while ( c != ConsoleKey.F1)//ここ\n {\n //char x = (char)Console.ReadKey().Key;\n \n //Console.WriteLine(x);\n }\n \n \n Console.WriteLine(\"end\");\n \n \n \n Console.ReadKey();\n } \n }\n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T09:45:34.930",
"favorite_count": 0,
"id": "51504",
"last_activity_date": "2018-12-26T00:13:49.630",
"last_edit_date": "2018-12-26T00:13:49.630",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c#"
],
"title": "特定のキーが入力されるまで文字を読み込み続ける処理を書きたい。",
"view_count": 1289
} | [
{
"body": "こんなかんじでいかがでしょうか\n\n```\n\n static void Main(string[] args)\n {\n while (true)\n {\n var c = Console.ReadKey();\n if (c.Key == ConsoleKey.F1)\n {\n break;\n }\n Console.WriteLine(c.KeyChar);\n }\n Console.WriteLine(\"end\");\n Console.ReadKey();\n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T12:06:11.163",
"id": "51507",
"last_activity_date": "2018-12-25T12:06:11.163",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14817",
"parent_id": "51504",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51504 | 51507 | 51507 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "301リダイレクトのコードの書き方を調べていますが、不明な点があります。 \nサンプルは、<http://example.com>を<http://www.example.com>にリダイレクトするということで\n\n```\n\n RewriteEngine on\n RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\\.com$\n RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]\n \n```\n\nとなっています。\n\n私のURLは、[http://st〇〇.sakura.ne.jp](http://st%E3%80%87%E3%80%87.sakura.ne.jp)と[http://www.st〇〇.sakura.ne.jp](http://www.st%E3%80%87%E3%80%87.sakura.ne.jp)なのですが、www無しを有にリダイレクト設定する場合、どのように記載すればよいかよく分かりません。 \nアドバイスよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T14:42:10.730",
"favorite_count": 0,
"id": "51511",
"last_activity_date": "2018-12-26T06:38:08.187",
"last_edit_date": "2018-12-26T00:20:04.037",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": "31588",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
".htaccess"
],
"title": "301リダイレクトのコードの書き方について",
"view_count": 119
} | [
{
"body": "`RewriteCond`の条件は正規表現になります。 \n`RewriteCond 【条件比較対象】 【条件式】` \n`%{HTTP_HOST}`は、ホスト名を取得します。 \n今回の場合は`st〇〇.sakura.ne.jp`を取得します。\n\n`^`は先頭を意味し、`$`は文末を意味します。 \n完全一致で比較する場合、全文を比較する必要はあるので先頭から文末まで文字列を指定します。\n\n正規表現上で使用する文字についてはエスケープが必要です。 \n`.`は正規表現上で任意の1文字を意味する文字なので、そのままでも動くと言えば動きますが、 \n`st〇〇-sakura-ne-jp`もヒットしてしまいます。 \nなので`\\.`にし、エスケープします。\n\n纏めると以下のような記述になります。\n\n```\n\n RewriteEngine on\n RewriteCond %{HTTP_HOST} ^st〇〇\\.sakura\\.ne\\.jp$\n RewriteRule ^(.*)$ http://www.st〇〇.sakura.ne.jp/$1 [R=301,L]\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:38:08.187",
"id": "51527",
"last_activity_date": "2018-12-26T06:38:08.187",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31539",
"parent_id": "51511",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51511 | null | 51527 |
{
"accepted_answer_id": "51518",
"answer_count": 1,
"body": "pythonを用いて、plotの線の色を変更したいです。 \n一般的な、「赤」「青」などの一色の線に変更するやり方はわかりますが、 \n線の途中である値に対して、線が赤になったり青になったりすることは可能でしょうか?\n\n以下に自作したscriptを示して、具体的になにを行いたいかを示します。\n\n```\n\n from pylab import *\n import random\n import numpy as np\n %matplotlib inline\n import matplotlib.pyplot as plt\n \n movements = np.arange(200)\n \n ##Storage information\n traceXs, traceYs = [], [];\n Speeds = [];\n Times = [];\n \n for trial in range(0, 1):\n ###moment information\n cur_x, cur_y = 0, 0;\n nxt_x, nxt_y = 0, 0;\n s = 100.0;\n \n traceXs.append(cur_x);\n traceYs.append(cur_y);\n Times.append(0);\n Speeds.append(s);\n \n for t in movements:\n \"\"\"\n Section for trace movements\n \"\"\"\n ###trace position of movement\n r = random.randint(0, 3)\n if r == 0:\n nxt_x, nxt_y = cur_x+1, cur_y;\n elif r == 1:\n nxt_x, nxt_y = cur_x, cur_y+1;\n elif r == 2:\n nxt_x, nxt_y = cur_x, cur_y-1;\n elif r == 3:\n nxt_x, nxt_y = cur_x-1, cur_y;\n \n traceXs.append(nxt_x);\n traceYs.append(nxt_y);\n \n #update the position for next step\n cur_x, cur_y = nxt_x, nxt_y;\n \n \n \"\"\"\n Section for trace movements\n \"\"\"\n direction = random.randint(0, 1)\n r2 = random.random();\n if direction == 0:\n s += r2;\n elif direction == 1:\n s -= r2;\n Times.append(t);\n Speeds.append(s);\n \n \n plt.figure()\n plt.plot(traceXs, traceYs)\n \n plt.figure()\n plt.scatter(Times, Speeds, s=1, c=Speeds, cmap='bwr')\n \n plt.figure()\n plt.scatter(traceXs, traceYs, s=1, c=Speeds, cmap='bwr')\n plt.colorbar()\n \n x_range = 1.1*max(abs(min(traceXs)), max(traceXs));\n y_range = 1.1*max(abs(min(traceYs)), max(traceYs));\n range_ = max(x_range, y_range)\n \n plt.xlim(-range_, range_)\n plt.ylim(-range_, range_)\n \n plt.show()\n \n```\n\n上記のscriptはrandom walkをトレースする図(図1)を作成します。 \nこの図1にスピードの変化を表す色をつけたいです。(実際にはrandom walkは一定のスピードで進むのは分かっています。)\n\n図2では移動スピードを別に計算して、それを作図したものを示します。(色はスピードの早さにより変わるようになっています。)\n\n図2で示した色を、図1でも表示したいのですが、作成方法がわかりません。\n\n自分で行えたのは、図3で示したようにscatter plotを使用して、それっぽくは表示してありますが、やはり線でつながれた状態で、色をつけたいです。\n\nもしご存知の方がおられましたら、ご教授をお願いします。",
"comment_count": 5,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-25T18:06:38.600",
"favorite_count": 0,
"id": "51512",
"last_activity_date": "2018-12-26T04:39:57.040",
"last_edit_date": "2018-12-26T03:07:17.107",
"last_editor_user_id": "29826",
"owner_user_id": "11048",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"matplotlib"
],
"title": "matplotlibでplotの線の色を変更する方法",
"view_count": 1925
} | [
{
"body": "スピードの変化に基づいて線の色を変える方法ですが、[こちら](https://matplotlib.org/examples/pylab_examples/multicolored_line.html)\nが参考になるかと思います。 \nで、上記を参考に質問に挙げられたコードを修正すると\n\n```\n\n import random\n import numpy as np\n import matplotlib.pyplot as plt\n from matplotlib.collections import LineCollection\n \n movements = np.arange(200)\n \n ##Storage information\n traceXs, traceYs = [], [];\n Speeds = [];\n Times = [];\n \n for trial in range(0, 1):\n ###moment information\n cur_x, cur_y = 0, 0;\n nxt_x, nxt_y = 0, 0;\n s = 100.0;\n \n traceXs.append(cur_x);\n traceYs.append(cur_y);\n Times.append(0);\n Speeds.append(s);\n \n for t in movements:\n \"\"\"\n Section for trace movements\n \"\"\"\n ###trace position of movement\n r = random.randint(0, 3)\n if r == 0:\n nxt_x, nxt_y = cur_x+1, cur_y;\n elif r == 1:\n nxt_x, nxt_y = cur_x, cur_y+1;\n elif r == 2:\n nxt_x, nxt_y = cur_x, cur_y-1;\n elif r == 3:\n nxt_x, nxt_y = cur_x-1, cur_y;\n \n traceXs.append(nxt_x);\n traceYs.append(nxt_y);\n \n #update the position for next step\n cur_x, cur_y = nxt_x, nxt_y;\n \n \n \"\"\"\n Section for trace movements\n \"\"\"\n direction = random.randint(0, 1)\n r2 = random.random();\n if direction == 0:\n s += r2;\n elif direction == 1:\n s -= r2;\n Times.append(t);\n Speeds.append(s);\n \n points = np.array([traceXs, traceYs]).T.reshape(-1,1,2)\n segments = np.concatenate([points[:-1], points[1:]], axis=1)\n norm = plt.Normalize(min(Speeds), max(Speeds))\n cmap = plt.cm.get_cmap('bwr')\n lc = LineCollection(segments, cmap=cmap, norm=norm)\n lc.set_array(np.array(Speeds))\n lc.set_linewidth(2)\n plt.gca().add_collection(lc)\n plt.xlim((min(traceXs),max(traceXs)))\n plt.ylim((min(traceYs),max(traceYs)))\n plt.show()\n \n```\n\nのように書けるかと思います。\n\nやっていることはほとんどサンプルと同様なので、説明はいらないと思いますが、\n\n 1. 図1の各ラインをセグメントに分割\n 2. 上記のデータより Colormapを適用した LineCollection を作成\n 3. セグメント毎の Speed を LineCollection.set_array() で渡す\n 4. axesにたいして、add_collection() にて LineCollection を追加\n\nとなります\n\n[](https://i.stack.imgur.com/jWauL.png)",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T04:39:57.040",
"id": "51518",
"last_activity_date": "2018-12-26T04:39:57.040",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "24801",
"parent_id": "51512",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51512 | 51518 | 51518 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "GoogleAppsScriptの月トリガーに26日が2つあり、25日がありません。 \n昨日26日にメール送信するように設定したトリガーが動いてしまいました。\n\nGoogleに連絡しても、サポート外とのことで対応したいただけませんでした。 \nこちらで何かわかる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。 \n[](https://i.stack.imgur.com/U2DRc.png)",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T00:21:02.697",
"favorite_count": 0,
"id": "51514",
"last_activity_date": "2018-12-26T00:21:02.697",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31589",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"google-apps-script"
],
"title": "GASの月トリガーに26日が2つあり、25日がありません",
"view_count": 90
} | [] | 51514 | null | null |
{
"accepted_answer_id": "51519",
"answer_count": 1,
"body": "現在、深層学習について勉強している状態でプログラムの構成について試行錯誤しているのですがtensorflowについて一つお聞きしたいです。 \ntensorflowではモデルを作成し、セッションを実行するまでが1セットであると認識しているのですが、これを訓練データによる学習とテストデータにテストにて用いる活性化関数を分けることは可能でしょうか? \n中間層の活性化関数を分ける事でデータの量子化を行えないかと考えています。 \n可能な限り教えていただきたいです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T02:00:59.750",
"favorite_count": 0,
"id": "51515",
"last_activity_date": "2018-12-26T04:51:23.233",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31321",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"tensorflow",
"深層学習"
],
"title": "tensorflowでテストデータと訓練データの活性化関数を分ける方法はありますか?",
"view_count": 144
} | [
{
"body": "結論から言うと可能です。 \nニューラルネットモデルのファイルを2つ作る必要があります。学習用とテスト用のモデルです。それぞれ活性化関数のみ違い、層の構造などは同じものを用意します。 \nあとは、学習を終えた後にtf.trainl.Saver()にあるsaveメソッドで学習したパラメータを保存し、テスト時にテスト用モデルでそのパラメータをロードすれば、活性化関数は異なるが学習したパラメータでテストすることができます。 \n注意して欲しいのが、活性化関数のみを変えることができると言うことです。層の構造やフィルター数、ストライドなどを変えてしまうとパラメータの要素数そのものが変わってしまうため、エラーが出ます。\n\n僕自身、試しにやってみましたが、活性化関数のみ変えただけではエラーは起こりませんでした。ご参考までに。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T04:51:23.233",
"id": "51519",
"last_activity_date": "2018-12-26T04:51:23.233",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29506",
"parent_id": "51515",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51515 | 51519 | 51519 |
{
"accepted_answer_id": "51539",
"answer_count": 1,
"body": "以下のようなコードで、フラグメントを用いたタブバーを作成していたところ、`setFragment()` \nの部分5つすべてで赤い波線が引かれ、Runすると不適格であるとエラーが出てしまいました。 \nどうすれば治るのでしょうか。どなたか教えてくださると大変助かります。\n\n```\n\n package com.example.********.*******;\n \n import android.app.Fragment;\n import android.app.FragmentTransaction;\n import android.support.annotation.NonNull;\n import android.support.design.widget.BottomNavigationView;\n import android.support.v7.app.AppCompatActivity;\n import android.os.Bundle;\n import android.view.MenuItem;\n import android.widget.FrameLayout;\n \n public class MainActivity extends AppCompatActivity {\n \n private BottomNavigationView mMainNav;\n private FrameLayout mMainFrame;\n \n private QuizFragment quizFragment;\n private CertificationFragment certificationFragment;\n private SendFragment sendFragment;\n private TakephotoFragment takephotoFragment;\n private ConsequenceFragment consequenceFragment;\n \n \n @Override\n protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {\n super.onCreate(savedInstanceState);\n setContentView(R.layout.activity_main);\n \n \n mMainFrame = (FrameLayout) findViewById(R.id.main_frame);\n mMainNav = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.main_nav);\n \n quizFragment = new QuizFragment();\n certificationFragment = new CertificationFragment();\n sendFragment = new SendFragment();\n takephotoFragment = new TakephotoFragment();\n consequenceFragment = new ConsequenceFragment();\n \n \n \n mMainNav.setOnNavigationItemSelectedListener(new BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener() {\n @Override\n public boolean onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item) {\n \n switch (item.getItemId()) {\n \n case R.id.nav_quiz :\n mMainNav.setItemBackgroundResource(R.color.colorPrimary);\n setFragment(quizFragment);\n return true;\n \n case R.id.nav_certification:\n mMainNav.setItemBackgroundResource(R.color.colorPrimary);\n setFragment(certificationFragment);\n return true;\n \n \n case R.id.nav_send:\n mMainNav.setItemBackgroundResource(R.color.colorPrimary);\n setFragment(sendFragment);\n return true;\n \n case R.id.nav_takephoto:\n mMainNav.setItemBackgroundResource(R.color.colorPrimary);\n setFragment(takephotoFragment);\n return true;\n \n case R.id.nav_consequence:\n mMainNav.setItemBackgroundResource(R.color.colorPrimary);\n setFragment(consequenceFragment);\n \n default:\n return false;\n \n }\n \n \n }\n \n private void setFragment(Fragment fragment) {\n \n FragmentTransaction fragmentTransaction = getFragmentManager().beginTransaction();\n fragmentTransaction.replace(R.id.main_frame,fragment);\n fragmentTransaction.commit();\n \n \n }\n });\n \n \n }\n }\n \n```\n\nちなみに、こちらの動画を参考に作りました。 \n[https://www.youtube.com/watch?v=EbcdMxAIr54&t=190s](https://www.youtube.com/watch?v=EbcdMxAIr54&t=190s)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T05:27:35.207",
"favorite_count": 0,
"id": "51520",
"last_activity_date": "2018-12-26T16:57:54.727",
"last_edit_date": "2018-12-26T06:21:14.783",
"last_editor_user_id": "23994",
"owner_user_id": "31592",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"java",
"android-studio",
"android-fragments"
],
"title": "フラグメントを用いたタブバーの作成中、setFragment() でエラーが出てきました。",
"view_count": 149
} | [
{
"body": "Fragmentにはフレームワークが提供するクラスと、サポートライブラリが提供するクラスがあります(パッケージが違います)。\n\n通常はサポートライブラリが提供するほうのFragmentを使うことが多いと思いますが、MainActivityではフレームワークのFragmentをimportしています。各フラグメントがどちらのクラスを使っているか確認してみてください。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T16:57:54.727",
"id": "51539",
"last_activity_date": "2018-12-26T16:57:54.727",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "319",
"parent_id": "51520",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51520 | 51539 | 51539 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 2,
"body": "以下のようなコードを書いてデータのファイルへの書き込みを試みたのですが、以下のようなエラーが出てしまいます...。 \nどのように下のコードを修正すれば、簡潔にtextデータをファイルに書き込めますでしょうか...?教えていただけると助かります。(ちなみに自分が使っているpythonはpython2でした...。)\n\nコード\n\n```\n\n with open(text_file, 'w', encoding=\"utf-8\") as fp:#エラーが発生してしまう場所\n fp.write(text)\n \n```\n\nエラー\n\n```\n\n Traceback (most recent call last):\n File \"ExtractText.py\", line 36, in <module>\n with open(text_file, 'w', encoding=\"utf-8\") as fp:\n TypeError: 'encoding' is an invalid keyword argument for this function\n \n```\n\nちなみにencoding引数を消すと以下のようなエラーになります... 。\n\nコード\n\n```\n\n with open(text_file, 'w') as fp:#エラーが発生してしまう場所\n fp.write(text)\n \n```\n\nエラー\n\n```\n\n Traceback (most recent call last):\n File \"ExtractText.py\", line 37, in <module>\n fp.write(text)\n UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-10: ordinal not in range(128)\n \n```",
"comment_count": 14,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:02:36.670",
"favorite_count": 0,
"id": "51521",
"last_activity_date": "2019-05-03T19:15:49.353",
"last_edit_date": "2018-12-26T06:28:46.340",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"テキストファイル",
"python2",
"encoding"
],
"title": "pythonにおけるopen関数のencoding引数について",
"view_count": 10673
} | [
{
"body": "プラットフォームのエンコーディングが違うのかな。 \nencoding=\"shift_jis\"とかにしてみたらできるかもしれません。",
"comment_count": 3,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:08:54.437",
"id": "51522",
"last_activity_date": "2018-12-26T06:08:54.437",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29506",
"parent_id": "51521",
"post_type": "answer",
"score": -1
},
{
"body": "読み込み時ではなく、書き込み時の\n\n```\n\n fp.write(text)\n \n```\n\nでエラーが発生しているのではないでしょうか。\n\n```\n\n for.write(text.encode(\"utf-8\"))\n \n```\n\nとできませんか?",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T13:46:55.227",
"id": "51567",
"last_activity_date": "2019-05-03T19:15:49.353",
"last_edit_date": "2019-05-03T19:15:49.353",
"last_editor_user_id": "29826",
"owner_user_id": "5997",
"parent_id": "51521",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51521 | null | 51567 |
{
"accepted_answer_id": "51529",
"answer_count": 1,
"body": "提示コードを実行すると`test`クラスのコンストラクターで例外が発生する原因を知りたいです。 \n演算子のオーバーロードをコメントにするとエラーがなくなりますので演算子のオーバーロードが原因と思われますが。対処法がわからず困っています。 \nまた \n`try catch`構文を使ってその例外を出力したいのですがクラス内ではその構文がエラーになるため \n使えません、 \n出力方法と解決法、原因などを教えてくれますでしょうか?\n\n```\n\n namespace ConsoleApp1\n {\n class Program\n {\n \n //delegate void test_del(ref int t);\n \n class test\n {\n public int x { get; set; }\n \n \n public test() { }\n \n public static test operator +(test a, test b)\n {\n //Console.WriteLine(\"演算子+\");\n test t = new test();\n \n a.x = 3;\n t = a + b;\n return t;\n \n }\n \n public void output()\n {\n Console.WriteLine(\"x:\" + x);\n }\n }\n \n \n static void Main(string[] args)\n {\n try\n {\n test a = new test();\n test b = new test();\n test c = new test();\n c = a + b;\n c.output();\n }catch(Exception ex)\n {\n Console.WriteLine(ex.Message);\n }\n \n Console.ReadKey();\n } \n }\n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:11:20.720",
"favorite_count": 0,
"id": "51523",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:20:52.537",
"last_edit_date": "2018-12-26T07:39:29.990",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": -3,
"tags": [
"c#"
],
"title": "C# 演算子のオーバーロードで原因の不明の例外が発生する原因を知りたい。",
"view_count": 1597
} | [
{
"body": "エラーメッセージはとてもとても重要です。質問中にエラーメッセージを省略することなく記載することをお勧めします。\n\nで、今回起きているのは `System.StackOverflowException` ですね? そうであるとして(違うはずがないのですが)\n\n`test.operator+` 中で `test`\nの加算を行っている=自分自身を再帰呼び出ししていて終了条件が無いため無限再帰してスタックオーバーフローに至っています。ソースコードに記述されている通りの、期待される動作がきっちり観測されていることになります。\n\nどう直すとよいかは「あなたが何をしたいのか」次第ですが、何がしたいのか、意図なり案件なりが提示コードから読み取れないのでこれ以上のアドバイスは今のところできません。\n\n* * *\n\nとはいえよくある誤りぽいのでもうちょっと解説とか。サンプルのためのサンプルでは面白くないので少し実用できるネタとして複素数を考えてみましょう\n(`System.Numerics.Complex` は既にありますがこれの再実装ってことで)\n\n直交座標系で表示するとしたら複素数クラスの基本は\n\n```\n\n public class OreComplex\n {\n public double re;\n public double im;\n public OreComplex(double r, double i)\n {\n re = r;\n im = i;\n }\n }\n \n```\n\nこれに加算演算子 `operator+` を [c#](/questions/tagged/c%23 \"'c#' のタグが付いた質問を表示\")\n流に実装するとなると、クラスの `public static` メンバにしなさいということなので `public static OreComplex\noperator +(OreComplex lh, OreComplex rh)` を「複素数の加算」になるよう適切に実装することになります。\n\nさて言語を問わず `OreComplex` の加算という操作は \n\\- `OreComplex` のメンバの演算で定義できる場合のみ考慮でき \n\\- 加算元の `OreComplex` インスタンスのどちらとも異なる新しい `OreComplex` インスタンスが生成される \nということになります。となると典型的コードは\n\n```\n\n public static OreComplex operator +(OreComplex lh, OreComplex rh)\n {\n return new OreComplex(lh.re + rh.re, lh.im + rh.im);\n }\n \n```\n\nこのコードは「 `OreComplex` の加算」という処理が「 `OreComplex` のメンバの演算→新しい `OreComplex`\nの生成」で実装できているのでプログラマの期待通りに動作します。質問で提示されたコードは `test` の加算が `test`\nのメンバの演算で定義できていない、 **`test` の加算中に `test`\nの加算を誤って行っている**ので、結果的に無限再帰に陥っています。演算子を自分で定義する際に自分自身を呼んでしまうというのは誰でもよくやりがちなミスですが、提示例はまさにこのミスを犯しています。\n\n無限ループに陥らないよう修正すれば `try ... catch` も必要ないので書かなくて済みます。\n\n演習1:ここまでで示された `OreComplex` で実際に加算するサンプルプログラムを完成させなさい\n\n演習2:乗算 `operator *` を実装して使ってみなさい",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:54:43.937",
"id": "51529",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:20:52.537",
"last_edit_date": "2018-12-28T07:20:52.537",
"last_editor_user_id": "8589",
"owner_user_id": "8589",
"parent_id": "51523",
"post_type": "answer",
"score": 11
}
] | 51523 | 51529 | 51529 |
{
"accepted_answer_id": "51530",
"answer_count": 2,
"body": "Font Awesome Freeのライセンスについて質問です。 \n参考:<https://fontawesome.com/license/free>\n\n上記URLの記載によると、Webフォントとして使う場合は、\"Downloaded Font Awesome Free files already\ncontain embedded comments with sufficient attribution\"\nとのことで、そのまま使えば良いと思うのですが、pngなどの画像にして使う場合はどのように著作権表記するのが望ましいでしょうか。 \n自サイトにリンク集のようなページを設けて、Font Awesomeへのリンクを貼れば良いでしょうか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:27:47.073",
"favorite_count": 0,
"id": "51525",
"last_activity_date": "2018-12-26T07:28:57.467",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "13492",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ライセンス",
"font"
],
"title": "Font Awesome Freeのライセンスについて",
"view_count": 7121
} | [
{
"body": "参照サイトの右側に「してもOKなこと」「してはNGなこと」リストがそれぞれありますが、png画像での利用は\n\n> **Dos (OK項目)** \n> \\- Embed FA Free in documents. (e.g. .pdf, .doc, etc.)\n\nに含まれるのではないでしょうか。\n\n唯一のNG項目が「(Font\nAwesomeの)名前を自分で作成した成果物に付けてはいけない」=「紛らわしい名前を付けてはダメ」なので、この点だけ気を付ければ問題ないと読み取れます。",
"comment_count": 3,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:44:42.057",
"id": "51528",
"last_activity_date": "2018-12-26T06:44:42.057",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51525",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "参考ページには、アイコンは[CC BY\n4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)のライセンスが付与されていると明記されていますから、これに従えば問題ありません。\n\nCC BY 4.0は著作権表記が必要なライセンスですから、原則として **著作権表記は必要** です。 \nただ、質問者さんが引用されているように、フォントファイルやJSファイル等には予め必要な著作権表記が含まれているためそのまま使用すればOKということになります。\n\npng画像としてアイコンを使用する場合は、それ単体だと著作権表記がされていませんから、別途に著作権表記をする必要があります。\n\n著作権表記の方法はCC BY 4.0に従えばOKです。一番簡単な方法は、著作権者(Font Awesome)を明記し、[Font\nAwesomeへのライセンスページへのリンク](https://fontawesome.com/license/free)を貼り、さらに[CC BY\n4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)へのリンクを貼ることです。\n\nどこにこれを記載するかについては、サイト内に「権利表記」のようなタイトルのページを設けてそこに記載するとよいと思います。法律家ではないので確実なことは申し上げられませんが、このような手法は大手のアプリ等でも行われているため問題ないかと思います。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T07:28:57.467",
"id": "51530",
"last_activity_date": "2018-12-26T07:28:57.467",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "30079",
"parent_id": "51525",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51525 | 51530 | 51530 |
{
"accepted_answer_id": "51542",
"answer_count": 1,
"body": "chromeのショートカットを使って複数ディスプレイに別の画面(Webページ)を表示しようとしています。 \n下記のコードで行おうとしているのですが、2つ目のブラウザを起動後に「プロセスは終了しているため、要求された情報は利用できません。」とエラーが出てしまいます。\n\n```\n\n [System.Runtime.InteropServices.DllImport(\"user32.dll\")]\n private static extern int MoveWindow(IntPtr hwnd, int x, int y,\n int nWidth, int nHeight, int bRepaint);\n \n public void OpenBrowser()\n { \n var display = Screen.AllScreens;\n \n try\n {\n for (int i = 0; i < display.Count(); i++)\n { \n System.Diagnostics.Process p = System.Diagnostics.Process.Start(string.Format(@\"C:\\URLList\\display{0}.lnk\", (i + 1)));\n System.Threading.Thread.Sleep(1000);\n MoveWindow(p.MainWindowHandle, display[i].Bounds.X, display[i].Bounds.Y, display[i].Bounds.Width, display[i].Bounds.Height, 1);\n \n }\n \n }catch(Exception ex)\n {\n throw ex;\n }\n }\n \n```\n\nChromeショートカット例 \nC:\\URLList\\display1.lnk (Yahoo表示用ショートカット)ディスプレイ1に表示 \nC:\\URLList\\display2.lnk (msn表示用ショートカット)ディスプレイ2に表示 \n... \nのようにChromeのショートカットを作成しています。\n\n改善方法、その他の手法がありましたらご教授お願いします。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T06:33:54.407",
"favorite_count": 0,
"id": "51526",
"last_activity_date": "2018-12-27T01:31:00.793",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "19580",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c#"
],
"title": "Windows Formアプリケーションから複数のChromeショートカットを別画面に起動したい",
"view_count": 782
} | [
{
"body": "少し強引な方法ですが、自己解決しました。\n\n```\n\n for (int i = 0; i < display.Count(); i++)\n { \n System.Diagnostics.Process p = System.Diagnostics.Process.Start(string.Format(@\"C:\\URLList\\display{0}.lnk\", (i + 1)));\n \n p.WaitForInputIdle();\n System.Threading.Thread.Sleep(1000); \n var prc = System.Diagnostics.Process.GetProcesses().ToList();\n var chrome = prc.Where(x => x.ProcessName == \"chrome\" && x.MainWindowTitle != \"\").ToList();\n foreach (var ss in chrome)\n {\n MoveWindow(ss.MainWindowHandle, display[i].Bounds.X, display[i].Bounds.Y, display[i].Bounds.Width, display[i].Bounds.Height, 1);\n }\n }\n \n```\n\n起動済のChromeプロセスを検索してそのプロセスに対して移動処理をしてあげることでうまくいきました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T01:31:00.793",
"id": "51542",
"last_activity_date": "2018-12-27T01:31:00.793",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "19580",
"parent_id": "51526",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51526 | 51542 | 51542 |
{
"accepted_answer_id": "51533",
"answer_count": 1,
"body": "[smb.conf](http://www.samba.gr.jp/project/translation/4.1/htmldocs/manpages/smb.conf.5.html#CSCPOLICY)\nの説明には以下のように書いてあるのですが、documents と programs が具体的にどのような機能なのかご存知の方はいらっしゃいませんか?\n\n> csc policy (S) \n> このパラメーターは、クライアントサイドのキャッシングポリシーを規定し、 オフラインキャッシュ機能を持つクライアントが、\n> 共有上のファイルをどのようにキャッシュするかを規定する。 有効な値は、manual, documents, programs, disable である。 \n> これらの値は、Windows のサーバー側の設定に対応している。 \n> 例えば、移動プロファイルが格納されている共有では、 csc policy = disable とすることで、 オフラインキャッシュを無効にできる。\n```\n\n> 既定値: csc policy = manual\n> 例: csc policy = programs\n> \n```\n\nsamba.org の ML には [[Samba] about csc policy\nparameter](https://lists.samba.org/archive/samba/2007-May/131501.html)\nという投稿があり、以下のように書かれています。ようするに「Windows server の機能と似たようなものだ」とのことです。\n\n> They carry the same meaning as the values by the same name when \n> configuring a Windows server. I think there is some useful \n> information here (just a quick search). \n>\n> <http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/c06621675.mspx>\n\nここに書かれたリンクはすでに無くなっているので、webarchive で、おそらくこれだろうというページを発掘しました。\n\n[Windows XP Professional Resource\nKit](https://web.archive.org/web/20070313003147/http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/reskit/c06621675.mspx)\n\nただ、このページには共有フォルダやオフラインキャッシュについての説明はありますが、 programs と documents\nの具体的な違いについては書かれていないようでした。\n\nこのページの「Files Available When Online Are Not Available When\nOffline」に一言だけ登場しますが、「ドキュメントを共有する」「アプリケーションファイルを共有する」としか書かれていません。\n\n> Automatic Caching for Documents if this share contains documents. \n> Automatic Caching for Programs if this share contains application files.\n\n * ドキュメントとは何か?\n * アプリケーションファイルとは何か?\n * 「Automatic Caching for Documents」を有効にした共有フォルダにアプリケーションファイルを置いたらどうなるのか?\n * 「Automatic Caching for Programs」を有効にした共有フォルダにドキュメントを置いたらどうなるのか?\n\n等といったことをご存知の方はいらっしゃいませんか?",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T08:13:31.490",
"favorite_count": 0,
"id": "51531",
"last_activity_date": "2018-12-26T13:10:38.853",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9592",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"samba"
],
"title": "samba の csc policy の documents と programs の違いとは?",
"view_count": 323
} | [
{
"body": "SambaやWindowsサーバのファイル共有はネットワーク経由でファイルをやり取りするので、様々な理由で切断される可能性があります(ネットワーク自体のトラブルや、クライアント=ノートPCがネットワーク外に持ち出されるなど)。\n\nネットワークが切断された状態でも、予めクライアント側でファイルをキャッシュとして保持しておき、変更があった場合はネットワークの復帰後に同期を行う仕組みが「オフラインファイル機能」であり、この仕組みに合わせた実装がSambaの`csc\npolicy`のようです。\n\n共有フォルダ上でどんなファイルが開かれるかと言うと、大きく分けて以下の二種類が考えられます。\n\n * ドキュメント \nクライアントで開いた場合、基本的には変更の可能性がある。キャッシュしたなら同期が必要。\n\n * アプリケーション \n運用次第の部分もあるが、基本的にクライアントからはリードオンリーで参照される。キャッシュが利用できるなら積極的に使った方がパフォーマンス向上も見込める。\n\n上記を踏まえて`csc policy`とWindowsサーバの振る舞いとして選択できるのは\n\n * disable (クライアント側でのオフライン利用を無効にする)\n * manual (ユーザーが手動で指定したファイルのみオフライン利用を有効にする)\n * documents (ユーザーが開いたファイルを自動でオフライン利用可能にする)\n * programs (パフォーマンスが最適になるようにする)\n\n※\"documents\"と\"programs\"はWindowsサーバのバージョンによって微妙に振る舞いは異なるようなので、Sambaの実装がどうなっているのかは自信がありません。\n\n* * *\n\n\"manual\"がデフォルトのようなので、\"documents\"や\"programs\"をうまく設定すればパフォーマンス向上が期待できるが、よっぽどのことが無い限りいじらないでおくほうが無難なのかなという気がします。\n\n**参考:**\n\n * [オフライン・ファイルを利用する - @IT](http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/578offlf/offlf_01.html)\n * [[改訂版] Sambaのすべて (googleブックス)](https://books.google.co.jp/books?id=meQeBAAAQBAJ&pg=PA245&lpg=PA245&dq=csc+policy&source=bl&ots=6WuPbWEPWA&sig=r56np-rprCsF6doU1He7sRuN2Lc&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwjS4q3JrL3fAhVZEHAKHYpyB_AQ6AEwA3oECAcQAQ#v=onepage&q&f=false)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T13:10:38.853",
"id": "51533",
"last_activity_date": "2018-12-26T13:10:38.853",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51531",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51531 | 51533 | 51533 |
{
"accepted_answer_id": "51535",
"answer_count": 1,
"body": "ご覧いただきありがとうございます。 \nvue.jsでv-forでli要素を生成します。\n\n生成が終わったらこの要素を取得し、何かしらのイベントを発火させたいと考えてます。\n\n```\n\n <ul class=\"list\">\n <li\n v-for=\"i in item\"\n :key=\"i.id\">\n <p>\n テスト\n </p>\n </li>\n </ul>\n \n```\n\nv-forで仕様している配列は、 vueのmethodsの部分で生成しています。\n\nmethodsの部分で配列を生成してからv−forで中身を生成しています。 \nこの生成したliをv-\nforが終了したタイミングで取得し、イベント発火させたいのですが、配列を生成してから、v-forが回るのでvueのどのタイミングで取得したら良いか、方法が見つかりません。\n\n知見がある方がいらっしゃれば、助けていただけるとありがたいです。 \n分かりづらい文章で申し訳ないですが、よろしくお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T08:27:33.530",
"favorite_count": 0,
"id": "51532",
"last_activity_date": "2018-12-26T15:10:08.040",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "27046",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"vue.js"
],
"title": "vue.jsのv-forで要素が生成されたタイミングを感知したい。",
"view_count": 2215
} | [
{
"body": "[`Vue.nextTick`](https://jp.vuejs.org/v2/api/index.html#Vue-nextTick) や\nvm.$nextTick() を使うことで描画後(DOM変化後)のタイミングでイベントは飛ばせるかと思いますがいかがでしょうか。\n\n[リアクティブの探求#非同期更新キュー](https://jp.vuejs.org/v2/guide/reactivity.html#%E9%9D%9E%E5%90%8C%E6%9C%9F%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC)\n\n```\n\n new Vue({\r\n el: '#app',\r\n data: {\r\n item: [],\r\n count: 0\r\n },\r\n methods: {\r\n onClick() {\r\n this.item.push(this.count++)\r\n console.log('before', this.$el.innerHTML)\r\n this.$nextTick(() => console.log('after', this.$el.innerHTML))\r\n }\r\n },\r\n })\n```\n\n```\n\n <script src=\"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.5.17/vue.js\"></script>\r\n <div id=\"app\">\r\n <ul class=\"list\">\r\n <li v-for=\"i in item\" :key=\"i.id\">\r\n <p>\r\n テスト {{i}}\r\n </p>\r\n </li>\r\n </ul>\r\n <button @click=\"onClick\">Toggle</button>\r\n </div>\n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T15:10:08.040",
"id": "51535",
"last_activity_date": "2018-12-26T15:10:08.040",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "2376",
"parent_id": "51532",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51532 | 51535 | 51535 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "自宅にあるサーバー用PCのMySQLに、自宅の別のPCからアクセスしたいのですができません。 \nMySQLのバージョンは8.0です。\n\nサーバー用PCと同じIPアドレス内にある別のPCから\n\n```\n\n mysql -u admin -p\n ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES)\n \n```\n\nとしても接続できず\n\n```\n\n mysql -h 'IPアドレス' -u admin -p \n ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'IPアドレス' (10061)\n \n```\n\nと、自宅のIPアドレスを入力しても接続できません。\n\n以下の要件は満たしています。\n\n * bind-addressは設定していない。\n * ファイアーウォールで3306は開放している。\n * MySQLのポートは3306に設定している。\n * adminは全てのIPアドレスからアクセスできるように設定している。\n\nどのようにしたらよいでしょうか。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T13:53:22.167",
"favorite_count": 0,
"id": "51534",
"last_activity_date": "2018-12-26T16:17:46.837",
"last_edit_date": "2018-12-26T14:30:14.900",
"last_editor_user_id": "23994",
"owner_user_id": "28423",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"mysql"
],
"title": "別のPCのMySQLに接続できない",
"view_count": 890
} | [
{
"body": "mysqlのアカウントはホスト名を含めて管理されています。 \nそのため、アカウント名としては アカウント名@接続ホスト名 \nでアクセスする必要があります。\n\n<https://www.dbonline.jp/mysql/connect/index3.html>\n\n接続元ホスト名の情報が正しくなければアクセスできないため、 \n以下の手順を試してみてはいかがでしょうか?\n\n<http://ext.omo3.com/linux/mysql_host.html>",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T16:17:46.837",
"id": "51536",
"last_activity_date": "2018-12-26T16:17:46.837",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "10174",
"parent_id": "51534",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51534 | null | 51536 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "PythonでVisual studio Codeのデバッグ時に変数の内容を16進で \n出来ないかと調べてみましたが、ウォッチ式で<変数名>,hで指定すると \n16進数になると言うのを見かけたのですが、出来ませんでした。 \nPythonでは無理なんでしょうか?",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-26T16:45:18.687",
"favorite_count": 0,
"id": "51538",
"last_activity_date": "2019-03-11T13:03:40.723",
"last_edit_date": "2018-12-26T22:33:54.373",
"last_editor_user_id": "31397",
"owner_user_id": "31598",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"python",
"vscode"
],
"title": "Visual Studio Codeでのウォッチ式で16進表記方法",
"view_count": 1980
} | [
{
"body": "ウォッチ式で表示する値は、ソースやデバッグコンソールで実行した時に表示される値と同じです。 \n`<変数名>,h`は[C++での表記](https://stackoverflow.com/q/39973214)を参考にされたかもしれませんが、pythonでは単純に`変数h`と解釈されて出力されます。\n\nソースやデバッグコンソールで16進数を表示する時と同様の記述で16進数をウォッチできます。 \n`hex(<変数名>)` で数値を16進数にする方法が簡単だと思います。\n\nなお手元の環境ではウォッチ式に下記の記述をすることで文字列の16進数表記を確認できました。\n\n * `ord(hoge)`\n * `\"{:x}\".format(ord(hoge))` \n`:X`で大文字表記\n\n * `binascii.hexlify(u.encode(\"utf-8\"))` \n要`import binascii`\n\n蛇足ですが、ウォッチ式はprint文を使わないので`hoge, fuga, sep=\"&\"`のようにprintで通用する構文はエラーになります。 \n",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T01:18:43.043",
"id": "51541",
"last_activity_date": "2018-12-27T01:18:43.043",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51538",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51538 | null | 51541 |
{
"accepted_answer_id": "51562",
"answer_count": 1,
"body": "rubyのloadとrequireの違いは、ドキュメントでは以下のように説明されています。\n\n> Kernel.#require は同じファイルは一度だけしかロードしませんが、 Kernel.#load は無条件にロードします。 \n> また、require は拡張子.rb や .so を自動的に補完しますが、 load は行いません。\n\nしかし、以下のプログラムではloadもrequireも正しく動作するにもかかわらず、\n\n```\n\n #! ruby253 -EWindows-31J\n # -*- mode:ruby; coding:Windows-31J -*-\n $:.push(\"c:/test/test\")\n load \"sub.rb\"\n require \"sub.rb\"\n \n```\n\n以下のプログラムではrequireのみが失敗します。loadは成功します。\n\n```\n\n #! ruby253 -EWindows-31J\n # -*- mode:ruby; coding:Windows-31J -*-\n $:.push(\"c:/テスト/test\")\n load \"sub.rb\"\n require \"sub.rb\"\n \n```\n\n動作環境はWindows7 +\nRuby2.5.3です。この挙動はrubyの仕様上正しいのか、二番目の例でrequireを成功させるにはどのように記述すべきなのか、教えていただけるとたいへん助かります。よろしくお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T03:10:31.900",
"favorite_count": 0,
"id": "51543",
"last_activity_date": "2018-12-27T11:13:13.957",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31398",
"post_type": "question",
"score": 4,
"tags": [
"ruby"
],
"title": "load と requireの違い",
"view_count": 153
} | [
{
"body": "Ruby自体の不具合と思われます。関係がありそうなIssueとして下記がありますが、未解決です。\n\n[Bug #9737: Non-ASCII characters in the path to ruby executable break require\npaths - Ruby trunk - Ruby Issue Tracking System](https://bugs.ruby-\nlang.org/issues/9737)\n\nライブラリのファイルへの絶対パス(ルートからの各ディレクトリ名及びファイル名)にASCII以外の文字が含まれていない場合は、何らかの不具合が他にも発生する可能性が高いです。これらを回避したい場合は、\n**ASCII文字のみのディレクトリ名およびファイル名を使用してください。**\n\nどうしても日本語のディレクトリ名を使いたいというのであれば、RubyのIssueへ問題を報告し、修正して貰う、または、自分でパッチを作って送りつけるしかないでしょう。\n\n* * *\n\n以下、私が手元で調べた詳細です。\n\n手元のWin 10, ruby 2.5.3p105 [x64-mingw32] (Ruby\nInstller)で確認する限り、`load`でも`require`でも\"stack level too deep\n(SystemStackError)\"が発生しました。また、読み込みすらしていない次のコードでもSystemStackErrorが発生しました。\n\n```\n\n # coding: Windows-31J\n $:.push(\"テスト\")\n puts $:\n \n```\n\nソースファイルをUTF-8にした場合は正常に動作し、`require`や`load`も問題なく動作しました。また、WSLのUbuntu環境(UTF-8)でRuby\n2.5.3および2.6.0で試したところ、`pust $:`は問題ないですが、`require`や`load`を用いた場合は次のような結果になりました。\n\n * ソースファイルがUTF-8の場合はSystemStackErrorで落ちます。\n * ソースファイルがWindows-31Jの場合はSystemStackErrorで落ちませんが、ディレクトリを辿れずライブラリファイルを見つけられません。\n\nとなりました。\n\nソースコードを見ると`$:`自体は`rb_ary_new()`で作成された普通のArrayであり、`vm->load_path`としてC上では存在します。しかし、詳しくはソースを追っていませんが、何かのタイミングでパスを展開し、キャッシュを持つようになっているようです。そこら辺の処理でASCII以外の文字の処理が再帰してSystemStackErrorになっていると思われます。\n\nOS、Rubyのバージョン、環境、パスの書き方によって異なる結果になると思われますので、質問者さんが出くわした現象では無いかも知れません。いずれにしても、ASCII以外は使わないことぐらいしか、確実な回避策は無いと思います。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T11:13:13.957",
"id": "51562",
"last_activity_date": "2018-12-27T11:13:13.957",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "7347",
"parent_id": "51543",
"post_type": "answer",
"score": 6
}
] | 51543 | 51562 | 51562 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "正規表現内で変数が使えません。 \n特定の月の日付を集計したいのですが以下ですとうまくいきませんでした。\n\n```\n\n month=input()\n re.findall(r'month/([0-9]{1,2})',data)\n \n```\n\nどうすればよいでしょうか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T06:08:24.400",
"favorite_count": 0,
"id": "51548",
"last_activity_date": "2018-12-27T08:11:21.167",
"last_edit_date": "2018-12-27T08:11:21.167",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "31192",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"python",
"python3",
"正規表現"
],
"title": "正規表現内の変数",
"view_count": 175
} | [
{
"body": "正規表現で`month`が文字列になっていることがうまくいかない原因と予想されます。 \n下記のコードのように`format`関数などで月を書き換えてみてください。\n\n```\n\n import re\n month = input() // \"01\"を入力\n \n data = \"\"\"01/30\n 01/AA\n 02/20\"\"\" \n \n print(r'month/([0-9]{1,2})') # month/({0-9]{1,2}) が出力される\n pattern = '{}/([0-9]{{1,2}})'.format(month) # r''でない場合は、{{と}}が{と}に変換される\n re.findall(pattern, data) # ['30']\n \n```\n\nそれでもうまく行かない場合はエラーメッセージなどを追記してください。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T07:19:38.167",
"id": "51549",
"last_activity_date": "2018-12-27T07:19:38.167",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51548",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51548 | null | 51549 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "速度改善などで、「改善すると〇〇 s早くなります」と書いてありますが、この『s』という単位は秒を表しているのでしょうか?\n\n[](https://i.stack.imgur.com/TmXG7.png)\n\n単位がわからず困っています。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T07:24:10.123",
"favorite_count": 0,
"id": "51550",
"last_activity_date": "2019-12-01T02:31:21.573",
"last_edit_date": "2019-12-01T02:31:21.573",
"last_editor_user_id": "32986",
"owner_user_id": "31601",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"untagged"
],
"title": "PageSpeed Insightsで表示されるスピードの単位について",
"view_count": 64
} | [
{
"body": "ドキュメントをなめて見たのですが、下記のようにあったので秒だと思います。\n\n<https://developers.google.com/speed/docs/insights/v5/about> \n`presented in seconds and milliseconds respectfully.` \n(それぞれ秒とミリ秒で表示します。)\n\nまた、画像に注釈する形で`between 1,000ms and 2,500ms.`とあり、 \n画像中で`2.3 s`となっていますので、ミリ秒の時は`ms`と表記されると思います。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T07:50:44.547",
"id": "51551",
"last_activity_date": "2018-12-27T07:50:44.547",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "7676",
"parent_id": "51550",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51550 | null | 51551 |
{
"accepted_answer_id": "51554",
"answer_count": 2,
"body": "以前の質問([https://ja.stackoverflow.com/questions/51521/pythonにおけるopen関数のencoding引数について](https://ja.stackoverflow.com/questions/51521/python%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8Bopen%E9%96%A2%E6%95%B0%E3%81%AEencoding%E5%BC%95%E6%95%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6))\nにおいて、Python2 を使っていたことで発生していた問題を Python3\nをインストールすることで解決をしようと試みたのですが、別の問題が発生してしまいました。 \nそれは、以下のコードで serval_process.csv のヘッダーを pointer.csv\nのヘッダーとして書き写そうとすると以下のようなエラーが出てしまうことです。 \nどうすればエラーを出さずに処理を実行できますでしょうか? \n教えて頂けると助かります。\n\nコード\n\n```\n\n # coding: utf-8\n import csv\n import zipfile\n import re\n #import io\n #import sys\n \n root_dir = '/Users/hoge'\n \n with open('serval_process.csv', 'r') as f:\n reader = csv.reader(f)\n #pointer.csvという新しいcsvファイルを以下で作る。\n g = open('pointer.csv', 'ab') #閉じるのを忘れずに...!\n csvWriter = csv.writer(g)\n \n header = next(reader) # ヘッダーを読み飛ばしたい時\n csvWriter.writerow(header) #エラーが出る...。\n \n for row in reader:# serval_process.csvのデータを1行づつ取得できる\n local = row[2]#localでzipファイルのある場所\n with zipfile.ZipFile(local, 'r') as zf: #zipファイルを読む\n files = [info.filename for info in zf.infolist() if info.filename.endswith('.txt')]\n for f in files:\n listData = [] #listの初期化\n listData.append(row[0])\n listData.append(row[1])\n bindata = zf.read(f)\n text = bindata.decode(row[3])#この後テキストデータを整形した上でTextに保存したい。\n #テキストの先頭にあるヘッダとフッタを削除\n text = re.split(r'\\-{5,}',text)[2]\n text = re.split(r'底本:', text)[0]\n #空白文字、改行およびタブの除去\n text = text.strip()\n #上で加工した書き込むテキストを開く。また、テキストの場所をpointer.csvに記録する。\n text_file = root_dir + '/Text/'+ f\n listData.append(text_file)\n with open(text_file, 'w', encoding=\"utf-8\") as fp:#エラーが発生してしまう場所\n fp.write(text)\n listData.append('utf-8')\n csvWriter.writerow(listData) #1行書き込み\n g.close()\n \n```\n\nエラー\n\n```\n\n Traceback (most recent call last):\n File \"ExtractText.py\", line 18, in <module>\n csvWriter.writerow(header) #エラーが出る...。\n TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T09:10:22.820",
"favorite_count": 0,
"id": "51553",
"last_activity_date": "2022-06-15T16:31:04.093",
"last_edit_date": "2022-06-15T16:31:04.093",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"python3",
"csv"
],
"title": "あるcsvファイルにある文字列のヘッダーを読み込み、別のcsvファイルのヘッダーとして書き込む方法。",
"view_count": 893
} | [
{
"body": "出力先のファイルをバイナリモードで開いているのが原因ではないでしょうか。\n\n```\n\n g = open('pointer.csv', 'ab')\n \n```\n\n出力するのが文字列なら以下を試してください。\n\n```\n\n g = open('pointer.csv', 'a')\n \n```\n\n参考: 英語版SOでの類似質問(とその回答)より \n<https://stackoverflow.com/a/33054552/2322778>",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T09:32:22.843",
"id": "51554",
"last_activity_date": "2018-12-27T09:32:22.843",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51553",
"post_type": "answer",
"score": 2
},
{
"body": "`open('pointer.csv', 'ab')`を`open('pointer.csv',\n'a')`に書き換えてください。(第2引数から`b`を削る)\n\n`open('pointer.csv',\n'ab')`で[ファイルを開く](https://docs.python.jp/3/tutorial/inputoutput.html#reading-\nand-writing-files)と、`a`追記(append)モード+バイナリモードでファイルを開きます。 \nこのモードで文字列型の`header`を書き込むと、「文字列ではなく、バイト型のオブジェクトが要求されています(意訳)」というエラーになります。\n\n> a bytes-like object is required, not 'str'\n\n※エラーメッセージを載せていただいたので、原因が特定しやすくなりました。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T09:33:47.220",
"id": "51555",
"last_activity_date": "2018-12-27T09:33:47.220",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51553",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51553 | 51554 | 51554 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 2,
"body": "エラー文にあるようにindex.blade.phpの記述に問題があると思い、ファイルを確認しましたがgetAuthIdentifierName()に関する記述が見当たらなくて、一体何が原因でエラーが起きているのかがわからず、問題の切り分けすら出来ない状態です。どなたかご回答頂けると助かります。また問題解決に向けて提示すべきファイルや環境がありましたら仰ってください。\n\nエラー文\n\n> Call to undefined method App\\User::getAuthIdentifierName() (View: \n> /Users/★★/projects/original/resources/views/originals/index.blade.php)\n\nindex.blade.php\n\n```\n\n @extends('layout')\n \n @section('content')\n <div class=\"contents row\">\n @foreach($originals as $original)\n <div class=\"content_post\" style=\"background-image: url( images/{{$original->image}} );\">\n @if (Auth::check() && Auth::user()->id == $original->user_id)\n <div class=\"more\">\n <span><img src=\"{{ asset('images/anonymous-250.jpg') }}\"></span>\n <ul class=\"more_list\">\n <li><a href=\"/original/{{$original->id}}/edit\">編集</a></li>\n <li><a href=\"/original/{{$original->id}}/delete\">削除</a></li>\n </ul>\n </div>\n @endif\n \n <p>{{ $original->text }}</p>\n <span class=\"name\">\n <a href=\"/users/{{ $original->user_id }}\">\n </a>\n </span>\n </div>\n {{ $originals->links() }}\n @endforeach\n </div>\n @endsection\n \n```\n\nuser.php(app)\n\n```\n\n <?php\n \n namespace App;\n \n use Illuminate\\Notifications\\Notifiable;\n use Illuminate\\Foundation\\Auth\\User as Authenticatable;\n use Illuminate\\Database\\Eloquent\\Model;\n \n \n class User extends Model\n {\n use Notifiable;\n \n /**\n * The attributes that are mass assignable.\n *\n * @var array\n */\n protected $fillable = [\n 'name', 'email', 'password', 'avatar',\n ];\n \n /**\n * The attributes that should be hidden for arrays.\n *\n * @var array\n */\n protected $hidden = [\n 'password', 'remember_token',\n ];\n \n public function originals()\n {\n return $this->hasMany(Original::class);\n }\n }\n \n```\n\n環境\n\n```\n\n Laravel Framework 5.7.19\n PHP 7.1.19 (cli) (built: Aug 17 2018 20:10:18) ( NTS )\n macOS Mojave 10.14.2(18C54\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T09:39:49.853",
"favorite_count": 0,
"id": "51556",
"last_activity_date": "2019-12-17T17:19:17.843",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31572",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"php",
"laravel",
"laravel-5"
],
"title": "LaravelでCall to undefined method App\\User::getAuthIdentifierName() で詰まっています。",
"view_count": 5394
} | [
{
"body": "class User extends Modelを \nclass User extends Authenticatableにしたら、 \nエラー解決しました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T10:59:40.153",
"id": "51560",
"last_activity_date": "2018-12-27T10:59:40.153",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31572",
"parent_id": "51556",
"post_type": "answer",
"score": -1
},
{
"body": "```\n\n use Illuminate\\Auth\\Authenticatable;\n use Illuminate\\Contracts\\Auth\\Authenticatable as UserContract;\n use Illuminate\\Database\\Eloquent\\Model;\n \n class User extends Model implements UserContract\n {\n use Authenticatable;\n }\n \n```\n\nが一番望ましい形ですね。 `extends` は最小限にして, `implements` \\+ `use`\nで行けるところはこっちでカバーするのがセオリーです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-12-17T17:19:17.843",
"id": "61523",
"last_activity_date": "2019-12-17T17:19:17.843",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "940",
"parent_id": "51556",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51556 | null | 61523 |
{
"accepted_answer_id": "54007",
"answer_count": 1,
"body": "LumenのStorageファサードを利用してS3にファイルを移動&コピーしたいのですが、コピーができません。エラーメッセージは以下です(今回は`/var/www/html/storage/logs/lumen.log`をコピーします、ファイルは存在します)。\n\n```\n\n File not found at path: lumen.log\n \n```\n\nfilesystems.phpの中身は以下です。\n\n```\n\n <?php\n return [\n 'disks' => [\n 'local' => [\n 'driver' => 'local',\n 'root' => storage_path('logs'),\n ],\n 's3' => [\n 'driver' => 's3',\n 'root' => storage_path('logs'),\n 'key' => env('AWS_KEY'),\n 'secret' => env('AWS_SECRET'),\n 'region' => env('AWS_REGION'),\n 'bucket' => env('AWS_BUCKET'),\n ],\n ],\n ];\n \n```\n\nそして、Storageへのアクセスは以下のようにしております。\n\n```\n\n Storage::disk('s3')->move('lumen.log', 'storage.log');\n \n```\n\nちなみに、以下はちゃんと動きましたのでアクセスの仕方が悪いわけではないと思います。\n\n```\n\n Storage::disk('local')->move('lumen.log', 'storage.log');\n \n```\n\nまた、以下はS3にファイルが作成されたので、S3の設定は問題なさそうです。\n\n```\n\n Storage::disk('s3')->push('hogehoge');\n \n```\n\ncomposer.jsonには以下を記載しております(諸々省略)。\n\n```\n\n \"laravel/lumen-framework\": \"5.5.*\",\n \"league/flysystem-aws-s3-v3\": \"~1.0\"\n \n```\n\n回答をお待ちしております。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T09:40:18.963",
"favorite_count": 0,
"id": "51557",
"last_activity_date": "2019-04-08T04:25:02.277",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "28291",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"laravel",
"amazon-s3"
],
"title": "LumenでS3にファイルを移動&コピーできない",
"view_count": 640
} | [
{
"body": "コメント欄にあるように、以下の方法で対応を行いましたので、自己回答をいたします。\n\n> メッセージから推測するに move は\n> S3バケット内でオブジェクトを移動するのではと思います。putしてからローカル上のファイルを削除すれば良さそうです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-04-08T02:50:31.077",
"id": "54007",
"last_activity_date": "2019-04-08T04:25:02.277",
"last_edit_date": "2019-04-08T04:25:02.277",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": "28291",
"parent_id": "51557",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51557 | 54007 | 54007 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "以下のコードでlocalという変数に格納されたアドレスにある圧縮ファイルを解凍しようとした場合に、もしもlocalという圧縮ファイルが存在せず、FileNotFoundErrorが発生したらlocalに対する処理を飛ばしたいです。 \nどのように以下のコードを変えれば上の問題は解決するでしょうか...?\n\nコード\n\n```\n\n # coding: utf-8\n import zipfile\n \n local = 'local.zip'\n with zipfile.ZipFile(local, 'r') as zf: #zipファイルを読む。ファイルが見つからない時の例外処理はどうすれば...。\n files = [info.filename for info in zf.infolist() if info.filename.endswith('.txt')]\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T11:17:27.867",
"favorite_count": 0,
"id": "51563",
"last_activity_date": "2022-06-15T16:55:10.057",
"last_edit_date": "2022-06-15T16:55:10.057",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"python3",
"exception"
],
"title": "with文で例外が発生した場合に、処理を飛ばす方法",
"view_count": 1317
} | [
{
"body": "### withブロック内で特定の例外が起きた際にwithブロックから出る\n\n[`contextlib.suppress`](https://docs.python.jp/3/library/contextlib.html#contextlib.suppress)\nが使えます。\n\n```\n\n #!/usr/bin/python3\n import zipfile\n from contextlib import suppress\n \n with suppress(FileNotFoundError):\n with zipfile.ZipFile(\"file.zip\", 'r') as zf:\n print(\"success:\", zf) # 何らかの処理\n \n```\n\nこのようなネストした[with文](https://docs.python.jp/3/reference/compound_stmts.html#with)は一つにしてインデントを減らせます。\n\n```\n\n with suppress(FileNotFoundError), zipfile.ZipFile(\"file.zip\", 'r') as zf:\n print(\"success:\", zf) # 何らかの処理\n \n```\n\n### コンテキスト式の例外のみ捕える\n\n上ではwithブロック内で発生した例外(`FileNotFoundError`)全てを捕えています。そうでは無く、コンテキスト式 (今回の例では\n`zipfile.ZipFile` でファイルを開く部分)での例外のみを処理したい場合は\n[`contextlib.ExitStack`](https://docs.python.jp/3/library/contextlib.html#contextlib.ExitStack)\nが使えます。\n\n```\n\n from contextlib import ExitStack\n # 略\n # for 文の末尾であるとして、 with ブロックから continue で脱出\n with ExitStack() as stack:\n try:\n zf = stack.enter_context(zipfile.ZipFile(\"file.zip\", 'r'))\n except FileNotFoundError:\n continue\n print(\"success:\", zf) # 何らかの処理\n \n```\n\n### 任意の箇所でwithブロックから抜ける\n\n上ではwith文がfor文の末尾にあるものとし、`continue` でwith文を抜けています。他にも例えば関数の末尾であれば `return`\nが使えます。しかし、with文がそういった箇所に置かれていない場合もあります。その際は、上で紹介した\n[`contextlib.suppress`](https://docs.python.jp/3/library/contextlib.html#contextlib.suppress)\nを組み合わせるとよいのではと思います。\n\n```\n\n #!/usr/bin/python3\n import zipfile\n from contextlib import suppress, ExitStack\n \n class SkipError(Exception):\n pass\n \n with suppress(SkipError), ExitStack() as stack:\n try:\n zf = stack.enter_context(zipfile.ZipFile(\"file.zip\", 'r'))\n except FileNotFoundError:\n raise SkipError(\"zip file not found\")\n \n print(\"success:\", zf) # 何らかの処理\n \n```\n\n他にも公式ドキュメントの[「`__enter__`\nメソッドからの例外をキャッチする」](https://docs.python.jp/3/library/contextlib.html#catching-\nexceptions-from-enter-methods) などが参考になります。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T08:43:48.680",
"id": "51618",
"last_activity_date": "2018-12-30T08:52:31.740",
"last_edit_date": "2018-12-30T08:52:31.740",
"last_editor_user_id": "3054",
"owner_user_id": "3054",
"parent_id": "51563",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51563 | null | 51618 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "下記のコードで`%`の部分は何をしているのでしょうか?\n\n**該当部分**\n\n```\n\n l_regex = re.compile(r'^%s*' % character[0])\n r_regex = re.compile(r'%s*$' % character[0])\n \n```\n\n**コード全体**\n\n```\n\n import re\n \n def strip_text(text, *character):\n if character:\n print(character)\n l_regex = re.compile(r'^%s*' % character[0])\n r_regex = re.compile(r'%s*$' % character[0])\n else:\n l_regex = re.compile(r'^\\s*')\n r_regex = re.compile(r'\\s*$')\n text = l_regex.sub('', text)\n text = r_regex.sub('', text)\n print(text)\n \n strip_text(' 前後のスペース文字を取り除く ')\n strip_text('XXXX前後のXを取り除くXXXX', 'X')\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T13:41:22.620",
"favorite_count": 0,
"id": "51566",
"last_activity_date": "2018-12-28T05:21:02.640",
"last_edit_date": "2018-12-28T05:21:02.640",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31606",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"python",
"正規表現"
],
"title": "Pythonの正規表現で使用しているパーセント記号は何?",
"view_count": 1721
} | [
{
"body": "これは文字列をフォーマット文字列として扱って置換しています。`%`形式の文字列フォーマットです。`%s` が後から渡された文字列に置換されています。\n\n```\n\n >>> 'aaa%sbbb' % 'あ'\n 'aaaあbbb'\n >>> 'aaa%sbbb' % 'い'\n 'aaaいbbb'\n \n```\n\nこのコードの場合は、与えられた文字列の1文字目 `character[0]` ごとに動的に正規表現を作るためにフォーマット文字列を使っています。\n\nなお、`%`を使って文字列をフォーマットするのは現在では古いやり方で、f文字列を使う新しいやり方があります。2016年の記事ですが[「Pythonの新しい文字列フォーマット\n: %記号、str.format()から文字列補完へ」](https://postd.cc/new-string-formatting-in-\npython/)などを参照してください。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-27T14:34:43.027",
"id": "51568",
"last_activity_date": "2018-12-27T14:34:43.027",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "19110",
"parent_id": "51566",
"post_type": "answer",
"score": 4
}
] | 51566 | null | 51568 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "Socket通信(TCP/Blocking I/O)において、以下のようなコードでreadを実行した際に \nEAGAINが発生した場合、その原因としてどのようなケースが考えられるのでしょうか?\n\n```\n\n while ((c = read(fileno(din), buf, bufsize)) > 0) {\n // something to do\n }\n \n```\n\nEAGAINは主にNon-Blocking I/O時に読み込むデータが無い場合等で発生する認識でしたが、 \n以下のmanの記載では、Blocking I/O時にもSO_RCVTIMEOが設定されている且つreadが \nタイムアウトした場合も発生するように読み取れます。 \n<https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-pages/man7/socket.7.html>\n\n上記記載の通り、Blocking I/OにおいてもEAGAINが発生するケースはあるのでしょうか。 \nまたあるとすれば、上記の他にどのようなケースが存在するのでしょうか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T02:40:13.693",
"favorite_count": 0,
"id": "51569",
"last_activity_date": "2020-07-06T13:01:55.220",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31608",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"linux",
"c",
"centos",
"socket",
"tcp"
],
"title": "Socket通信(TCP/Blocking I/O)において、read(recv)実行時にEAGAINが発生するケースについて",
"view_count": 3263
} | [
{
"body": "質問に記載の2ケースを想定しておけばよいと思います。(socketの`read`に関する情報は、`recvmsg`のマニュアルを参照するのがよいと思います。そこには、質問に記載の2ケースが述べられています)\n\n[Man page of RECV](https://linuxjm.osdn.jp/html/LDP_man-\npages/man2/recvmsg.2.html)\n\n「エラー」節より引用\n\n> **EAGAIN** または **EWOULDBLOCK** \n> ソケットが非停止 (nonblocking) に設定されていて 受信操作が停止するような状況になったか、 受信に時間切れ (timeout)\n> が設定されていて データを受信する前に時間切れになった。 \n> POSIX.1-2001 は、この場合にどちらのエラーを返すことも認めており、 これら 2 つの定数が同じ値を持つことも求めていない。 \n> したがって、移植性が必要なアプリケーションでは、両方の可能性を 確認すべきである。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T08:25:36.277",
"id": "51580",
"last_activity_date": "2018-12-28T12:12:13.253",
"last_edit_date": "2018-12-28T12:12:13.253",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "20098",
"parent_id": "51569",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51569 | null | 51580 |
{
"accepted_answer_id": "51594",
"answer_count": 1,
"body": "私は「[詳解\nディープラーニング](https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=72995)」の本で勉強しています. \nそこで4章でmnistのデータで簡単なニューラルネットワークを作りました. \n本ではkerasのみの実装でtensorflowがなかったのでtensorflowで同じモデルを作ることを試みました.\n\n以下コードです.\n\n```\n\n import numpy as np\n import tensorflow as tf\n from sklearn.utils import shuffle\n from sklearn.model_selection import train_test_split\n \n #70000のデータから10000だけ選ぶ\n n = len(mnist.data)\n N = 1000\n indices = np.random.permutation(range(n))[:N]\n X = mnist.data[indices]\n y = mnist.target[indices]\n \n Y = np.eye(10)[y.astype(int)]\n \n X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, train_size = 0.8)\n \n #モデルの設定\n \n n_in = len(X[0])\n n_hidden = 200\n n_out = 10\n \n x = tf.placeholder(tf.float32,shape = [None,n_in])\n t = tf.placeholder(tf.float32,shape = [None,n_out])\n \n #入力~隠れ層\n W = tf.Variable(tf.truncated_normal([n_in,n_hidden]))\n b = tf.Variable(tf.zeros([n_hidden]))\n h = tf.nn.sigmoid(tf.matmul(x,W) + b)\n \n #隠れ層~出力\n V = tf.Variable(tf.truncated_normal([n_hidden,n_out]))\n c = tf.Variable(tf.zeros([n_out]))\n y = tf.nn.softmax(tf.matmul(h,V)+ c)\n \n cross_entropy = tf.reduce_mean(-tf.reduce_sum(t * tf.log(y),reduction_indices = [1]))\n train_step = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.01).minimize(cross_entropy)\n \n correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y,1),tf.argmax(t,1))\n accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction,tf.float32))\n \n epochs = 1000\n batch_size = 100\n n_batches = epochs // batch_size\n \n #モデルの学習\n init = tf.global_variables_initializer()\n sess = tf.Session()\n sess.run(init)\n \n for epoch in range(epochs):\n X_, Y_ = shuffle(X_train,Y_train)\n \n for i in range(n_batches):\n start = batch_size * i\n end = start + batch_size\n sess.run(train_step, feed_dict = {\n x:X_[start:end],\n t:Y_[start:end]\n })\n \n accuracy_rate = accuracy.eval(session = sess, feed_dict = {\n x:X_test,\n t:Y_test\n })\n \n print(accuracy_rate)\n \n```\n\n本書ではこのモデルで87%の正解率を達成できているのですが, \n上記のコードでは65%程度です.\n\nご教示のほどよろしくお願いいたします.",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T03:59:38.300",
"favorite_count": 0,
"id": "51570",
"last_activity_date": "2018-12-29T01:47:15.430",
"last_edit_date": "2018-12-28T16:53:59.807",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31609",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"tensorflow"
],
"title": "mnistの分類問題で正答率が低すぎる",
"view_count": 1555
} | [
{
"body": "僕もこの本を持ち合わせておりまして、コードなど比較してみました。 \n1つ目の原因として、データ数が少なすぎるのではないかと考えられます。 \n質問者様のコードですと、データ数がN=1000となっていますが、本ではN=10000となっていますね。 \n僕も一応N=10000で実装してみましたが、accuracy=0.74くらいまで上がりました。 \nもう1つ考えられる原因としては、epoch数ですかね。おそらく、学習回数が少なすぎるのではないかと思います。 \n本でもepoch=1000となっていますが、多分5000くらいでやったほうがいいかもしれませんね。機械学習は、コードやデータが同じだとしても、毎回同じepochで同じaccuracyに到達するわけでわありません。なぜかというと、重みの初期値が違うからです。なので、この本の著者は運良くepoch=1000で高い精度になったんですかね笑 \n実際、epoch=5000でaccuracy=0.81まで上がりました。 \nそれか、バッチサイズをもう少し大きくするとかです。機械学習では慣習的に、2^nでバッチサイズを決めることが多いみたいです。それと、N=10000でbatch_szie=100だと少し小さすぎる印象があります。大体batch_size=256、512あたりが妥当ですかね。\n\nこの書籍はとっつきやすくわかりやすい構成で書いてありますが、誤植が多いのが玉に瑕です。なので、ある程度の機械学習の構造を理解するくらいがこの本にとってちょうど良いかもしれませんね。 \n他にも機械学習に関しての書籍はいっぱいありますし、この本を読んだ後に違う本を読んでみるのも1つの手かもしれませんね。 \n現に僕も何冊も読んで、各書籍の良いとこや理解できたとこだけを取っていってます笑",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T01:47:15.430",
"id": "51594",
"last_activity_date": "2018-12-29T01:47:15.430",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29506",
"parent_id": "51570",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51570 | 51594 | 51594 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "ruby on railsのアプリケーションはViewがVue.jsで作成されています。 \nいくつかViewの変更が必要になったので、変更した後、サーバーを再起動しましたが、変更が反映されていません。 \nいろいろ調べていくと、Vue.jsはプリコンパイルされているらしいのです。 \nなので、Vue.jsを再コンパイルしたいと思います。 \nどうすれば、再コンパイルできるでしょうか。\n\n環境は次のとおりです。 \nOS:utunbu16.04 \nruby:2.4.2 \nrails:5.1 \nVue.js:不明",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T06:46:07.260",
"favorite_count": 0,
"id": "51573",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:05:27.027",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29110",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ruby-on-rails",
"ruby",
"ubuntu",
"vue.js"
],
"title": "Vue.jsの再コンパイルがしたい",
"view_count": 254
} | [
{
"body": "単にRailsアプリのフロントアセットのコンパイルと言ってもどのような構成になっているか(ビルド環境、使用技術)によって様々な場合が存在するかと思います。\n\nRails標準のアセットパイプラインの `sprockets-rails` や `webpacker` などを利用しているアプリケーションであれば一般的に\n\n```\n\n rails assets:precompile\n \n```\n\nでプリコンパイルが行えるでしょう。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T07:05:27.027",
"id": "51575",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:05:27.027",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "2376",
"parent_id": "51573",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51573 | null | 51575 |
{
"accepted_answer_id": "51576",
"answer_count": 1,
"body": "研究で[TEPLA](http://www.cipher.risk.tsukuba.ac.jp/tepla/)という暗号計算ライブラリを利用しています。\n\nWindowsでTEPLAを利用するために、Cygwinの導入とTEPLAのインストールを終え、サンプルプログラムを以下のコマンドで実行したところエラーが発生しています。\n\n```\n\n $ gcc sample.c -o sample -ltepla -lgmp -lcrypto\n /usr/lib/gcc/x86_64-pc-cygwin/7.3.0/../../../../x86_64-pc-cygwin/bin/ld: -ltepla が見つかりません\n collect2: エラー: ld はステータス 1 で終了しました\n \n```\n\n静的ライブラリは`/usr/local/lib`に`libtepla.a`が存在しているのでエラーの原因がわかりません。 \n原因の調査法や解決法等教えていただけると嬉しいです。 \nよろしくおねがいします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T07:05:06.033",
"favorite_count": 0,
"id": "51574",
"last_activity_date": "2018-12-28T12:21:14.247",
"last_edit_date": "2018-12-28T12:21:14.247",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31611",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"gcc",
"cygwin"
],
"title": "Cygwin環境下での静的ライブラリのリンクエラー",
"view_count": 1270
} | [
{
"body": "参照しようとしているライブラリが標準パス以外にある場合は、`-L`オプションで明示的にディレクトリを追加してみてください。\n\n今回の場合であれば`-L/usr/local/lib`を追加して\n\n```\n\n $ gcc sample.c -o sample -L/usr/local/lib -ltepla -lgmp -lcrypto\n \n```",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T07:12:28.893",
"id": "51576",
"last_activity_date": "2018-12-28T07:12:28.893",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51574",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51574 | 51576 | 51576 |
{
"accepted_answer_id": "51601",
"answer_count": 1,
"body": "ReactでIE11向けサイトを作成しているのですが、 \nChromeでは使用できるarrow関数がIE11では構文エラーとなってしまいます。\n\n`@babel/plugin-transform-arrow-functions`\nはarrow関数をfunctionに変換してくれるプラグインだという認識ですが正しいでしょうか。 \nbuildした際にarrow関数が残ってしまいます。\n\n[](https://i.stack.imgur.com/CaY1Q.png)\n\n設定は下記になります。\n\n**package.json**\n\n```\n\n \"dependencies\": {\n \"@babel/runtime\": \"^7.2.0\",\n \"@fortawesome/fontawesome-svg-core\": \"^1.2.8\",\n \"@fortawesome/free-solid-svg-icons\": \"^5.5.0\",\n \"@fortawesome/react-fontawesome\": \"^0.1.3\",\n \"aglio\": \"^2.3.0\",\n \"axios\": \"^0.18.0\",\n \"bootstrap\": \"^4.1.3\",\n \"bootstrap-daterangepicker\": \"^3.0.3\",\n \"echarts\": \"^4.2.0-rc.2\",\n \"echarts-for-react\": \"^2.0.15-beta.0\",\n \"getstorybook\": \"^1.7.0\",\n \"global\": \"^4.3.2\",\n \"jquery\": \"^3.3.1\",\n \"mobx\": \"4\",\n \"mobx-react\": \"^5.3.6\",\n \"moment\": \"^2.22.2\",\n \"prop-types\": \"^15.6.2\",\n \"react\": \"^16.6.1\",\n \"react-bootstrap-daterangepicker\": \"^4.1.0\",\n \"react-content-loader\": \"^3.4.1\",\n \"react-dom\": \"^16.6.1\",\n \"react-global-configuration\": \"^1.3.0\",\n \"react-icons\": \"^3.2.2\",\n \"react-loading\": \"^2.0.3\",\n \"react-loading-skeleton\": \"^1.0.0\",\n \"react-router-dom\": \"^4.3.1\",\n \"reactstrap\": \"^6.5.0\"\n },\n \"devDependencies\": {\n \"@babel/core\": \"^7.1.5\",\n \"@babel/plugin-proposal-class-properties\": \"^7.1.0\",\n \"@babel/plugin-proposal-decorators\": \"^7.1.2\",\n \"@babel/plugin-transform-arrow-functions\": \"^7.2.0\",\n \"@babel/polyfill\": \"^7.2.5\",\n \"@babel/preset-env\": \"^7.1.5\",\n \"@babel/preset-react\": \"^7.0.0\",\n \"@storybook/react\": \"^4.0.8\",\n \"babel-loader\": \"^8.0.4\",\n \"babel-plugin-transform-runtime\": \"^6.23.0\",\n \"css-loader\": \"^1.0.1\",\n \"ol\": \"^5.3.0\",\n \"style-loader\": \"^0.23.1\",\n \"styled-components\": \"^4.1.1\",\n \"uniqid\": \"^5.0.3\",\n \"url-loader\": \"^1.1.2\",\n \"uuid\": \"^3.3.2\",\n \"webpack\": \"^4.25.1\",\n \"webpack-cli\": \"^3.1.2\",\n \"webpack-dev-server\": \"^3.1.10\",\n \"write-file-webpack-plugin\": \"^4.4.1\"\n },\n \n```\n\n**webpack.config.js**\n\n```\n\n // webpack.confing.js\n \n const path = require('path')\n const WriteFilePlugin = require('write-file-webpack-plugin')\n \n module.exports = {\n mode: 'development',\n entry: ['./src/app.js'],\n output: {\n path: path.resolve(__dirname, './'),\n filename: 'public/build.min.js'\n },\n plugins : [\n new WriteFilePlugin(),\n ],\n module: {\n rules: [\n {\n test: /\\.js$/,\n exclude: /node_modules/,\n loader: 'babel-loader',\n query: {\n babelrc: false,\n presets: [\n ['@babel/preset-env', {\n useBuiltIns : 'usage',\n targets : {\n browsers : [\n 'last 2 versions',\n 'ie >= 11',\n ],\n },\n }],\n '@babel/preset-react',\n ],\n plugins: [\n ['@babel/plugin-proposal-decorators', {\n legacy: true\n }],\n ['@babel/plugin-proposal-class-properties', {\n loose: true\n }],\n ['@babel/plugin-transform-runtime', {\n regenerator : true,\n }],\n ['@babel/plugin-transform-arrow-functions', {\n spec : false,\n }],\n ]\n }\n },\n {\n test: /\\.css$/,\n use: ['style-loader', 'css-loader?modules']\n },\n {\n test: /\\.scss$/,\n use: ['style-loader', 'css-loader', 'sass-loader']\n },\n {\n test: /\\.(pdf|jpg|png|gif|svg|ico)$/,\n use: ['url-loader']\n }\n ]\n },\n resolve: {\n extensions: ['.js', '.jsx']\n },\n devServer: {\n contentBase: path.join(__dirname, './public'),\n compress: true,\n port: 9000\n }\n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T07:28:35.933",
"favorite_count": 0,
"id": "51577",
"last_activity_date": "2021-04-04T00:57:09.890",
"last_edit_date": "2021-04-04T00:57:09.890",
"last_editor_user_id": "32986",
"owner_user_id": "20868",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"reactjs",
"internet-explorer",
"axios"
],
"title": "IE11でarrow関数の変換ができない @babel/plugin-transform-arrow-functions が機能しない",
"view_count": 2610
} | [
{
"body": "問題は`react-global-configuration`が依存しているパッケージである`serialize-\njavascript`内でアロー関数が使用されている点にあります。ご提示の`babel-loader`の設定に`exclude:\n/node_modules/`とありますから、`node_modules`内にある依存モジュールに対してはbabelの処理が行なわれていません。\n\n実は、この問題は`serialize-\njavascript`側で[昨日修正されました](https://github.com/yahoo/serialize-\njavascript/pull/42)。ですので、以下のコマンドを実行して`serialize-\njavascript`を最新版にアップデートしてからビルドし直すことで解決すると思われます。\n\n```\n\n npm update serialize-javascript --depth 2\n \n```\n\n* * *\n\nこれは余談ですが、`@babel/plugin-transform-arrow-functions`は不要ではないかと思います。\n\n今回は`@babel/preset-env`が使用されており、アロー関数もこれで処理されてしまうためです。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T09:25:23.730",
"id": "51601",
"last_activity_date": "2018-12-29T12:08:28.780",
"last_edit_date": "2018-12-29T12:08:28.780",
"last_editor_user_id": "30079",
"owner_user_id": "30079",
"parent_id": "51577",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51577 | 51601 | 51601 |
{
"accepted_answer_id": "51581",
"answer_count": 1,
"body": "Raspberry Pi 3Bの解像度を4K(3840x2160)にしたいです。 \nRasberry Pi 3Bで4K表示をする方法がわかりましたら教えてください。\n\nやりたいこと \nWEBブラウザを起動して、フルスクリーンで4K画像を表示したい。\n\n試したこと \nraspi-configで解像度の変更を試みましたが、 \n3840x2160の項目はありませんでした。\n\n1920x1080で出力ができました。\n\nUbutu 18 LTSやDebianをインストールしたPCだと \n3840x2160出力ができたことから、 \nRaspbianの設定でできるのではないか?と思っています。\n\n下記を参考に、/boot/config.txtにhdmi_cvtなどの項目を記述しましたが \n4K表示ができず、画面に信号がない状態になりました。\n\n<https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=79330> \ntvserviceコマンドの実行結果も1920x1080のままです。\n\n動作環境 \nRaspberry Pi3B \nOS: Raspbian stretch \n2018-11-13-raspbian-stretch-full.img \nテレビ:AQUOS LC-50US45 [50インチ]\n\nRP3Bで4Kで出力した事がある方がおりましたら \n設定方法を教えて頂けると幸いです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T07:41:35.767",
"favorite_count": 0,
"id": "51578",
"last_activity_date": "2018-12-28T09:13:05.887",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "15346",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"raspberry-pi"
],
"title": "Raspberry Pi 3Bの解像度を4K(3840x2160)にしたい",
"view_count": 1975
} | [
{
"body": "テレビ側が対応していないと思われます。 \n参考にされた記事にはリフレッシュレート15Hzとありますが、使用されているテレビでは未サポートです。\n\n> I have managed to get 3840 x 2160 (4k x 2k) at 15Hz\n\n[アクオストップ 製品ラインアップ US45ライン LC-50US45\n外観・仕様](http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc50us45_spec.html)\n\n> (注16)\n> 480i,480p,1080i,720p(30/60Hz),1080p(24/30/60Hz),3840×2160p(24/30/60Hz)入力対応。\n\n15Hzをサポートしているテレビ・モニターを入手して試してみましょう。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T09:13:05.887",
"id": "51581",
"last_activity_date": "2018-12-28T09:13:05.887",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51578",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51578 | 51581 | 51581 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "以下がソースですが、画像の箇所にミスがあるようですが、わからないです。 \nどなたか助けて頂けないでしょうか。 \n宜しくお願い致します。\n\n以下ソース\n\n```\n\n <html>\n <head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\n <title></title>\n <style type=\"text/css\">\n <!--\n @page{\n margin:0;\n padding:0;\n size:290px 130px;\n }\n body {\n font-family: \"メイリオ\", Meiryo, \"MS Pゴシック\", \"ヒラギノ角ゴ Pro W3\", \"Hiragino Kaku Gothic Pro\", Osaka, sans-serif;\n padding: 0;\n margin: 0;\n background-color: #ffffff;\n }\n table,\n td {\n border-collapse: collapse;\n mso-table-lspace: 0;\n mso-table-rspace: 0;\n border-spacing: 0;\n }\n td {\n word-break:break-all;\n }\n a {\n text-decoration: underline;\n }\n body, table, td, a {\n -webkit-text-size-adjust:100%;\n -ms-text-size-adjust:100%;\n }\n img {\n border: 0 none;\n height: auto;\n line-height: 1;\n outline: none;\n text-decoration: none;\n vertical-align: middle;\n -ms-interpolation-mode:bicubic;\n }\n a img {\n border: 0 none;\n text-decoration: none;\n }\n span {\n display: inline;\n }\n -->\n </style>\n </head>\n <body>\n \n <table width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" style=\"width:100% !important; max-width:306px; padding: 0 0 10px;mso-line-height-rule:exactly;font-size: 0;\">\n <tr>\n <td width=\"306\" valign=\"top\" style=\"width: 306px\">\n \n <div style=\"width: 100%; min-width: 300px; max-width: 306px;display: inline-block;vertical-align: top;\" class=\"col2_column\">\n <table width=\"100%\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n <tr>\n <td align=\"left\" valign=\"top\" style=\"padding:0 10px 10px;\">\n <table width=\"100%\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"60\" align=\"left\" valign=\"top\"><span style=\"display: block; border: 1px solid #cccccc;\"><a href=\"\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration: none;\"><img valign=\"middle\" src=\"{{ img_url }}\" width=\"62\" height=\"62\" alt=\"\" style=\"max-width: 100%;\"></a></span></td>\n <td width=\"*\" align=\"left\" valign=\"top\" style=\"padding-left: 10px;\">\n <table width=\"100%\" border=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"*\" align=\"left\" valign=\"middle\" style=\"font-family: 'メイリオ', Meiryo, 'MS Pゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;font-size: 14px;mso-line-height-rule:exactly;line-height: 22px;\"><a href=\"######\" target=\"_blank\" style=\"text-decoration: underline;color: #000000;\">{{ title | truncate(70, True, \"...\") }}</a></td>\n </tr>\n <tr>\n <td align=\"left\" style=\"padding: 0 0 0;font-family: 'メイリオ', Meiryo, 'MS Pゴシック', 'ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', Osaka, sans-serif;color: #000000;font-size: 14px;font-weight: bold;mso-line-height-rule:exactly;line-height:24px;\">{{ price_string }}</td>\n </tr>\n </table>\n </td>\n </tr>\n </table>\n </td>\n </tr>\n </table>\n </div>\n \n </td>\n </tr>\n </table>\n \n </body>\n </html>\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T12:29:34.710",
"favorite_count": 0,
"id": "51584",
"last_activity_date": "2018-12-28T13:30:32.223",
"last_edit_date": "2018-12-28T13:25:28.373",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"html"
],
"title": "htmlにて画像がでないです。どこかおかしいのでしょうか。",
"view_count": 80
} | [
{
"body": "`{{ img_url }}`とあるので、JSXなどの言語のチュートリアルを参考にしているのかもしれません。 \nそこの部分をファイルパスに置き換えて下さい。 \n例: HTMLと同じフォルダ内のhoge.pngなら `src=\"./hoge.png\"` \nHTMLがあるフォルダ内のimgフォルダにあるfuga.pngなら`src=\"./img/fuga.png\"`",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T13:30:32.223",
"id": "51588",
"last_activity_date": "2018-12-28T13:30:32.223",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29212",
"parent_id": "51584",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51584 | null | 51588 |
{
"accepted_answer_id": "51587",
"answer_count": 1,
"body": "私は現在以下のようにコマンドで mecab-python3 をインストールしようとしているのですが、エラーが出てしまいます。 \nこれは swig をインストールすれば、解決するという意味でしょうか...? \nもし、そうでなければ mecab-python3 をインストールする上での対処法を教えて頂けると助かります。\n\nコマンド\n\n```\n\n $ pip install mecab-python3\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T12:31:19.407",
"favorite_count": 0,
"id": "51585",
"last_activity_date": "2022-06-15T16:57:21.673",
"last_edit_date": "2022-06-15T16:57:21.673",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python3",
"macos",
"mecab"
],
"title": "mecab-python3 をインストールする上での swig コマンドの必要性",
"view_count": 706
} | [
{
"body": "mecab-python3 0.996.1のリリースからswigが必要なようですので、お使いの環境に合わせて事前にインストールしてください。\n\n[mecab-python3 0.996.1](https://pypi.org/project/mecab-python3/0.996.1/)\n\n> You must have mecab and **swig** installed before running setup.py. \n> (setup.pyを実行するには、事前にmecabとswigがインストールされている必要があります。)\n\n* * *\n\n以下蛇足\n\n> swigをインストールすれば、解決するという意味でしょうか\n\n手元で試せるものは、まず自分で試してみましょう。結果を見てわからないことがあれば改めて質問すべきかなと思います。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T13:09:26.147",
"id": "51587",
"last_activity_date": "2018-12-28T13:09:26.147",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51585",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51585 | 51587 | 51587 |
{
"accepted_answer_id": "51593",
"answer_count": 1,
"body": ".NET Core\nのアプリケーションを作成し、プロジェクトをいったん閉じてから再度開くとパッケージマネージャーコンソールに以下のエラーメッセージが表示されます。\n\n> 契約名 \"NuGet.PackageManagement.VisualStudio.IScriptExecutor\" による 1\n> 回のエクスポートが予想されましたが、適用可能な制約の適用後に 0 が見つかりました。\n\n.NET Framework のアプリケーションを作成した場合は、エラーメッセージは表示されません。 \nエラーを解消するにはどうすればよいでしょうか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T12:31:20.453",
"favorite_count": 0,
"id": "51586",
"last_activity_date": "2018-12-29T00:19:03.900",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3925",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"visual-studio",
".net",
".net-core"
],
"title": "パッケージマネージャーコンソールにエラーが表示される",
"view_count": 503
} | [
{
"body": "拡張機能のキャッシュをクリアすることでエラーは表示されなくなりました。 \n具体的には、インストール済みだった「Clear MEF Component Cache」を実行しました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T00:19:03.900",
"id": "51593",
"last_activity_date": "2018-12-29T00:19:03.900",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3925",
"parent_id": "51586",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51586 | 51593 | 51593 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "こちらのlaravelのチュートリアルで練習をしているのですが質問があります。 \n<https://www.hypertextcandy.com/laravel-tutorial-authentication-part-2>\n\n開発環境 AWScloud9\n\n【実現したいこと】 \nログイン画面にパスワード変更こちらにアクセスするとパスワード再発行ページに \n遷移してメールアドレスを入力して「再発行リンクを送る」ボタンをクリックするとmailtrapのデモinboxにメールを送りたいです。 \n<https://i.gyazo.com/f9e43eeadccb39f41f8a1ebe6988e554.png>\n\n【起こったエラー】 \nパスワードの変更はこちらからのボタンを押すと \n[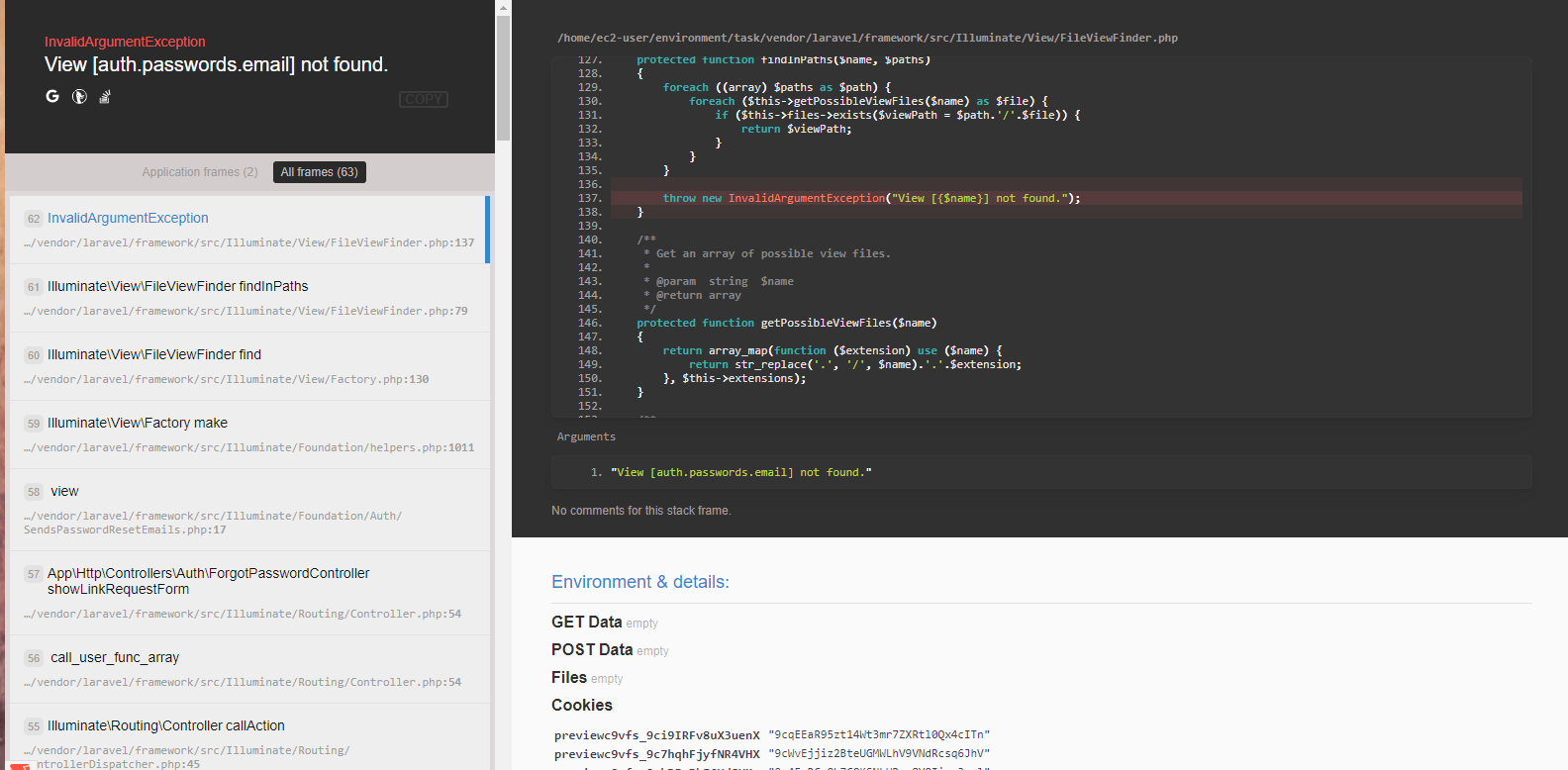](https://gyazo.com/920870c435ecd6d407c9c1885761856c)\n\nこちらのようなエラーが表示されます。 \n【試してみた事】 \ntinkerを起動してメール文がmailtrapに届いているか試したのですがこちらは問題なく送れました。 \n<https://stackoverflow.com/questions/40596795/view-auth-emails-password-not-\nfound> \nこちらで試して調べてやってみたのですが、以前エラーが表示されまます。 \nどなたかわかるかたお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T16:05:20.317",
"favorite_count": 0,
"id": "51591",
"last_activity_date": "2018-12-28T17:13:21.263",
"last_edit_date": "2018-12-28T16:19:27.340",
"last_editor_user_id": "29918",
"owner_user_id": "29918",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"laravel"
],
"title": "laravelでパスワード再発行画面が表示されないエラーに関して質問があります。",
"view_count": 428
} | [
{
"body": "実際にやったことはもう少し具体的に書いてください。(試してみたこと、以前にそこまでの経緯を) \nまたエラー内容はテキストで書き起こしてくださいね、今回だと **`View [auth.passwords.email] not found`** ですね。\n\nさて、今回の内容はおそらく **エラーをよく読んでください**\nで片付けられてしまう内容です。[参照先](https://www.hypertextcandy.com/laravel-tutorial-\nauthentication-part-2#%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88)に\n\n> **パスワード再設定メール送信ページ** \n> `resources/views/auth/passwords/email.blade.php` を以下の内容で作成してください。\n\nとあるのですが、これを飛ばしていたりあるいは作成するファイル名を誤っていたりしないでしょうか、確認してみてください。\n\n* * *\n\n実際に何が問題なのかを誤解されているようなきもするのですが、今回の問題は「メールが送れない」ではなくて「メール送信画面が表示できない」です(タイトル見る限りその認識のようなきもしますが)。まずはエラーメッセージを読んでもらえれば分かるかと。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-28T17:13:21.263",
"id": "51592",
"last_activity_date": "2018-12-28T17:13:21.263",
"last_edit_date": "2020-06-17T08:14:45.997",
"last_editor_user_id": "-1",
"owner_user_id": "2376",
"parent_id": "51591",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51591 | null | 51592 |
{
"accepted_answer_id": "51621",
"answer_count": 1,
"body": "`rails server`しても立ち上がらなくなり昨日から大苦戦しております。どなたかこちらをご教授頂けませんでしょうか?\n\n昨日ターミナルのBASHを色がついてるZSHに変えてターミナルにコマンドを打ちました。しばらくしてPHPとRuby on\nRailsをポート3000とポート8000で同時に立ち上げようとしました。\n\nその際今まで `php artisan serv` や `rails server`\nで立ち上げていた制作物のページにエラーが走り見れなくなりました。ご教授いただきガリガリコマンドを打ちましたが直せませんでした。\n\nrailsやruby homebrewなど再インストールしてrailsのバージョンも2.4.1にしたのですがなぜか2.5.1を読みに行っているみたいです。\n\nエラーはターミナルで `rails s` を打つと\n\n```\n\n MacBookPro:pictgram yokoyamanaonori$ rails s\n Traceback (most recent call last):\n 4: from bin/rails:3:in `<main>'\n 3: from bin/rails:3:in `load'\n 2: from /Users/yokoyamanaonori/pictgram/bin/spring:10:in `<top (required)>'\n 1: from /Users/yokoyamanaonori/pictgram/bin/spring:10:in `read'\n /Users/yokoyamanaonori/pictgram/bin/spring:10:in `read': No such file or directory @ rb_sysopen - /Users/yokoyamanaonori/pictgram/Gemfile.lock (Errno::ENOENT)\n \n```\n\nと表示されます。もしどなたかこちらのページを見ていただけましたら是非ご教授いただけますと \n幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T02:27:52.633",
"favorite_count": 0,
"id": "51595",
"last_activity_date": "2018-12-30T12:05:52.447",
"last_edit_date": "2018-12-29T12:13:42.263",
"last_editor_user_id": "29826",
"owner_user_id": "30298",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ruby-on-rails",
"ruby"
],
"title": "rails server がうまくいかず困っています。",
"view_count": 846
} | [
{
"body": "Gemfile.lockファイルが作成されてないため`bundle install`で作成してください。 \nまた、bundle execからrailsを実行すると2.4.1を見に行くようになると思います。\n\n```\n\n $ bundle install\n $ bundle exec rails server\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T12:05:52.447",
"id": "51621",
"last_activity_date": "2018-12-30T12:05:52.447",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31623",
"parent_id": "51595",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51595 | 51621 | 51621 |
{
"accepted_answer_id": "52998",
"answer_count": 1,
"body": "Rのバグのように感じたので、質問です。\n\nこのようなデータベースがあったとします。\n\n```\n\n sex <- c(\"F\",\"F\",\"F\",\"M\",\"M\")\n height <- c(159,163,178,172,165)\n weight <- c(61,65,82,67,74)\n sports <- c(\"1\",\"2\",\"0\",NA,\"2\")\n goal <- c(\"1\",\"1\",\"0\",\"0\",\"0\")\n data_set <- data.frame(SEX=sex, HEIGHT=height, WEIGHT=weight,SPORTS=sports,GOAL=goal)\n data_set\n \n```\n\n\\- SPORTS=2:毎週かなり運動している,1:少しは運動している,0:運動習慣がない,NA:無回答 \n\\- GOAL=1:goalした,0:goalできなかった\n\nとします。\n\nifelse()を使って、「スポーツ習慣がある人」をまとめようとする(二値変数のfactorに)と、\n\n```\n\n data_set$SPORTS <- as.factor(ifelse(data_set$SPORTS==\"2\",\"1\",data_set$SPORTS))\n data_set$SPORTS\n \n```\n\nとすると、下のように順序だけでなくバラバラな数値があてがわれてしまっていました。\n\nID before after \n1 1 2 \n2 2 1 \n3 0 1 \n4 \n5 2 1\n\nとなり、「かなり運動している人」がなぜか、「運動習慣がない」という分類になってしまいました。 \nしばらく気づかず、解析結果も大きく変わりました。 \n結構やってしまいがちな気がしました。\n\nこれはどのような理由で起こるのでしょうか? \nas.factor()のlabel,level問題と同じような理由なのでしょうか? \nこんな事が他にも起こっていたらと思うとゾッとしますが、使い慣れておられる方たちはこういったバグを避けるために何かされているのでしょうか?\n\nちなみに構造を見ると、 \n`str(data_set$SPORTS)` \nFactor w/ 3 levels \"0\",\"1\",\"2\": 2 3 1 NA 3 \n`str(ifelse(data_set$SPORTS==\"2\",\"1\",data_set$SPORTS))` \nchr [1:5] \"2\" \"1\" \"1\" NA \"1\" \n`str(as.factor(ifelse(data_set$SPORTS==\"2\",\"1\",data_set$SPORTS)))` \nFactor w/ 2 levels \"1\",\"2\": 2 1 1 NA 1 \nとなります。 \nifelseが\"1\"をlevel=1と勘違いしているような印象でしたが、よくわかりませんでした。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T06:53:16.320",
"favorite_count": 0,
"id": "51597",
"last_activity_date": "2019-02-24T15:24:51.153",
"last_edit_date": "2018-12-29T08:26:08.517",
"last_editor_user_id": "31615",
"owner_user_id": "31615",
"post_type": "question",
"score": 2,
"tags": [
"r"
],
"title": "R ifelse()のバグ?",
"view_count": 167
} | [
{
"body": "あなたは望みの振る舞いを達成するために `factor`を`character`に変換する必要があります。 下記を参照してください:\n\n```\n\n sex <- c (\"F\", \"F\", \"F\", \"M\", \"M\")\n height <- c (159, 163, 178, 172, 165)\n weight <- c (61, 65, 82, 67, 74)\n sports <- c (\"1\", \"2\", \"0\", NA, \"2\")\n goal <- c (\"1\", \"1\", \"0\", \"0\", \"0\")\n data_set <- data.frame(SEX = sex, HEIGHT = height, WEIGHT = weight, SPORTS = sports, GOAL = goal)\n \n data_set$SPORTS_before <- data_set$SPORTS\n # by OP\n data_set$SPORTS_OP <- as.factor (ifelse (data_set $ SPORTS == \"2\", \"1\", data_set $ SPORTS))\n \n # correct with as.character\n data_set$SPORTS_after <- as.factor(ifelse(as.character(data_set$SPORTS) == \"2\", \"1\", as.character(data_set $ SPORTS)))\n \n data_set[, c(\"SPORTS_before\", \"SPORTS_after\")]\n \n```\n\nアウトプット:\n\n```\n\n SPORTS_before SPORTS_after\n 1 1 1\n 2 2 1\n 3 0 0\n 4 <NA> <NA>\n 5 2 1\n \n```\n\nそうです、それが起こる理由は、`ifelse`の`factor`から`integer`への暗黙の変換です。 から明らかなように:\n\n`Factor w/ 3 levels \"0\",\"1\",\"2\": 2 3 1 NA 3`\n\nしたがって、 `\"0\"`、 `\"1\"`、 `\"2\"`は、 `factor`、 `integer`値、 `1`、 `2`、 `3`に対応します。\nそれからこれらの `integer`値は`character`に変換されるので、あなたはあなたが気付いた効果を得ることができます。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-02-24T15:24:51.153",
"id": "52998",
"last_activity_date": "2019-02-24T15:24:51.153",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "32306",
"parent_id": "51597",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51597 | 52998 | 52998 |
{
"accepted_answer_id": "51779",
"answer_count": 1,
"body": "最近機械学習の勉強を始めました。友達に勧められchainerを使っています。 \n今は特にCNNについて勉強しています。学習はGPUなどがないと厳しそうなので、CIFAR-10のデータセットとModel\nzooにある学習済みCNNのcaffemodelを用いてとりあえず推論だけさせてみたいのですが、推論の方法を調べても学習の過程でさせているものが多く困っています。推論だけする方法を教えてほしいです。\n\n使おうと思っているcaffemodelのリンクを以下に貼ります。 \n<https://github.com/Coderx7/SimpNet/blob/master/SimpNetV2/Pretrained%20Models/CIFAR10/5/Cifar10_model.caffemodel>",
"comment_count": 5,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T07:29:36.243",
"favorite_count": 0,
"id": "51598",
"last_activity_date": "2019-01-07T04:18:41.317",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31616",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python3",
"chainer"
],
"title": "chainerを用いてcaffemodelで推論がしたい",
"view_count": 106
} | [
{
"body": "結論から言えばできません. \n<https://colab.research.google.com/drive/1K5QHLIYiqAAqwKOU26yFWevNbqKo0ruL>\n\nSimpNetはCaffe自体に拡張がなされているようです.",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-07T04:18:41.317",
"id": "51779",
"last_activity_date": "2019-01-07T04:18:41.317",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29620",
"parent_id": "51598",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51598 | 51779 | 51779 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "Railsで開発しております。 \nassets/images/名前.jpgというパスで画像が位置づけされていますが、 \nHTMLのimgタグのsrcに上記パスを記載しても画像が表示されません。\n\nビューファイルはassetsフォルダと同じ階層にあるviewsフォルダ内にあるhomeフォルダ内に入っております。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T08:51:42.083",
"favorite_count": 0,
"id": "51600",
"last_activity_date": "2018-12-30T05:35:01.113",
"last_edit_date": "2018-12-29T16:00:59.883",
"last_editor_user_id": "76",
"owner_user_id": "31617",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ruby-on-rails",
"画像"
],
"title": "HTML imgタグの画像が表示されません",
"view_count": 244
} | [
{
"body": "assets 内にある画像ファイルを表示するためには、`image_tag` を利用して以下のように指定してください。適切な `img`\nタグが展開されます。\n\n```\n\n <%= image_tag(\"test.jpg\") %>\n \n```\n\nassets 以下のファイル名をそのまま指定することが出来ません。これは、assets 内にあるファイルは最終的に /aseets/ベース名-\nダイジェスト値.拡張子 (e.g.\n/assets/test-3e7e2ca170634b5950c05290d759711e800664f93cdd6914fc58590f8bd7619d.jpg)として参照されるためです。(ファイルの内容が変化するとダイジェストの値が変わり、別のファイル名になります。)\n\n何かしらの理由があって画像のパスを取得したい場合には、`asset_path` を利用してください。\n\n```\n\n asset_path(\"test.jpg\")\n <img src=\"<%= asset_path(\"test.jpg\")%>\">\n \n```\n\n固定されたファイル名を使用したい場合には、public 以下のディレクトリに置くことも出来ます。この場合、public/images/test.jpg\nであれば、/images/test.jpg として直接参照出来ます。\n\n**(参考) 何故ダイジェスト値をファイル名に含めるのか?**\n\n本番環境では高速化のため /assets\nの内容をキャッシュさせることが多いのですが、ファイルの内容が変化した場合にキャッシュが利用されないようにするためです。\n\nダイジェストを利用したくない場合には、設定で変更することも出来ます。config/initializers/assets.rb\nに以下の内容を追加してください。(おすすめしませんが。)\n\n```\n\n Rails.application.config.assets.digest = false\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T05:35:01.113",
"id": "51616",
"last_activity_date": "2018-12-30T05:35:01.113",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "76",
"parent_id": "51600",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51600 | null | 51616 |
{
"accepted_answer_id": "51606",
"answer_count": 4,
"body": "最近ラムダ計算つまりラムダ式について調べているのですが、その中の値の定義的な話で躓いてしまいました。その詳細ですが、[こちら](https://www.ed.tus.ac.jp/j-mune/sem/text/1.pdf)の\n**_2.1 構文規則_** は全体の90%程は理解できましたが、問題の **_2.1.4 プログラムの意味_** にある、\n\n```\n\n Z := 0;\n for Y do Z := Z + X\n \n```\n\nの`X`がどこから出てきたのかが分かりません。for文からして恐らく\n\n```\n\n for X do Z\n \n```\n\nではないかと思いますが、これだと言える確証がありません。stackoverflowが学問的な、計算論理学的な疑問に対応しているかは分かりませんが(念の為書いておきますがレベルが低いなどと言っている訳ではありません)、良質な日本語対応の質問サイトをここ以外知らないもので、こちらに質問させていただきました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T10:30:07.297",
"favorite_count": 0,
"id": "51602",
"last_activity_date": "2018-12-30T10:36:37.783",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "30493",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"プログラミング言語"
],
"title": "プログラム意味論的な話で「for Y do Z := Z + X」のXがどこから出てきたのか解らない",
"view_count": 225
} | [
{
"body": "直後を読む限り、`X`も`Y`も所与の変数(気分的には引数)では?\n\n> 掛け算を行うプログラム: 変数XとYに,負でない整数を代入して実行すると,変数ZにX*Yの値が代入されて停止する.",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T11:23:37.520",
"id": "51604",
"last_activity_date": "2018-12-29T11:23:37.520",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "10685",
"parent_id": "51602",
"post_type": "answer",
"score": 2
},
{
"body": "> 掛け算を行うプログラム : 変数 X と Y に,負でない整数を代入して実行すると,変数 Z に X ∗ Y の値が代入されて停 \n> 止する.\n\nという注釈を読む限り、`X`を`Y`回足したもの`Z`の結果が、式\n\n```\n\n sum = X * Y\n \n```\n\nでいう、`sum`と`Z`が等しい事の説明であると読めるので、リンク先の式で合っていると思います。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T11:38:10.917",
"id": "51605",
"last_activity_date": "2018-12-29T11:38:10.917",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14745",
"parent_id": "51602",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "質問の出典を最後まで読むと、これは掛け算をするプログラムを表しています。\n\n> 2.1.4 プログラムの意味\n```\n\n> Z := 0;\n> for Y do Z := Z + X\n> \n```\n\n>\n> 掛け算を行うプログラム : 変数 X と Y に,負でない整数を代入して実行すると,変数 Z に X ∗ Y の値が代入されて停止する. \n> <https://www.ed.tus.ac.jp/j-mune/sem/text/1.pdf> より抜粋\n\nここで、`X` は被乗数(かけられる数)、`Y`は乗数(かける数、掛け算の回数)、 `Z` は\n[@Чайка](https://ja.stackoverflow.com/users/14745)\n氏の指摘するとおり`sum`、つまり掛け算の繰り返しの途中で結果を保存する変数として登場しているようです。\n\nRubyがお得意のようですので、この内容をRuby風に書くと以下のようになるでしょうか。\n\n```\n\n def multiply(x, y)\n z = 0\n (1..y).each{\n z = z + x\n }\n return z\n end\n \n puts multiply(5, 8)\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T13:08:02.390",
"id": "51606",
"last_activity_date": "2018-12-29T13:08:02.390",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29826",
"parent_id": "51602",
"post_type": "answer",
"score": 2
},
{
"body": "# 短いお返事\n\nその時点では形式的に構文規則を定めた所なので、実際にはXだとかZだとかに **意味はありません。** \nしかし私達は通常のプログラムの **意味論を踏まえてしまっているから** 不思議に思えてしまうのです。\n\nただし、その後に定められている表示的意味論を解釈する限りは、 **所与の変数値** と同等のものと考えられます。\n\n# しっかりしたお返事\n\nそのテキストの文脈は、 **構文規則** を定めた直後ですね。 \n実はその時点では、構文として一応そういった文が作れるということしか定めておらず、 \n現実にそれがどのような意味を持つものかを何も定めていない段階です。 \nつまり変数の記号 `X` であるとはどういうことかが、まだ何も定まっていません。 \nそのためその場所に (構文規則に従っている限り) **突然登場することも、まったく可能** なのです。\n\nサンプルのあと、実際にお話は意味論(意味関数による表示的意味論ですね)に進みます。 \nここで意味関数を与えたことで、始めてこの文がどんな意味を持つのか明らかになったのです。\n\nそこで実際に意味論に従ってこの値を解釈して導出してみましょう。\n\nまず 環境 `ϕ` を任意に定めます。 \nたとえば `ϕ = { (X, 30), (Y, 2), (Z, 1000), (その他の変数は適当に) }` なんてどうでしょうか。 \n(上記は集合を使った関数の定義です。つまりXを引数に取ると30,Yなら2、Zなら1000という関数を環境と思っています)\n\nそして(ちょっとテキストの構成上、定まりの悪い `;` の意味論などに気をつけながら)展開すると\n\n```\n\n M_cmd[[Z := 0;for Y do Z := Z + X]]ϕ\n = M_cmd[[Z := 0;for Y do Z := Z + X]]ϕ\n = M_cmd[[for Y do Z := Z + X]](M_cmd[[Z := 0]]ϕ)\n = M_cmd[[for Y do Z := Z + X]](ϕ(Z := 0))\n = M_cmd[[Z := Z + X]](M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 0))) (ϕ(Y) = 2であるため2回展開した)\n = M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 0)(Z := M_exp[[Z + X]]ϕ(Z := 0)))\n = M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 0)(Z := M_exp[[Z]]ϕ(Z := 0) + M_exp[[X]]ϕ(Z := 0) ))\n = M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 0)(Z := ϕ(Z := 0)(Z) + ϕ(Z := 0)(X) ))\n = M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 0)(Z := 0 + 30))\n = M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 0)(Z := 30))\n = M_cmd[[Z := Z + X]](ϕ(Z := 30))\n = ϕ(Z := 60) (ここはもう操作を省略しました。紙面などで試してみてください)\n = { (X, 30), (Y, 2), (Z, 60), (その他の変数はϕに等しい) }\n \n```\n\n`ϕ(X)` の値は、この文における意味論の課程で、特に書き換えられていない(最初から最後まで30でした)ことから、 \nつまるところ初期の `ϕ(X)` に与えられた値がそのまま継承されているはずです。\n\n結局、直感的には環境 `ϕ` に依存した値 `ϕ(X)` が、 \nこの `X` の値として該当コードの\"実行\"(そんな概念は無いのであくまで直感的に!)で採用されることになるでしょう。 \nもうちょっと言葉をスムーズにするならこれは「所与の変数 `X` の値をそのまま採用しましょう。」 \nということだと直感的には解釈できます。\n\nしかし基本的には意味論を厳密に解釈するなら、値が「どこからくる」という考え方自体を、実はしていないのです。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T17:45:35.570",
"id": "51610",
"last_activity_date": "2018-12-30T10:36:37.783",
"last_edit_date": "2018-12-30T10:36:37.783",
"last_editor_user_id": "30827",
"owner_user_id": "30827",
"parent_id": "51602",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51602 | 51606 | 51610 |
{
"accepted_answer_id": "51614",
"answer_count": 1,
"body": "以下の操作をディレクトリ内の特定のファイルだけでなく、全ファイルに同じように適用したい時にどのようなコマンドを書けば良いのかわかりません。 \n一応、<https://qiita.com/elzup/items/e839a8c4e815808fb4bc>\nなどは読んでみたのですが、よくわかりません...。 \n教えて頂けると助かります。 \n元のファイル(01_hangan_chimatao_iku.txt)はTextディレクトリに入っていて、操作後のファイル(hangan_wakati.txt)はTextと同じ階層にあるWakatiディレクトリ内に作成するようにしたいです。\n\n操作(特定のファイル01_hangan_chimatao_iku.txtに対して)\n\n```\n\n $mecab -Owakati 01_hangan_chimatao_iku.txt -o hangan_wakati.txt\n $nkf -w --overwrite hangan_wakati.txt\n \n```",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T16:04:56.567",
"favorite_count": 0,
"id": "51607",
"last_activity_date": "2018-12-30T04:05:45.863",
"last_edit_date": "2018-12-29T20:41:56.867",
"last_editor_user_id": "31249",
"owner_user_id": "31249",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"linux"
],
"title": "linuxで特定のディレクトリ内の全てのファイルに対して同じ操作を適用する方法",
"view_count": 2741
} | [
{
"body": "僕の場合は行いたい「こと」と、行いたい「対象」を分けて考える手法を良く使います。\n\n行いたいことは、引数として渡されたファイル名に対してどういう事を行うかを、シェルスクリプトに記述して、該当ディレクトリまたは`/usr/local/bin`に実行パーミッションを付けて配置します。\n\nひな形はこんな感じになります。\n\n```\n\n #!/bin/sh\n \n while [ -n \"$1\" ]\n do\n fullname=$1\n extension=${fullname##*.}\n filename=${fullname%.*}\n suffix=${filename##*_}\n if [ \"$suffix\" != \"Z\" ] ; then\n mv ${filename}\".\"${extension} ${filename}\"_Z.\"${extension}\n fi\n shift\n done\n \n```\n\n今回の場合は`mecab`出力を同じ階層にある`Wakati`ディレクトリに`wakati.txt`という名前で出力することと読めますので、\n\n```\n\n #!/bin/sh\n \n while [ -n \"$1\" ]\n do\n # 引数をファイル名と拡張子に分割、出力ファイル名作成\n originalpath=`dirname $1`\n fullname=`basename $1`\n extension=${fullname##*.}\n filename=${fullname%.*}\n outputname=\"$originalpath\"/Wakati/\"$filename\"_wakati.txt\n # 実行したいコマンド\n mecab -Owakati \"$fullname\" -o \"$outputname\"\n nkf -w --overwrite \"$outputname\"\n # 今の引数を捨て、次の引数を処理するためのコマンド\n shift\n done\n \n```\n\nこれを仮に`domecab`という名前で保存したとして、\n\n```\n\n chmod +x domecab\n sudo mv domecab /usr/local/bin\n rehash\n \n```\n\nこれで、`domecab`が`unix`コマンドであるかのように使えるようになります。\n\n次に、行いたい対象にこのコマンドを全て適用すればいいわけですが、そのためには、`find`コマンドを使います。 \n具体的には、処理をしたい対象テキストファイルがある一つ上のディレクトリーが、`aozora`というディレクトリーだとしましす \nこの`aozora`が`ls`で見た場合に`aozora`と見える場合は\n\n```\n\n find aozora -name \"*.txt\" -exec domecab {} \\;\n \n```\n\n同様に`.`に見える場合には\n\n```\n\n find . -name \"*.txt\" - exec domecab {} \\;\n \n```\n\nと実行すれば`find`の次の引数ディレクトリー以下の`txt`拡張子を持つファイルに対して`domecab`コマンドを実行してくれます。\n\n行いたいことが簡単であれば、`find`コマンドの`-exec`オプションにやりたいことをそのまま書いてしまい、`一行野郎(one\nliner)`でやってしまう方が簡単ですが、今回は名前の変更があるため、あえて準備に手間が掛かる代わりに応用が利く方法を紹介させて頂きました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T04:05:45.863",
"id": "51614",
"last_activity_date": "2018-12-30T04:05:45.863",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14745",
"parent_id": "51607",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51607 | 51614 | 51614 |
{
"accepted_answer_id": "51611",
"answer_count": 1,
"body": "Pythonで指定した一列だけrenameする方法を探しています。\n\n```\n\n df.columns[0]='新列名'\n \n```\n\nとしてもrenameできません。 \nぐぐると全列名をリストで入れる方法と辞書で指定する方法は出てくるのですが、今回は使えません。 \nというのも、列名ではなく数値で列を指定しているのは関数化してループさせたときに1回目と2回目では列名が異なってくる、列数が異なってくるからです。 \n(ちなみに0列目を同じ名前でrenameするというのは共通しています。)\n\nどうぞよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T17:36:01.853",
"favorite_count": 0,
"id": "51609",
"last_activity_date": "2018-12-30T09:08:26.477",
"last_edit_date": "2018-12-30T09:08:26.477",
"last_editor_user_id": "3054",
"owner_user_id": "12457",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"pandas"
],
"title": "Pythonのpandasで一列だけrenameする方法",
"view_count": 1387
} | [
{
"body": "`pandas`の話ですよね?普通にリストで入れてあげればいいと思うのですがダメなのでしょうか\n\n```\n\n NAME = 'new_column_name'\n df.columns = [NAME] + list(df.columns[1:])\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-29T17:59:49.180",
"id": "51611",
"last_activity_date": "2018-12-29T17:59:49.180",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "10685",
"parent_id": "51609",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51609 | 51611 | 51611 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "Spresense SDK チュートリアルの examples/hello をチュートリアルの手順にしたがって試してみました。「1.4. Spresense\nメインボードへのイメージのロード」の図3にあるように、loadに成功し、rebootまでの表示が出ました(サイズは154176 bytes\nと、図3の表示とは若干異なります)。updater# sync という表示も出ています。\n\nところが、minicom で繋いで、hello と入力しても、command not found となり、help で見ても、Builtin Apps:\nには何のエントリーもありません。Nuttxのversionは7.22です。\n\nまた、チュートリアルでは、examplesのディレクトリはsdkの下にあるように書かれていましたが、 \nダウンロードしたものでは、sdkと同じ階層にありました(それで mv しました)。\n\n```\n\n $ git clone --recursive https://github.com/sonydevworld/spresense.git\n \n```\n\nのダウンロードも、なぜか2回行わないと、spresenseのディレクトリが現れませんでした。\n\nどう対処すれば良いでしょうか? ご教授お願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T05:37:25.713",
"favorite_count": 0,
"id": "51617",
"last_activity_date": "2019-01-04T07:38:11.843",
"last_edit_date": "2018-12-30T05:49:19.440",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31152",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ubuntu",
"spresense"
],
"title": "Sony Spresense built-in app not found",
"view_count": 222
} | [
{
"body": "外しているかもしれませんが、「Spresense SDK チュートリアル」の ”1.3. Spresense メインボードへのブートローダーのインストール”\nを行いましたか?\n\nNuttX が正しくインストールされているならば、\n\n```\n\n NuttShell (NSH)\n nsh> \n \n```\n\nのコマンドプロンプトが出るはずです。おぼろげな記憶で不確かですが、ブートローダをインストールしていないと、\"updater#\"\nのコマンドプロンプトが出ていたように思います。",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-04T07:38:11.843",
"id": "51694",
"last_activity_date": "2019-01-04T07:38:11.843",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "27334",
"parent_id": "51617",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51617 | null | 51694 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 2,
"body": "batで、あるファイル内の文字を置換するものを書いたのですが改行やスペースが消えてしまいます。 \n解決方法をご教授ください。\n\n```\n\n @echo off\n rem 元ファイルをtempにコピー\n copy %~n1.tex \"%~n1\"_temp.tex\n \n rem 元ファイルを削除\n del \"%~n1.tex\"\n \n setlocal enabledelayedexpansion\n for /f \"delims=\" %%a in (%~n1_temp.tex) do (\n set line=%%a\n set line=!line:。=. !\n set line=!line:、=, !\n echo !line! >> %~n1.tex\n )\n endlocal\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T10:38:38.110",
"favorite_count": 0,
"id": "51620",
"last_activity_date": "2019-01-01T05:44:58.330",
"last_edit_date": "2018-12-30T10:42:05.197",
"last_editor_user_id": "14745",
"owner_user_id": "31202",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"windows",
"batch-file"
],
"title": "batでテキストファイルの改行やスペースが消えてしまう",
"view_count": 14492
} | [
{
"body": "「改行やスペースが消えてしまいます」の詳細が不明なので、全てのデータに当てはまるか不明ですが、echo の書き方が原因と思われます。\n\n[windowsの.batバッチファイルで文字列を置換する](https://qiita.com/wagase/items/2180d8911dcc2a748fd3)\n\n> echoの都合で \n> ・空行はなかったことにされる \n> ・半角スペースしか無い行は echo off が出力される\n\nさらに環境変数に代入した内容を出力していることで、以下が適用されるでしょう。\n\n[コマンド別/echo](https://otnx.jp/CMD/%A5%B3%A5%DE%A5%F3%A5%C9%CA%CC/echo/)\n\n> echoの直後に何かの記号を書くと良い。大抵の記号は大丈夫だが、よく見るのは . / : 等である。 \n> ただし、echo. 等とすると遅延展開を使う場合、 ! ! の間に , ; = の文字が入ると駄目である。 \n> ここで、echoの直後に書く記号を , ; = のいずれかを使うと大丈夫。\n\n逆に出力結果に空白が付加されることもあるようです。\n\n[バッチファイル | テキストファイルを 1 行ずつ読み込む\n(完全版?)](https://blogs.yahoo.co.jp/kerupani/15344574.html)\n\n> 6.おまけ: echo は かっこ で囲うといいかもしれない\n\n上記を元に echo の行を以下のようにして試してみてください。 \nまあかっこの有無や使う記号を変えるなど、色々試してみてください。\n\n```\n\n (echo=!line!) >> %~n1.tex\n \n```\n\nさらにここまで書いてきてナンですが、FOR /F は eol= のデフォルト値で行頭がセミコロンだと \nその行はコメント行として扱われスキップされるという機能があり、その回避が難しいようです。\n\n[FOR /F その1 = FOR文でファイルを1行ずつ取り出して実行する方法 -\nWindowsのコマンドプロンプト(bat,cmd)](http://tounderlinedk.blogspot.com/2011/05/for-f-1-for1-windowsbatcmd.html)\n\n他にsetlocal enabledelayedexpansion を指定すると対象ファイル名に制限が付く等あるようです。 \n[バッチファイルでの試行錯誤を回避するためのメモ](https://qiita.com/yz2cm/items/8058d503a1b84688af09)\n\n@sayuriさんコメントのように、PowerShellにしてみるとか、編集や文字列処理に特化した sed や awk(gawk)\nといったコマンドを使用してみるのが良いのではないでしょうか。 \n[GNU utilities for Win32](http://unxutils.sourceforge.net/)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T02:03:32.270",
"id": "51640",
"last_activity_date": "2019-01-01T02:03:32.270",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51620",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "追加情報です。sedをbatで使う場合、おそらく一番手軽なのはgit bash を導入してしまうことです。 \nセットアップ時にMinGWも一緒にいれてくれるので、普通にコマンドプロンプトから利用できるようになります。 \n<https://gitforwindows.org/>",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T05:27:32.960",
"id": "51643",
"last_activity_date": "2019-01-01T05:44:58.330",
"last_edit_date": "2019-01-01T05:44:58.330",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "10174",
"parent_id": "51620",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51620 | null | 51640 |
{
"accepted_answer_id": "51723",
"answer_count": 1,
"body": "お世話になります.\n\n以下のような図を,matplotlibで作成しました. \n[](https://i.stack.imgur.com/ytnJc.png)\n\nグラフの右下・左下で,x軸・y軸の軸目盛りが近づいてしまい,見づらくなってしまっています.\n\nそこで,x軸の軸目盛りをx軸から離したいのですが,方法が分かりません. \nご教授お願いします.",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T14:55:11.640",
"favorite_count": 0,
"id": "51625",
"last_activity_date": "2019-01-06T03:53:32.763",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "27841",
"post_type": "question",
"score": 4,
"tags": [
"python",
"matplotlib"
],
"title": "Matplotlib 軸と目盛りの距離の変更",
"view_count": 1654
} | [
{
"body": "[`Axes.tick_params()`](https://matplotlib.org/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.tick_params.html#matplotlib.axes.Axes.tick_params)\nで `pad` を設定すると良いです。\n\n```\n\n ax.tick_params(pad=〈tick と tick label の間の距離を float で指定する〉)\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-05T05:56:50.100",
"id": "51723",
"last_activity_date": "2019-01-06T03:53:32.763",
"last_edit_date": "2019-01-06T03:53:32.763",
"last_editor_user_id": "19110",
"owner_user_id": "19110",
"parent_id": "51625",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51625 | 51723 | 51723 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "Railsチュートリアルでは、herokuのpostgresqlを使うための設定としては、Gemfileに下記のように追記するだけでした。\n\n```\n\n group :production do\n gem 'pg', '0.20.0'\n end\n \n```\n\nconfig/database.ymlは以下のようにデフォルトのままでいじることはありませんでした。\n\n```\n\n default: &default\n adapter: sqlite3\n pool: <%= ENV.fetch(\"RAILS_MAX_THREADS\") { 5 } %>\n timeout: 5000\n \n development:\n <<: *default\n database: db/development.sqlite3\n \n test:\n <<: *default\n database: db/test.sqlite3\n \n production:\n <<: *default\n database: db/production.sqlite3\n \n```\n\ndatabase.ymlのproductionの設定のところはsqlite3を使う設定のままになっているのにheroku上ではpostgresqlにちゃんと接続できるのはなぜでしょうか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-30T22:58:12.390",
"favorite_count": 0,
"id": "51626",
"last_activity_date": "2019-01-03T01:36:20.387",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": null,
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"ruby-on-rails",
"ruby"
],
"title": "herokuのpostgresqlを使う設定について",
"view_count": 64
} | [
{
"body": "仮にこの設定で問題なく動いていたとして、おそらく production 環境(heroku)では sqlite3 で動作していると思います。\n\n個人的には、開発で使うデータベースと、本番で使うデータベースは、同じアダプタを用いるのが良いと思います。",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T01:36:20.387",
"id": "51669",
"last_activity_date": "2019-01-03T01:36:20.387",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "754",
"parent_id": "51626",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51626 | null | 51669 |
{
"accepted_answer_id": "51632",
"answer_count": 1,
"body": "ファイルから読み取った文字列の内容によって、開くファイルを分岐で区別して、そこに書いてある数字をfscanfで読み取り、クローズするというのをループするプログラム(その間ストリームポインタは同じものを使っています)なのですが、コンパイルも通り実行もエラーはなかったのですが、全て読み取ってループを抜けた後のprintfの出力がされませんでした。 \n調べると、22回のループのうち21回目までは読み取れていましたが、最後の22回目のfscanfの前まではstderrが出力され、その直後はstderrが出力されず、当然その後のprintf等も通らずに実行が終了していました。これはどうしてなのでしょうか。fscanf文と読み取るファイルは以下の通りです。iはループカウンタです。\n\nfscanf(fp1, ''%d %d'', &unit[i].p_num, &unit[i].t_num);\n\n読み取りファイル \n///////////////// \n7\n\n3\n\n////////////////\n\nこのファイルはループの20回目にも開かれ、それはきちんと読み取れていました。もちろんクローズもされています。\n\n【 補足】 \n全て書くと多いので、必要と思われるソースだけ追記します。\n\n```\n\n for(i=0; i<22; i++){\n if((fp1=fopen(''sw.txt'',''r''))==NULL){ //i=19,21の時通るようにしてある\n printf(''ファイルが見つかりません'');\n exit(EXIT_FAILURE);\n }\n //ここでelse{}を作ると通る\n //iがいくつでもここでのstderrは実行される\n fscanf(fp1, ''%d %d'', &unit[i].p_num, &unit[i].t_num);\n //i=21の時ここでのstderrが実行されない\n fclose(fp1);\n }\n printf(''〜'');//実行されない\n \n```\n\nまた、読み込みファイルのフォーマットを\n\n```\n\n 7 3\n \n```\n\nのように修正しても結果は同じでした。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T04:18:56.860",
"favorite_count": 0,
"id": "51627",
"last_activity_date": "2018-12-31T13:35:05.337",
"last_edit_date": "2018-12-31T13:35:05.337",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": "31624",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c"
],
"title": "fscanfが実行されません。",
"view_count": 280
} | [
{
"body": "示されている範囲で、原因わかりません。\n\n参考になるかわかりませんが、コメントです。\n\n(1) \nこれは、改行があるからダメでは? \n///////////////// \n7\n\n3 \n////////////////\n\n(2)\n\n”このファイルはループの20回目にも開かれ” \n22回目の誤記ですか?\n\n(3) \nunit[i]の配列サイズは、十分ですか?\n\n(4)トータルとして、 \n意識している部分と違う部分が誤っている気がします。\n\n以上",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T10:19:47.943",
"id": "51632",
"last_activity_date": "2018-12-31T10:19:47.943",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31548",
"parent_id": "51627",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51627 | 51632 | 51632 |
{
"accepted_answer_id": "51637",
"answer_count": 1,
"body": "ファル名 keisan.csv \n2018年月21日,abc,\\387 \n2018年6月23日,abc,\"\\1,418\" \n2018年6月23日,abc,\\276 \n2018年6月30日,abc,\\925 \n2018年6月30日,abc,\\619\n\nawkで3番目のファイールドだけを下記などで、 \nsum += $3 \n計算したいのでが、取得したcsvファイルが3桁カンマや円マークが \n入っているため計算できません。\n\n正規表現で桁数カンマと、ダブルクオーテーション、円マークを \n取り除いたのですが、awkの正規表現でも同じようなことは可能でしょうか\n\n\"?\\\\(\\d+),?(\\d+)\"? \n$1$2\n\n最終的に、3番目のフィールドだけを計算したいのですが、 \nawkではmatchを使うという記事を参考に書きを試して \nみましたが、うまくいきません。\n\nawk -F, 'match($0, /\"?\\\\(\\d+),?(\\d+)\"?/, a) {print a[1]}' keisan.csv",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T06:41:26.697",
"favorite_count": 0,
"id": "51628",
"last_activity_date": "2018-12-31T13:49:34.093",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "25524",
"post_type": "question",
"score": 2,
"tags": [
"正規表現",
"awk"
],
"title": "awkで正規表現のキャプチャの利用方法",
"view_count": 544
} | [
{
"body": "質問の例にあるのはGNU awk固有の書き方ですね。コマンド名をgawkとすると、こんな感じかと。\n\n```\n\n $ gawk -F, 'match($3, /\"?([0-9]+)\"?/, a) { print a[1] }' keisan.csv\n \n```\n\n一般的なawkだとこんな感じでしょうか。\n\n```\n\n $ awk -F, 'match($3, /[0-9]+/) { print substr($3, RSTART, RLENGTH) }' < keisan.csv\n \n```",
"comment_count": 3,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T13:49:34.093",
"id": "51637",
"last_activity_date": "2018-12-31T13:49:34.093",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "4010",
"parent_id": "51628",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51628 | 51637 | 51637 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "chromeの拡張機能であるStylusで\n\n```\n\n *{color:#000000 !important;}\n {color:#1A0DAB ;}\n \n```\n\nでリンクの色が#1A0DABに変化しない。 \n(`*{color:#000000 !important;}`、`a:link {color:#1A0DAB\n!important;}`でgoogle検索結果のリンクの色が`#1A0DAB`に変化しない。)",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T07:46:33.027",
"favorite_count": 0,
"id": "51630",
"last_activity_date": "2018-12-31T13:34:11.163",
"last_edit_date": "2018-12-31T13:34:11.163",
"last_editor_user_id": "2238",
"owner_user_id": "31626",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"css"
],
"title": "リンクの色が変化しない stylus",
"view_count": 357
} | [
{
"body": "すべてのリンクに適用したいなら、`a:any-link{color:#1A0DAB;}`のように、`:any-link`を試してみてください。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T11:20:57.160",
"id": "51633",
"last_activity_date": "2018-12-31T11:20:57.160",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29212",
"parent_id": "51630",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51630 | null | 51633 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "stylusで \n_{ \nbackground-color:#006400 !important; \n} \nと記述した場合にサイト(<https://support.google.com/>_)が正しく表示されないのですがcssを特定のurlに適用しないなどの対処方法を教えてください。",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T11:56:15.117",
"favorite_count": 0,
"id": "51634",
"last_activity_date": "2018-12-31T12:25:33.803",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31626",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"css"
],
"title": "background-color:でサイト(https://support.google.com/*)が正しく表示されない場合の対処方法",
"view_count": 54
} | [
{
"body": "Stylusでは適用先URLを正規表現で指定できます。「適用先:正規表現に一致するURL」にしてください。 \nたとえば、先読みを使って`(?!https\\:\\/\\/support\\.google\\.com.*).*`とかはどうでしょうか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T12:25:33.803",
"id": "51635",
"last_activity_date": "2018-12-31T12:25:33.803",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "29212",
"parent_id": "51634",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51634 | null | 51635 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "このプログラムを実行すると、decide_direction()内のxとyが意図したとおりに変化しません。教えてもらえませんか? \nこのコードを実行したときに出力されるyの値を2, 4, 6, 8 ... としたいのですが、2, 2, 2, 2, ... と値が変わらないです。\n\n```\n\n #include <iostream>\n #include <ctime>\n /*\n *棒倒し法\n */\n \n class maze {\n int wall_info[77][77] = {{0}};\n int x, y;\n public:\n maze();\n void make_wall();\n int decide_direction();\n int wall_check();\n void show();\n };\n \n maze::maze()\n {\n //make wall\n for (y = 0; y <= 76; y++) {\n for (x = 0; x <= 76; x++) {\n if (y == 0 || x == 0 || y == 76 || x == 76) {\n wall_info[y][x] = 1;\n }if (y % 2 == 0 && x % 2 == 0) {\n wall_info[y][x] = 1;\n }\n }\n }\n y = 2;\n x = 2;\n }\n \n void maze::make_wall()\n {\n while (y < 76) {\n while (x < 76) {\n if (decide_direction() == 4) {\n wall_info[y - 1][x] = 1;\n }\n else if (decide_direction() == 3) {\n wall_info[y][x - 1] = 1;\n }\n else if (decide_direction() == 2) {\n wall_info[y + 1][x] = 1;\n }\n else {\n wall_info[y][x + 1] = 1;\n }\n x += 2;\n }\n y += 2;\n // std::cout << y << std::endl;\n }\n }\n \n int maze::decide_direction()\n {\n int direction = 0;\n int check;\n \n std::cout << y << std::endl;\n \n if (y <= 2) {\n check = wall_check();\n if (wall_check() == -1) {\n direction = rand() % 3 + 1;\n }\n else {\n direction = rand() % 4 + 1;\n }\n }\n else {\n if (wall_check() == -1) {\n direction = rand() % 2 + 1;\n }\n else {\n direction = rand() % 3 + 1;\n }\n }\n \n return direction;\n }\n \n int maze::wall_check()\n {\n if (wall_info[y][x - 1] == 1) {\n return -1;\n }\n else {\n return 0;\n }\n }\n \n void maze::show()\n {\n for (int i = 0; i <= 76; i++) {\n for (int j = 0; j <= 76; j++) {\n if (wall_info[i][j] == 1) {\n std::cout << \"■ \";\n }\n else {\n std::cout << \"□ \";\n }\n }\n std::cout << std::endl;\n }\n }\n \n int main()\n {\n srand((unsigned)time(NULL));\n maze maze;\n \n maze.make_wall();\n maze.show();\n \n return 0;\n }\n \n```",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T13:44:53.557",
"favorite_count": 0,
"id": "51636",
"last_activity_date": "2019-01-01T06:52:52.790",
"last_edit_date": "2019-01-01T05:54:07.817",
"last_editor_user_id": "31631",
"owner_user_id": "31631",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c++"
],
"title": "privateの変数、xとyが意図したとおりに変化できない",
"view_count": 176
} | [
{
"body": "```\n\n void maze::make_wall()\n {\n while (y < 76) {\n while (x < 76) {\n // 省略\n x += 2;\n }\n y += 2;\n // std::cout << y << std::endl;\n }\n }\n \n```\n\nこのメソッドでは、二重ループで、まずxから計算しています。内側のループでxを計算している間、yの値は変わらないので、期待される出力は`2,2,2...4,4,4,...6,6,6...`です。しかし、実際には`2,2,2,...`になると思います。これは、最初の`y==2`の時に内側のルーフが終わった後、xを再初期化していないため、`y==4`以降、`x==76`のままで内側のループが実行されないためです。内側のループの直前でxを再初期化すればうまくいくはずです。\n\n```\n\n void maze::make_wall()\n {\n while (y < 76) {\n x = 2; // ここを追加\n while (x < 76) {\n \n```\n\n* * *\n\nちなみに、ループの中で方向を決める部分ですが、\n\n```\n\n if (decide_direction() == 4) {\n wall_info[y - 1][x] = 1;\n }\n else if (decide_direction() == 3) {\n wall_info[y][x - 1] = 1;\n }\n else if (decide_direction() == 2) {\n wall_info[y + 1][x] = 1;\n }\n else {\n wall_info[y][x + 1] = 1;\n }\n \n```\n\n一番最後の`else`の部分が実行される確率が、かなり高いと思います。`decide_direction()`を何度も呼び出していますが、返ってくる値はそのたびに違うからです。例えば、最初の`if`で`decide_direction()`が3を返すと、次の`else\nif`が実行され、そこで2が返ってくると、更にその次の`else\nif`が実行され、そこで4が返ってくると、1は一度も返ってきていないのに、1が返ってきた場合に当たる、最後の`else`が実行されてしまいます。ここは`switch`を使うのが良いでしょう。\n\n```\n\n switch (decide_direction()) {\n case 4:\n wall_info[y - 1][x] = 1;\n break;\n case 3:\n wall_info[y][x - 1] = 1;\n break;\n case 2:\n wall_info[y + 1][x] = 1;\n break;\n default:\n wall_info[y][x + 1] = 1;\n break;\n }\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T06:52:52.790",
"id": "51648",
"last_activity_date": "2019-01-01T06:52:52.790",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3605",
"parent_id": "51636",
"post_type": "answer",
"score": 4
}
] | 51636 | null | 51648 |
{
"accepted_answer_id": "51642",
"answer_count": 1,
"body": "jsonのデータの取り出しについて教えてください。\n\njsonファイルで\n\n```\n\n {\n \"totalItems\": \"1212\",\n \"items\": [\n {\n \"id\": \"AAAAA\",\n \"volumeInfo\": {\n \"title\": \"あああああ\",\n \"authors\": \"かか かかか\",\n \"publisher\": \"さささ\",\n \"publisherDATE\": \"2000\",\n \"description\": \"xxxx\",\n \"pageCount\": \"201\",\n \"previewLink\": \"http//\"\n }\n },\n {\n \"id\": \"BBBBBBB\",\n \"volumeInfo\": {\n \"title\": \"いいいいいい\",\n \"authors\": \"ききき きき\",\n \"publisher\": \"ししし\",\n \"publisherDATE\": \"2001\",\n \"pageCount\": \"250\",\n \"previewLink\": \"http//\"\n }\n },\n {\n \"id\": \"XXXXXXXX\",\n \"volumeInfo\": {\n \"title\": \"うううううううう\",\n \"authors\": \"くくく くくく\",\n \"publisher\": \"すすす\",\n \"publisherDATE\": \"2002\",\n \"description\": \"yyyyyyy\",\n \"pageCount\": \"280\",\n \"previewLink\": \"http//\"\n }\n },\n {\n \"id\": \"YYYYYYY\",\n \"volumeInfo\": {\n \"title\": \"ええええええええ\",\n \"authors\": \"けけけ けけ\",\n \"publisher\": \"せせせ\",\n \"publisherDATE\": \"2003\",\n \"description\": \"zzzzz\",\n \"previewLink\": \"http//\"\n }\n },\n {\n \"id\": \"ZZZZZZZZZ\",\n \"volumeInfo\": {\n \"title\": \"おおおおおお\",\n \"authors\": \"こここ ここここ\",\n \"publisher\": \"そそそ\",\n \"publisherDATE\": \"2004\",\n \"previewLink\": \"http//\"\n }\n }\n ]\n }\n \n```\n\nこのjsonファイルの中で \ndescription \npageCount \nキーと値を削除してデータを取り出したいです。 \nそれと、descriptionとpageCountキーの値がない場合のエラーを出さないようにしたいです。\n\n自分が試したのは\n\n```\n\n json_file = open('JSONファイルの名前.json', 'r')\n json_object = json.load(json_file)\n \n print(json_object[\"items\"][0][\"volumeInfo\"])\n \n```\n\nvolumeInfoの階層までは取り出せたのですが、 \n次のtittle から previewLink までのデータを取得したいのですが、 \nここからがどうしてもわかりません。 \nその階層までいけば、for文で回せばいいのかなって \n思ってるのですが、、\n\n書き方が読みづらいと思いますが、\n\nどなたか、ご教授お願い致します。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T20:57:50.660",
"favorite_count": 0,
"id": "51638",
"last_activity_date": "2019-01-01T08:11:11.977",
"last_edit_date": "2019-01-01T06:37:34.817",
"last_editor_user_id": "29826",
"owner_user_id": "31632",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"json"
],
"title": "python3 jsonファイルデータの取得方法を教えて下さい。",
"view_count": 268
} | [
{
"body": "とりあえずこんな感じでどうでしょう。 \nPythonコードと実行結果を貼り付けておきます。 \n実行環境はpython3.7.0です。\n\n```\n\n # coding: UTF-8\n \n import json\n \n json_file = open('a.json', 'r')\n json_object = json.load(json_file)\n \n for item in json_object['items']:\n item_info = item['volumeInfo']\n \n print('======== 書籍ID: {} の情報 ========'.format(item['id']))\n print('タイトル: {}'.format(item_info['title']))\n print('著者: {}'.format(item_info['authors']))\n print('出版: {}'.format(item_info['publisher']))\n print('出版日: {}'.format(item_info['publisherDATE']))\n try:\n print('説明: {}'.format(item_info['description']))\n print('ページ数: {}'.format(item_info['pageCount']))\n except KeyError:\n pass\n print('リンク: {}'.format(item_info['previewLink']))\n print()\n \n```\n\n実行結果\n\n```\n\n ======== 書籍ID: AAAAA の情報 ========\n タイトル: あああああ\n 著者: かか かかか\n 出版: さささ\n 出版日: 2000\n 説明: xxxx\n ページ数: 201\n リンク: http//\n \n ======== 書籍ID: BBBBBBB の情報 ========\n タイトル: いいいいいい\n 著者: ききき きき\n 出版: ししし\n 出版日: 2001\n リンク: http//\n \n ======== 書籍ID: XXXXXXXX の情報 ========\n タイトル: うううううううう\n 著者: くくく くくく\n 出版: すすす\n 出版日: 2002\n 説明: yyyyyyy\n ページ数: 280\n リンク: http//\n \n ======== 書籍ID: YYYYYYY の情報 ========\n タイトル: ええええええええ\n 著者: けけけ けけ\n 出版: せせせ\n 出版日: 2003\n 説明: zzzzz\n リンク: http//\n \n ======== 書籍ID: ZZZZZZZZZ の情報 ========\n タイトル: おおおおおお\n 著者: こここ ここここ\n 出版: そそそ\n 出版日: 2004\n リンク: http//\n \n```\n\ndescriptionとpageCountのキーと値を削除してデータを取り出したい、というのはどういうことでしょうか? \njson_objectからそれらのキーと値を削除したいということでしょうか? \nそれらの値が必要ない、というだけであれば、わざわざ削除しなくても、descriptionやpageCountの値を呼び出さなければ良いだけの話かと思います。 \n上の例であれば、try~exceptに囲まれた部分をコメントアウトしてしまう事がそれに当たるでしょう。\n\n* * *\n\n**追記** \nもっとコードを汎化して短くしてみました。\n\n```\n\n # coding: UTF-8\n \n import json\n \n json_file = open('a.json', 'r')\n json_object = json.load(json_file)\n attributes = ['title', 'authors', 'publisher', 'publisherDATE', 'description', 'pageCount', 'previewLink']\n \n for item in json_object['items']:\n print('======== 書籍ID: {} の情報 ========'.format(item['id']))\n \n for att in attributes:\n try:\n print('{}: {}'.format(att, item['volumeInfo'][att]))\n except KeyError:\n pass\n \n print()\n \n```\n\n実行結果\n\n```\n\n ======== 書籍ID: AAAAA の情報 ========\n title: あああああ\n authors: かか かかか\n publisher: さささ\n publisherDATE: 2000\n description: xxxx\n pageCount: 201\n previewLink: http//\n \n ======== 書籍ID: BBBBBBB の情報 ========\n title: いいいいいい\n authors: ききき きき\n publisher: ししし\n publisherDATE: 2001\n pageCount: 250\n previewLink: http//\n \n ======== 書籍ID: XXXXXXXX の情報 ========\n title: うううううううう\n authors: くくく くくく\n publisher: すすす\n publisherDATE: 2002\n description: yyyyyyy\n pageCount: 280\n previewLink: http//\n \n ======== 書籍ID: YYYYYYY の情報 ========\n title: ええええええええ\n authors: けけけ けけ\n publisher: せせせ\n publisherDATE: 2003\n description: zzzzz\n previewLink: http//\n \n ======== 書籍ID: ZZZZZZZZZ の情報 ========\n title: おおおおおお\n authors: こここ ここここ\n publisher: そそそ\n publisherDATE: 2004\n previewLink: http//\n \n```",
"comment_count": 5,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T04:34:36.587",
"id": "51642",
"last_activity_date": "2019-01-01T08:11:11.977",
"last_edit_date": "2019-01-01T08:11:11.977",
"last_editor_user_id": "25734",
"owner_user_id": "25734",
"parent_id": "51638",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51638 | 51642 | 51642 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "お世話になっております。\n\nタイトルの件について質問です。\n\nnumpy v1.15のリファレンス sin関数の引数の意味についてです。 \n<https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.15.0/reference/generated/numpy.sin.html#numpy.sin>\n\nリファレンスには、\n\nnumpy.sin(x, /, out=None, *, where=True, casting='same_kind', order='K',\ndtype=None, subok=True[, signature, extobj]) =\n\nと記載されておりますが、\n\n実際に使う場合 \nsin(x, *args, **kwargs)\n\nとしなければいけません。 \npycharmからnumpyソースコードのumath.pyを確認してみましたが、 \ndef sin(x, *args, **kwargs): \nで定義されており、\n\nnumpy.sin(x, /, out=None, *, where=True, casting='same_kind', order='K',\ndtype=None, subok=True[, signature, extobj]) = \nの部分はその下の行でコメントアウトされておりました。\n\nなぜ、マニュアルには \nnumpy.sin(x, /, out=None, *, where=True, casting='same_kind', order='K',\ndtype=None, subok=True[, signature, extobj]) = \nと記載されているのか意味が解らず困っております。\n\n第1引数のxはわかりますが、 \n第2引数以降の \n/, out, *, hwere, casting, order等の調べ方がわかりません。\n\nわかりづらい質問で大変申し訳ございませんが、 \nこのあたりの調べ方、numpyマニュアルのどの部分を見れば読み解くことができるかご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2018-12-31T22:32:59.313",
"favorite_count": 0,
"id": "51639",
"last_activity_date": "2020-06-20T11:23:54.900",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31633",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"numpy"
],
"title": "numpyリファレンス 関数の引数にあるスラッシュ以降の意味について",
"view_count": 465
} | [
{
"body": "コメントに挙げられたリンクでほぼ全て説明されているのですが、あとから参考になるように日本語で回答を残しておきます。\n\nこの記法は numpy 独自のものではなく、 Python のマニュアルで従来から用いられているものです。もともとこれは C で実装された Python\n関数の独自の仕様を説明するための記法だったのですが、 Python 3.8 から pure Python\nのコードでも使えるようになったので、そちらをもとに説明します。\n\n引数の途中の `/` は、関数定義の引数を左右に分割する目印で、実際に `/` という引数を渡せるわけではありません。実は同じようなものに `*`\nという区切りの目印が以前から存在していました。大雑把には以下のような意味です。\n\n * `/` より左側の引数は **位置専用引数 (positional-only parameters)** で、関数を呼び出すときに、仮引数の名前を使ったキーワード渡し(`f(x=42)` のような)ではなく、仮引数の順番に基づいて引数を渡さなければなりません。\n * `*` より右側の引数は **キーワード専用引数 (keyword-only parameters)** で、キーワードを必ず指定して引数を渡さなければなりません。\n * `/` と `*` の間にある引数は、位置による指定もキーワードによる指定も使えます(通常はこれがデフォルトです)。\n\n[PEP 570](https://www.python.org/dev/peps/pep-0570/) から具体例を引用して説明します。\n\n```\n\n def standard_arg(arg):\n print(arg)\n \n def pos_only_arg(arg, /):\n print(arg)\n \n def kwd_only_arg(*, arg):\n print(arg)\n \n def combined_example(pos_only, /, standard, *, kwd_only):\n print(pos_only, standard, kwd_only)\n \n```\n\nこのような関数があったときに、最初の関数は `standard_arg(2)` や `standard_arg(arg=2)`\nのどちらでも呼び出すことができますが、2番目の関数は `pos_only_arg(arg=1)` とするとエラーになります。同様に、3番目の関数は\n`kwd_only_arg(3)` とするとエラーになります。最後の例はすべて混ぜたパターンで、上に書いたとおり `/` と `*`\nとの相対的な位置によって引数の渡し方が決まります。\n\nより詳しくは [PEP 570](https://www.python.org/dev/peps/pep-0570/) や [Python 3.8\nリリースノートの位置専用引数の項目](https://docs.python.org/ja/3/whatsnew/3.8.html#positional-\nonly-parameters) を参照してください。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2020-06-20T11:23:54.900",
"id": "67835",
"last_activity_date": "2020-06-20T11:23:54.900",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "40595",
"parent_id": "51639",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51639 | null | 67835 |
{
"accepted_answer_id": "51644",
"answer_count": 1,
"body": "以下のコードでファイルに入っている画像を順に並べて1枚の画像にしたいです。 \n(5×9)枚で画像枚数は42~50で枠が足りなくてもあふれても最初の1枚目からから最高45枚だけ出力させたいです。 \n問題としてはIndexError: list index out of rangeが出てしまいます。 \nよろしくお願いします。 \n[](https://i.stack.imgur.com/ooQ0S.png)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T03:52:08.133",
"favorite_count": 0,
"id": "51641",
"last_activity_date": "2019-01-01T07:27:34.527",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31634",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"python3",
"画像",
"array"
],
"title": "pythonでファイルに入っている複数枚の画像をn×mで連結して、1枚の画像として出力したいです",
"view_count": 4199
} | [
{
"body": "動作確認はしていませんが、ご質問のフォーマットに合わせるとこんな感じですかね。 \nイメージファイルの数を取得しておいて、それ以上になったらbreakでループを抜けます。 \n最低1個のイメージファイルが必要です。\n\n```\n\n from PIL import Image\n \n import numpy as np\n import cv2, os, glob\n \n fn = glob.glob('\\\\Users\\y\\Desktop\\resize\\*.jpg')\n l = len(fn)\n k = 0\n for i in range(5):\n for j in range(9):\n if k >= l:break\n im = np.array(Image.open(fn[k]))\n if j == 0:im1 = im\n else:im1 = np.hstack((im1,im))\n k += 1\n if i == 0:im2 = im1\n else:im2 = np.vstack((im2,im1))\n if k >= l:break\n cv2.imwrite('\\\\Users\\y\\Desktop\\stack.jpg', im2)\n \n```\n\n* * *\n\n@metropolisさんの指摘を受けて、あらかじめダミーのブランクイメージをファイルなり \n何かの処理で初期化したデータなりで準備して、残り位置に穴埋めすれば良いのでは? \n以下はファイルで用意した例となるでしょう。\n\n```\n\n from PIL import Image\n \n import numpy as np\n import cv2, os, glob\n \n blank = np.array(Image.open('blank.jpg'))\n fn = glob.glob('\\\\Users\\y\\Desktop\\resize\\*.jpg')\n l = len(fn)\n k = 0\n for i in range(5):\n for j in range(9):\n if k < l:im = np.array(Image.open(fn[k]))\n else:im = blank.copy()\n if j == 0:im1 = im\n else:im1 = np.hstack((im1,im))\n k += 1\n if i == 0:im2 = im1\n else:im2 = np.vstack((im2,im1))\n if k >= l:break\n cv2.imwrite('\\\\Users\\y\\Desktop\\stack.jpg', im2)\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T06:14:54.733",
"id": "51644",
"last_activity_date": "2019-01-01T07:27:34.527",
"last_edit_date": "2019-01-01T07:27:34.527",
"last_editor_user_id": "26370",
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51641",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51641 | 51644 | 51644 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 2,
"body": "Android Studio Version 3.2.1を使用しています。\n\n通常以下の手順でImage Assetを起動できると思いますが、 \nImage Assetの項目自体が出てこないため、起動することができません。\n\n①Android Studio で Android アプリのプロジェクトを開きます。 \n②[Project] ウィンドウで [Android] ビューを選択します。 \n③res フォルダを選択して、[File] > [New] > [Image Asset] の順に選択します。\n\n解決方法を教えていただけると助かります。 \nよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T06:37:10.433",
"favorite_count": 0,
"id": "51645",
"last_activity_date": "2023-05-11T14:07:40.993",
"last_edit_date": "2020-08-19T02:33:53.723",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31635",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"android-studio"
],
"title": "Android StudioでImage Assetを起動できない",
"view_count": 1787
} | [
{
"body": "同じバージョンですが、再現しませんでした。確認したのはWindows版です。 \n根本的な解決にはならないのですが、以下に代替手段があります。\n\n<https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/index.html>\n\nこのサイト上でImageAssetとほぼ同じ操作が行えると思います。 \nライセンス等が異なる可能性があるので、その点はご注意ください。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T08:23:12.670",
"id": "51660",
"last_activity_date": "2019-01-02T08:23:12.670",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "8795",
"parent_id": "51645",
"post_type": "answer",
"score": 0
},
{
"body": "私の場合はShiftキーを2回押すとImage\nAssetが表示されました。選択するとアップデートする旨のメッセージが画面下部に表示されアップデートすると使えるようになりました。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2021-05-28T01:26:11.843",
"id": "76133",
"last_activity_date": "2021-05-28T01:26:11.843",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "45532",
"parent_id": "51645",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51645 | null | 51660 |
{
"accepted_answer_id": "51652",
"answer_count": 1,
"body": "Rust言語では `ref` パターンを使って右辺の式の参照を暗に取る事ができると思います。\n\n```\n\n // Copyではない適当な型\n struct Val{\n value: u32\n }\n \n fn main() {\n let x: Val = Val { value: 32 };\n let rx1: &Val = &x; // 普通に参照を取る\n let ref rx2: Val = x; // 参照を暗に取る\n let ref rx3: Val = x; // 何度でも取れる\n println!(\"{}\", x.value); // 単に参照をとっているだけなのでmoveされておらずxは使える\n }\n \n```\n\nこの文法を関数引数で使ってみます。\n\n```\n\n struct Val {\n value: u32\n }\n \n // refでとってみる\n fn test(ref v: Val) {\n println!(\"test: {}\", v.value)\n }\n \n fn main() {\n let x: Val = Val { value: 32 };\n test(x); // しかし残念ながらここでmoveされていて\n test(x) // コンパイルエラー(value used here after move)\n }\n \n```\n\nしかしこの場合は引数はmoveされてしまい、二度使う事ができません。 \nこういう形でrefを使った場合にxがmoveされる理由をご存知の方がいたら教えて頂けませんか。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T06:50:49.103",
"favorite_count": 0,
"id": "51647",
"last_activity_date": "2019-01-01T10:23:09.823",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "30827",
"post_type": "question",
"score": 2,
"tags": [
"rust"
],
"title": "関数引数でのrefパターンがmoveを生じさせる理由を知りたい",
"view_count": 169
} | [
{
"body": "`let x: Val`のとき`test(x)`とすると、関数の引数は「値渡し」になります。値渡しでは、値が関数の引数の領域へmoveします。\n\n`main`ではスタック領域上に`x`のための領域があります。\n\n```\n\n mainのスタックフレーム\n x | Val { value: 32}\n \n```\n\n`test`を呼ぶと、まず`main`の`x`の値が、`test`の引数の領域(`arg0`としました)にmoveします。\n\n```\n\n testのスタックフレーム\n v | 初期化されてない状態\n arg0 | Val { value: 32}\n \n mainのスタックフレーム\n x | 初期化されてない状態(move済み)\n \n```\n\nそして`v`には`arg0`への参照が置かれます。\n\n```\n\n testのスタックフレーム\n v | &arg0\n arg0 | Val { value: 32}\n \n mainのスタックフレーム\n x | 初期化されてない状態(move済み)\n \n```\n\nこれを擬似的なコードで示すと、以下のようになります。\n\n```\n\n fn test(arg0: Val) {\n let ref v = arg0;\n println!(\"test: {}\", v.value)\n }\n \n```\n\nこのように動作しますので、`x`の値がmoveするわけです。\n\n参考: <https://users.rust-lang.org/t/ref-and-for-function-arguments/12790>",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T10:23:09.823",
"id": "51652",
"last_activity_date": "2019-01-01T10:23:09.823",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "14101",
"parent_id": "51647",
"post_type": "answer",
"score": 2
}
] | 51647 | 51652 | 51652 |
{
"accepted_answer_id": "51650",
"answer_count": 1,
"body": "GAEを使用してtweet botを運用したいのですが、使い方がよく分かりません。\n\n**やりたい事** \n指定した時間にプログラムを実行するようにしたい。 \n無料で運用したい。\n\n**現状** \nコードは1つのファイルにまとめてある。(ローカルでは動作確認済み) \nその中にtweetするデータを収集する関数 \n収集したデータをtweetする関数がある。 \ngoogle cloud for sdk ubuntu14.04(vagrant内で動作)インストール済み \napp.yaml(GAEの設定ファイル?)、cron.yaml(時間指定に必要?)、requirements.txt(pythonのライブラリーをインストール)というのがデプロイするのに必要という事がなんとなくわかっている。\n\n**わからない事** \nyamlの書き方が分からない。 \nドキュメントを見るとFlaskでの始め方が書いてあるが、それは常に実行されていて?urlにアクセスする事で動作している?多分違う解釈\n\n年明けでいきなりすません。 \nエンジニアの方々の技術が必要です。 \nよろしくお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T07:05:40.283",
"favorite_count": 0,
"id": "51649",
"last_activity_date": "2019-01-01T08:47:53.550",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "22565",
"post_type": "question",
"score": -1,
"tags": [
"python",
"google-app-engine",
"google-cloud",
"google-api",
"yaml"
],
"title": "GAE yamlを書いてpythonで作ったtweet botを運用したい!",
"view_count": 112
} | [
{
"body": "YAMLの書き方ということであれば以下リンク先にリファレンスがありました。\n\n[cron.yaml\nリファレンス](https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/python/config/cronref?hl=ja)",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T08:47:53.550",
"id": "51650",
"last_activity_date": "2019-01-01T08:47:53.550",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3060",
"parent_id": "51649",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51649 | 51650 | 51650 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "eclipse+openocdのデバッグ環境を構築中なのですが、 \nexampleのhelloプログラムのデバッグ方法が分かりません。 \n手順を具体的に教えていただけないでしょうか?\n\nこちらで、試したのは、nuttxのデバッグを開始したところで、 \nhello_main()にブレークポイントをはり、 \nnuttxをコンティニューで実行したのち、 \nシリアルターミナルから\"hello\"と入力しました。 \n結果、セグメンテーションフォルトが発生してコネクションが切れました。\n\n以下は、デバッグコンソールのログとシリアルターミナルのログです。\n\n```\n\n [console]\n b hello_main\n Breakpoint 2 at 0xd008098: file hello_main.c, line 56.\n \n bt\n #0 __start () at chip/cxd56_start.c:277\n \n b\n Note: breakpoint 1 also set at pc 0x28.\n Breakpoint 3 at 0x28\n \n c\n c\n Continuing.\n Segmentation fault (core dumped)\n Remote connection closed\n -----------------------------------\n [serial terminal]\n Waiting for debugger connection.. \n NuttShell (NSH) NuttX-7.22 \n nsh> hello \n ------------------------------------\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T09:42:22.990",
"favorite_count": 0,
"id": "51651",
"last_activity_date": "2019-01-19T06:16:50.120",
"last_edit_date": "2019-01-01T10:18:30.460",
"last_editor_user_id": "29826",
"owner_user_id": "31638",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"spresense"
],
"title": "eclipse debug サンプル Hello World",
"view_count": 113
} | [
{
"body": "お世話になっております。自己解決しました、ありがとうございます。\n\n./spresense-openocd/src/rtos/nuttx_header.h \n上記、ファイルを修正しました。以下はdiffです。\n\n```\n\n diff nuttx_header.org.h nuttx_header.h\n 38,40c38,40\n < #define XCPREG 0x70\n < #define STATE 0x19\n < #define NAME 0xb8\n ---\n > #define XCPREG 0x78\n > #define STATE 0x1a\n > #define NAME 0x14c\n \n```\n\n以上、宜しくお願い致します。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-19T06:16:50.120",
"id": "52109",
"last_activity_date": "2019-01-19T06:16:50.120",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31638",
"parent_id": "51651",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51651 | null | 52109 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "私は詳解ディープラーニングという書籍を使いtensorflowの学習を行っています.\n\nそこで疑問なのですが,データを正規化させて重みにも1/√nをかけて実行したのですが正解率が正規化する前よりも下がってしまいまいした.その理由がわからないので教えていただきたいです.\n\n自分では,重みの初期値の設定の仕方が間違っている可能性があると思っていますが,具体的にどう間違っているのかがわかりません.\n\nなおこの学習で用いたモデルは隠れ層3層 \nノード数全て200 \n活性化関数relu \n出力層softmax \n誤差関数SGDを用いました.\n\nこの実装では正答率はだいたい70~80%でした. \n正規化を行わない場合全く同じモデルで94%以上でした. \n以下コードです.(正規化を行ったコードです.)\n\n```\n\n import tensorflow as tf\n import numpy as np\n from sklearn.datasets import fetch_mldata\n from sklearn.model_selection import train_test_split\n from sklearn.utils import shuffle\n mnist = fetch_mldata('MNIST original', data_home = '.')\n \n class DNN(object):\n def __init__(self, n_in, n_hiddens, n_out):\n self.n_in = n_in\n self.n_out = n_out\n self.n_hiddens = n_hiddens\n self.weight = []\n self.bias = []\n \n self._x = None\n self._y = None\n self._t = None\n self._sess = None\n self._keep_prob = None\n self._history = {\n 'loss':[],\n 'accuracy':[]\n }\n \n \n \n def weight_variable(self,shape):\n #initial = tf.truncated_normal(shape, stddev=0.01)\n initial = np.sqrt(1.0 / shape[0]) * tf.truncated_normal(shape)\n return tf.Variable(initial)\n \n def bias_variable(self,shape):\n initial = tf.zeros(shape)\n return tf.Variable(initial)\n \n def inference(self, x, keep_prob):\n for i,n_hidden in enumerate(self.n_hiddens):\n if i == 0:\n input = x\n input_dim = self.n_in\n \n else:\n \n input = output\n input_dim = self.n_hiddens[i-1]\n \n self.weight.append(self.weight_variable([input_dim, n_hidden]))\n self.bias.append(self.bias_variable([n_hidden]))\n \n h = tf.nn.relu(tf.matmul(input, self.weight[-1]) + self.bias[-1])\n output = tf.nn.dropout(h, keep_prob)\n \n self.weight.append(\n self.bias_variable([self.n_hiddens[-1], self.n_out]))\n self.bias.append(self.bias_variable([self.n_out]))\n \n y = tf.nn.softmax(tf.matmul(\n output, self.weight[-1]) + self.bias[-1])\n \n return y\n \n def loss(self, y, t):\n cross_entropy = tf.reduce_mean(-tf.reduce_sum(t * tf.log(y),axis = 1))\n return cross_entropy\n \n def training(self,loss):\n optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(0.01)\n train_step = optimizer.minimize(loss)\n return train_step\n \n def accuracy(self,y,t):\n correct_prediction = tf.equal(tf.argmax(y, 1), tf.argmax(t, 1))\n accuracy = tf.reduce_mean(tf.cast(correct_prediction, tf.float32))\n return accuracy\n \n def fit(self, X_train, Y_train,\n nb_epoch=100, batch_size=100, p_keep=0.5):\n \n x = tf.placeholder(tf.float32, shape = [None, self.n_in])\n t = tf.placeholder(tf.float32, shape = [None, self.n_out])\n keep_prob = tf.placeholder(tf.float32)\n \n self._x = x\n self._t = t\n self._keep_prob = keep_prob\n \n \n y = self.inference(x, keep_prob)\n loss = self.loss(y, t)\n train_step = self.training(loss)\n accuracy = self.accuracy(y, t)\n \n init = tf.global_variables_initializer()\n sess = tf.Session()\n sess.run(init)\n \n self._sess = sess\n self._y = y\n \n for epoch in range(nb_epoch):\n X_, Y_ = shuffle(X_train,Y_train)\n \n for i in range(len(X_train) // batch_size):\n \n start = i * batch_size\n end = start + batch_size\n \n sess.run(train_step, feed_dict = {\n x:X_[start:end],\n t:Y_[start:end],\n keep_prob:p_keep\n })\n \n loss_ = loss.eval(session = self._sess, feed_dict = {\n x:X_train,\n t:Y_train,\n keep_prob:1.0\n })\n \n accuracy_ = accuracy.eval(session = self._sess, feed_dict = {\n x:X_train,\n t:Y_train,\n keep_prob:1.0\n })\n \n self._history['loss'].append(loss_)\n self._history['accuracy'].append(accuracy_)\n \n print('epoch:', epoch,\n ' loss:', loss_,\n ' accuracy:', accuracy_)\n \n return self._history\n \n def evaluate(self, X_test, Y_test):\n accuracy = self.accuracy(self._y,self._t)\n return accuracy.eval(session = self._sess, feed_dict = {\n self._x:X_test,\n self._t:Y_test,\n self._keep_prob:1.0\n })\n \n \n if __name__ == '__main__':\n \n n = len(mnist.data)\n N = 10000 # MNISTの一部を使う\n indices = np.random.permutation(range(n))[:N] # ランダムにN枚を選択\n \n X = mnist.data[indices]\n #X = X / X.max()\n #X = X - X.mean(axis = 1).reshape(len(X),1)\n \n X = X / 255.0\n X = X - X.mean(axis=1).reshape(len(X), 1)\n \n y = mnist.target[indices]\n Y = np.eye(10)[y.astype(int)] # 1-of-K 表現に変換\n \n X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, train_size=0.8)\n \n '''\n モデル設定\n '''\n \n model = DNN(n_in=len(X[0]),\n n_hiddens=[200, 200, 200],\n n_out=len(Y[0]))\n \n '''\n モデル学習\n '''\n model.fit(X_train, Y_train,\n nb_epoch=50,\n batch_size=200,\n p_keep=0.5)\n \n '''\n 予測精度の評価\n '''\n accuracy = model.evaluate(X_test, Y_test)\n print('accuracy: ', accuracy)\n \n```\n\nご教示のほどよろしくお願いいたします.",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-01T17:34:45.547",
"favorite_count": 0,
"id": "51654",
"last_activity_date": "2019-01-01T17:34:45.547",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31609",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"python",
"機械学習",
"tensorflow",
"深層学習"
],
"title": "tensolflowでmnistの学習 データの正規化について",
"view_count": 619
} | [] | 51654 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "```\n\n List<Member> members = new List<Member>(); \n private void BtnRegisterAcct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)\n {\n \n string cellphone = txtMobileNr.Text;\n string firstName = txtFirstName.Text;\n string lastName = txtLastName.Text;\n string address = txtAddress.Text;\n \n if (!string.IsNullOrEmpty(firstName)&& !string.IsNullOrEmpty(lastName) && !string.IsNullOrEmpty(cellphone) && string.IsNullOrEmpty(address))\n {\n if (ComboBox.SelectedItemProperty != null) \n {\n members.Add(new Member(cellphone,firstName,lastName,address,ここにComboBoxの任意のアイテムを入れたいです));\n }\n }\n \n }\n \n```\n\nif文で、最初に代入した全ての変数がIsNullOrEmptyでないとき、さらにネスト上になったif文のコンボボックスの値も\nnullではないときという条件付けをしています。\n\nそして、その条件であった場合に、リストmembersに先ほどの変数と、コンボボックスの任意に選ばれたアイテムを追加したいです。しかしコンボボックス内のアイテムの、コード内での扱い方が不明です。\n\nComboBox(ドロップダウンメニューです)のアイテムは、Child member, Normal member, VIP member\nです。どう扱ったらよいのでしょうか。よろしくお願いします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T00:08:34.957",
"favorite_count": 0,
"id": "51655",
"last_activity_date": "2019-01-02T04:21:03.667",
"last_edit_date": "2019-01-02T04:21:03.667",
"last_editor_user_id": "31225",
"owner_user_id": "31225",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"c#",
"visual-studio",
"wpf"
],
"title": "ComboBox内のアイテムをリスト(List<T>)に加えたい場合",
"view_count": 735
} | [
{
"body": "コンボボックスの`SelectedItem`で選択中の`ComboBoxItem`が取得できます。 \nそこから`Content`を取り出してstring型にすることでアイテムに表示されている値を取り出せます。\n\n`ComboBox.SelectedItemProperty`は静的なプロパティなので、実際にxaml上に記述したコンボボックスのインスタンスから選択中のアイテムを取ることはできません。\n\n下記のコードでコンボボックスの値をリストボックスに表示できます。(住所や氏名などのテキストボックスは割愛) \nコンボボックスの`ItemsSource`に独自のクラスを設定している場合は`SelectedItem`をキャストしてください。\n\n**MainWindow.xaml**\n\n```\n\n <Window x:Class=\"WpfApp1.MainWindow\"\n xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation\"\n xmlns:x=\"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml\"\n xmlns:d=\"http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008\"\n xmlns:mc=\"http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006\"\n xmlns:local=\"clr-namespace:WpfApp1\"\n mc:Ignorable=\"d\"\n Title=\"MainWindow\" Height=\"450\" Width=\"800\">\n <Grid>\n <StackPanel>\n <ComboBox Name=\"CmbMember\">\n <ComboBoxItem Content=\"Child member\"/>\n <ComboBoxItem Content=\"Normal member\"/>\n <ComboBoxItem Content=\"Vip member\"/>\n </ComboBox>\n <Button Name=\"BtnRegisterAcct\" Content=\"test\"/>\n <ListBox Name=\"LstCustomer\" DisplayMemberPath=\"DisplayMember\"/>\n </StackPanel>\n </Grid>\n </Window>\n \n```\n\n**MainWindow.xaml.cs**\n\n```\n\n using System.Collections.Generic;\n using System.Windows;\n using System.Windows.Controls;\n \n namespace WpfApp1\n {\n /// <summary>\n /// MainWindow.xaml の相互作用ロジック\n /// </summary>\n public partial class MainWindow : Window\n {\n public List<Customer> Customers { get; set; }\n \n public MainWindow()\n {\n InitializeComponent();\n \n Customers = new List<Customer>();\n LstCustomer.ItemsSource = Customers;\n \n BtnRegisterAcct.Click += BtnRegisterAcct_Click;\n }\n \n private void BtnRegisterAcct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)\n {\n string cellphone = \"090-1234-5678\";\n string firstName = \"John\";\n string lastName = \"Smith\";\n string address = \"日本\";\n \n if (!string.IsNullOrEmpty(firstName) && !string.IsNullOrEmpty(lastName) && !string.IsNullOrEmpty(cellphone) && !string.IsNullOrEmpty(address))\n { \n if (CmbMember.SelectedItem != null)\n {\n var item = (ComboBoxItem)CmbMember.SelectedItem;\n // 選択中のコンボボックスアイテムをそのまま保持したい時\n Customers.Add(new Customer(cellphone, firstName, lastName, address, item));\n // 中の文字列を取り出したい時\n Customers.Add(new Customer(cellphone, firstName, lastName, address, item.Content.ToString()));\n \n // 再描画\n LstCustomer.Items.Refresh();\n }\n }\n }\n }\n \n public class Customer\n {\n public Customer(string cellphone, string firstName, string lastName, string address, string member)\n {\n CellPhone = cellphone;\n FirstName = firstName;\n LastName = lastName;\n Address = address;\n Member = member;\n }\n \n public Customer(string cellphone, string firstName, string lastName, string address, ComboBoxItem item)\n : this(cellphone, firstName, lastName, address, item.Content.ToString())\n {\n }\n \n public string CellPhone { get; set; }\n public string FirstName { get; set; }\n public string LastName { get; set; }\n public string Address { get; set; }\n public string Member { get; set; }\n \n public string DisplayMember\n {\n get\n {\n return string.Format(\"[{0}] {1} {2}: {3} ({4})\", Member, FirstName, LastName, Address, CellPhone);\n }\n }\n }\n }\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T03:40:56.330",
"id": "51657",
"last_activity_date": "2019-01-02T03:40:56.330",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "9820",
"parent_id": "51655",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51655 | null | 51657 |
{
"accepted_answer_id": "51680",
"answer_count": 1,
"body": "下記の様に指定しても、パソコンに`MS Mincho`と`MS Gothic`が無ければ、正しいフォントが表示してくれません。\n\n```\n\n \\usepackage{luatexja-fontspec}\n \\setmainjfont[BoldFont=HGMinchoB]{MS Mincho}\n \\setsansjfont[BoldFont=KozGoPro-Bold]{MS Gothic}\n \n```\n\n`LuaLaTeX`として出来るかどうか、未だ存じておりませんが、合理上利用されるフォントを直接フロンエンドのフォルダーの中に保管すれば完璧解決のではないでしょうか。\n\n[](https://i.stack.imgur.com/IBBzf.png)\n\n下記は、正しい構文ではないですが、下記のようにフォントが利用できますでしょうか。\n\n```\n\n \\setmainjfont[BoldFont=HGMinchoB]{'./../fonts/msgothic.ttc' , './../fonts/HGRMB.TTC'}\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T03:51:01.517",
"favorite_count": 0,
"id": "51658",
"last_activity_date": "2019-01-06T08:23:31.590",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "16876",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"latex"
],
"title": "LuaLaTeX + luatexja-fontspec: 利用されるフォントを、直接プロジェクトフォルダから利用出来ますか?",
"view_count": 1141
} | [
{
"body": "TeX/LaTeX Stack Exchange\nに[類似の質問](https://tex.stackexchange.com/questions/357489/)がありました.\n\nluatexja-fontspec の場合も同様の方法が使えるようです.手許に MS Gothic\n等のフォントがないので,[にしき的フォント](http://hwm3.gyao.ne.jp/shiroi-niwatori/nishiki-\nteki.htm)の例になりますが,以下のようなディレクトリ構成で\n\n```\n\n .\n ├── nishiki-teki\n │ └── nishiki-teki.ttf\n └── test.tex\n \n```\n\n次の LaTeX 文書を lualatex に **`-recorder`\nオプションを付けて**処理すると,相対パスで指定したフォントファイルのフォントが出力 PDF に埋め込まれます.\n\n```\n\n \\documentclass{ltjsarticle}\n \n \\usepackage[abspath]{currfile}\n \\usepackage{luatexja-fontspec}\n \n \\setmainjfont[\n Path = \\currfileabsdir,\n UprightFont = nishiki-teki/nishiki-teki.ttf,\n BoldFont = nishiki-teki/nishiki-teki.ttf,\n ]{nishiki-teki}\n \n \\setsansjfont[\n Path = \\currfileabsdir,\n UprightFont = nishiki-teki/nishiki-teki.ttf,\n BoldFont = nishiki-teki/nishiki-teki.ttf,\n ]{nishiki-teki}\n \n \\begin{document}\n \n mainのフォント.{\\bfseries boldのフォント.}{\\sffamily\\gtfamily sansのフォント.}\n \n \\end{document}\n \n```\n\n[](https://i.stack.imgur.com/TTJBE.png)\n\nまた,LuaTeX の場合は `\\directlua` が使えて,なおかつ Lua の lfs\nライブラリを用いるとカレントディレクトリが簡単に取得できるので,上の `\\usepackage[abspath]{currfile}` の代わりに\n\n```\n\n \\edef\\currfileabsdir{\\directlua{tex.sprint(lfs.currentdir())}/}\n \n```\n\nでも ok ですね.この場合は `-recorder` オプションも不要です.",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T11:46:41.917",
"id": "51680",
"last_activity_date": "2019-01-06T08:23:31.590",
"last_edit_date": "2019-01-06T08:23:31.590",
"last_editor_user_id": "27047",
"owner_user_id": "27047",
"parent_id": "51658",
"post_type": "answer",
"score": 4
}
] | 51658 | 51680 | 51680 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "flaskでAPIを作成しており、POSTメソッドを実装してみたところ、下記のようなエラーが発生しましたが、解決できず困っています。\n\n * エラー内容\n\n```\n\n sqlalchemy.exc.IntegrityError: (_mysql_exceptions.IntegrityError) (1452, 'Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`mydb`.`page`, CONSTRAINT `page_ibfk_1` FOREIGN KEY (`belong_id`) REFERENCES `belong` (`id`))') [SQL: 'INSERT INTO page (id, title, belong_id, created_at, updated_at) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)'] [parameters: (0, 'test', '', datetime.datetime(2019, 1, 2, 6, 16, 56, 752822), datetime.datetime(2019, 1, 2, 6, 16, 56, 752822))] (Background on this error at: http://sqlalche.me/e/gkpj)\n 127.0.0.1 - - [02/Jan/2019 06:16:56] \"POST /pages?title=test HTTP/1.1\" 500 -\n \n```\n\n * flask POSTメソッド実装部分\n\n```\n\n @app.route('/pages',methods=['POST'])\n def post_page():\n title = request.args.get('title','')\n belong_id = request.args.get('belong_id','')\n page_repository = PageRepository(access_point)\n page = page_repository.post(title,belong_id)\n \n```\n\n * 実行内容\n\n```\n\n curl -X POST -H \"Content-Type: application/json\" http://0.0.0.0:8080/pages?belong_id=1&title;=test\n \n```\n\n * o/rマッパー部分抜粋\n\n```\n\n class Relation(Base):\n __tablename__ = 'relation'\n id = Column('id', Integer, primary_key=True)\n code_link = Column('code_link', Text)\n memo = Column('memo', Text)\n \n class Belong(Base):\n __tablename__ = 'belong'\n id = Column('id', Integer, primary_key=True)\n relation_order = Column('relation_order', Integer, ForeignKey('relation.id', onupdate=\"CASCASE\", ondelete=\"CASCASE\"))\n page = relationship('Page')\n \n Base.metadata.create_all(engine)\n \n class Page(Base):\n __tablename__ = 'page'\n id = Column('id', Integer, primary_key=True)\n title = Column('title', String(200))\n belong_id = Column('belong_id', Integer, ForeignKey('belong.id', onupdate=\"CASCASE\", ondelete=\"CASCASE\"))\n created_at = Column(DateTime)\n updated_at = Column(DateTime)\n \n```\n\nrelationテーブル、belongテーブルにはそれぞれ1レコード(id=1)データがそれぞれ既に入っています。 \nまた、最初に入れていたデータがおかしいのかと思い、一度テーブルを削除、作り直しをしてデータを入れ直してもみましたが、同じエラーが発生しています。\n\n恐れ入りますが何かご教授いただけますと幸いです。 \nよろしくお願いいたします。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T06:32:52.770",
"favorite_count": 0,
"id": "51659",
"last_activity_date": "2019-01-04T14:46:12.370",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "30649",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"mysql",
"api",
"flask"
],
"title": "flaskでpostメソッドを実施すると外部キー制約周りでエラーが発生する",
"view_count": 184
} | [
{
"body": "エラー内容を見る限り、以下のクエリが発行されています。\n\n```\n\n INSERT INTO page (\n id, \n title, \n belong_id, \n created_at, \n updated_at\n ) \n VALUES (\n 0, \n 'test', \n '', # ここが空\n '2019 01/02 ...',\n '2019 01/02 ...'\n );\n \n```\n\n`belong_to` の値が空でMySQLの外部キー制約に反するためにINSERTができないのだと思われます。",
"comment_count": 4,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-04T14:46:12.370",
"id": "51707",
"last_activity_date": "2019-01-04T14:46:12.370",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31669",
"parent_id": "51659",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51659 | null | 51707 |
{
"accepted_answer_id": "51662",
"answer_count": 1,
"body": "[こちらの質問](https://ja.stackoverflow.com/questions/51109/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%B8%8A%E3%81%A7%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8Bjavascript%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をしたものです。 \nマルチプラットフォームで動作するJavaScriptのランタイムエンジンを探していて、皆さんのアドバイスもあって[BaristaCore](https://github.com/BaristaLabs/BaristaCore)というChakraCoreを使い.NET\nStandardで実装されたフレームワークを見つけたのですが、いざ開発してみるといきなり壁にぶち当たってしまいました。\n\nMacとiOSで試すためにUnityを使ってテストを行いました。 \n[こちらのトピック](https://github.com/BaristaLabs/BaristaCore/wiki/Embedding-\nBaristaCore-into-your-own-\napplication)を読みながらそのままで書いていたのですが、Macでは期待した動作をしてくれたのですがiOSにビルドしてみると上手く動作しませんでした。\n\nそこで Xcodeのログを読むと以下のようになっていました。\n\n```\n\n InvalidOperationException: \n A suitable constructor for type 'BaristaLabs.BaristaCore.BaristaRuntimeFactory' could not be located. \n Ensure the type is concrete and services are registered for all parameters of a public constructor.\n \n```\n\nエラー文で調べると`BaristaRuntimeFactory`のコンストラクタが`private`になっている可能性があると出たので早速[ソース](https://github.com/BaristaLabs/BaristaCore/blob/e0cee70a0e3de72411e636d72e63d4cc9a51202b/src/BaristaLabs.BaristaCore.Common/BaristaRuntimeFactory.cs)を読みましたが、コンストラクタは`public`になっていました。\n\nこれは私が何か前提を間違えているのか、BaristaCoreはiOSでは使えないのかが分かりません。 \nUnityのビルド設定でしなければいけないことがあるかも知れませんし、XcodeのLinked Frameworks and\nLibrariesの欄に何か追加しなければいけないのかもしれません。\n\n考えられる可能性は何でも教えていただきたいです。\n\nかなり欲しい条件を満たしているので、できればこのままBaristaCoreを使いたいです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T09:07:59.007",
"favorite_count": 0,
"id": "51661",
"last_activity_date": "2019-01-02T16:00:30.087",
"last_edit_date": "2019-01-02T11:16:16.253",
"last_editor_user_id": "76",
"owner_user_id": "31396",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"javascript",
"unity3d"
],
"title": "BaristaCoreがMac上では動作するがiOS上で動作しない理由がわかりません",
"view_count": 151
} | [
{
"body": "逆にBaristaCoreがiOSで動作するという根拠が判りません。\n\n該当ページの [README.md](https://github.com/BaristaLabs/BaristaCore) にも、そこで紹介されている\n[Roadmap](https://github.com/BaristaLabs/BaristaCore/wiki/Roadmap)\nにも、macOSは記載されていますが、iOSはありません。\n\nREADME.md\n\n> Provides a sandboxed JavaScript runtime natively to a .Net Standard 2.0\n> application on Windows, Linux and macOS.\n\nRoadmap\n\n> Continuous Integration \n> ☑ Automated Cross-Platform builds w/ Unit Tests \n> ☑ Windows \n> ☑ Linux \n> ☑ macOS \n> Automated Releases \n> NuGet \n> Chocolatey \n> Apt-Get \n> Brew\n\nChakraCore自身もiOSで動かしたことはあるようですが、公式サポートはされていないようです。 \n[How can i build ChakraCore for IOS?\n#3179](https://github.com/Microsoft/ChakraCore/issues/3179)\n\n> There is no build configuration for iOS today. Some friends of the project\n> have made it work on iOS, but there is not a PR or public fork at present.\n\nただし、誰もテストしていないだけで、動くのかもしれませんが、 \nその場合は誰か(貴方?)が動作確認やサポートのプロジェクトを立ち上げて \n推進していく必要があるでしょう。\n\n* * *\n\n## 追記\n\n古い記事なので今も当てはまるか不明ですが、こんな情報があります。何か参考になれば。 \n[Xamarin.Mac (か Xamarin.iOS )から netstandard2\nを使用する方法](https://qiita.com/toshi0607/items/8ff2b9ca54a0ad353f2f) \n[Xamarin.Mac and netstandard2](https://medium.com/@donblas/xamarin-mac-and-\nnetstandard2-708a06890302) \n[Unable to build iOS project that references a NET Standard 2.0\nlibrary](https://bugzilla.xamarin.com/show_bug.cgi?id=58504)\n\n[Xamarin(Formsもね)で.NET Standard\n2.0なライブラリを利用する](http://www.nuits.jp/entry/xamarin-forms-with-netstandard-20) \n[.NET\nStandardなライブラリプロジェクトを作成して参照する](https://www.buildinsider.net/language/dotnetcore/05)\n\n* * *\n\n## さらに追記\n\nこういう記事 [Is the `JS engine` on `IOS` or `MaxOS's` Chrome browser `V8`?Or\n`JavaScriptCode`?](https://stackoverflow.com/q/49890333/9014308) や\n[iOS版「Google\nChrome」が速くない理由](http://ascii.jp/elem/000/000/707/707070/index-3.html)\nがあって、技術的や個人使用では可能でも、商用・公開ソフトとしては作れないのかもしれませんね。\n\n> AppleがiOSデベロッパーに課すライセンス契約(アプリ埋め込みでないスクリプト/インタープリタ機構の搭載を禁じる条項がある)により、...",
"comment_count": 2,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T09:55:01.163",
"id": "51662",
"last_activity_date": "2019-01-02T16:00:30.087",
"last_edit_date": "2020-06-17T08:14:45.997",
"last_editor_user_id": "-1",
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51661",
"post_type": "answer",
"score": 1
}
] | 51661 | 51662 | 51662 |
{
"accepted_answer_id": "52266",
"answer_count": 3,
"body": "Spresense を ArduinoIDE で使用しています。 \n未使用関数等が多いライブラリを使用時のプログラムサイズ削減の方法について質問します。\n\nU8g2\nなどの未使用のフォントデータ等が多いライブラリを使用する際、プログラムサイズを超過することがありました。そのため、コンパイル・リンカオプションで未使用関数等の削除を行うよう設定したところ、実行時に異常終了してしまいます。ライブラリを使用しないシリアル出力だけのコードでも異常終了するため、オプションでの削除は不可能のようです。 \nライブラリから必要なコードだけ抜き出して使用する以外で、なにか解決方法はありませんでしょうか?\n\n◆\"platform.txt\" 変更内容 \ncompiler.c.flags : -ffunction-sections -fdata-sections を追加 \ncompiler.cpp.flags : -ffunction-sections -fdata-sections を追加 \ncompiler.c.elf.flags : -Wl,--gc-sections を追加\n\n◆サンプルコード\n\n```\n\n #include <U8g2lib.h> //あってもなくても異常終了する\n void setup() {\n Serial.begin(115200);\n Serial.println(\"START\");\n }\n void loop() {\n }\n \n```",
"comment_count": 1,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-02T14:28:31.470",
"favorite_count": 0,
"id": "51664",
"last_activity_date": "2019-01-23T16:52:11.763",
"last_edit_date": "2019-01-02T14:30:09.000",
"last_editor_user_id": "76",
"owner_user_id": "31644",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"arduino",
"spresense"
],
"title": "ArduinoIDE環境でライブラリ使用時の未使用関数等の削除について",
"view_count": 416
} | [
{
"body": "そのオプションはどこからも参照されない関数や変数を生成しないというものなので、割り込みハンドラ関数などは軒並み削除対象となってしまいます \n必要な割り込みハンドラは削除しないように指定する必要がありますね",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T07:30:45.790",
"id": "51676",
"last_activity_date": "2019-01-03T07:30:45.790",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "27481",
"parent_id": "51664",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "gc-sections オプションによる関数・データ単位の削除が使えそうにないので、オブジェクト単位で削除するしかなさそうです。\n\nlibrary.properties に\n\n```\n\n dot_a_linkage=true\n \n```\n\nを追加して.aファイル化すれば、不要な.oファイルはリンクされなくなるのでコードサイズが削減できるかもしれません。\n\n私も U8g2 ライブラリで同じ問題にハマりました。。\n\ndot_a_linkage=true 追加で、自分のアプリはビルドできるようになりましたが、U8g2.a\nアーカイブ化しても未使用フォントデータがすべてリンクされてしまうので、かなりのメモリサイズを無駄に喰っています。\n\nやっぱり必要な font だけ抜き出して使うしかなさそうです。\n\n以下は少々手順が複雑ですが、fontごとにファイルを分割してみた例です。\n\n```\n\n ### src/clib ディレクトリ下で作業\n $ cd src/clib\n \n ### u8g2_fonts.cファイルを分割するスクリプト(かなりやっつけですが^^; \n $ cat split_u8g2_fonts.awk\n {\n if(NR>5){\n if(/^\\/\\*/) {\n fn=sprintf(\"u8g2_font_%04d.c\",++num);\n print \"#include \\\"u8g2.h\\\"\" >> fn\n }\n print >> fn;\n }\n }\n \n ### u8x8_fonts.c も\n $ cat split_u8x8_fonts.awk\n {\n if(NR>5){\n if(/^\\/\\*/) {\n fn=sprintf(\"u8x8_font_%04d.c\",++num);\n print \"#include \\\"u8x8.h\\\"\" >> fn\n }\n print >> fn;\n }\n }\n \n ### ファイル分割\n $ awk -f split_u8g2_fonts.awk u8g2_fonts.c\n $ awk -f split_u8x8_fonts.awk u8x8_fonts.c\n \n ### オリジナルファイルを削除\n $ rm u8g2_fonts.c u8x8_fonts.c\n \n```\n\nここまでしてからビルドすれば未使用フォントもリンク時に削除されてプログラムサイズも妥当な値になりました。\n\n**(追記)** \nU8g2 ライブラリ本体を変更するのでない限り、上記の方法で一回作成した U8g2.a を取っておいて、precompiled オプション(Arduino\nIDE 1.8.6 以降)を使うのもアリかもしれません。\n\nU8g2/library.properties から dot_a_linkage を削除して、precompiled=trueを追加。\n\n```\n\n precompiled=true\n \n```\n\n作成済みの U8g2.a を U8g2/src/spresense へコピー\n\n```\n\n ### コピー\n $ mkdir src/spresense\n $ cp your/U8g2.a src/spresense\n \n ### .cpp や .c ファイルをバッサリ削除\n $ rm src/*.cpp src/clib/*.c\n \n```\n\nこの状態でスケッチをビルドすれば、U8g2.a はリンクするだけになって快適に使えます。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-23T01:51:48.923",
"id": "52225",
"last_activity_date": "2019-01-23T01:58:19.437",
"last_edit_date": "2019-01-23T01:58:19.437",
"last_editor_user_id": "31378",
"owner_user_id": "31378",
"parent_id": "51664",
"post_type": "answer",
"score": 1
},
{
"body": "改めて gc-sections オプションが使えない理由を調べてみました。\n\n> ◆\"platform.txt\" 変更内容 \n> compiler.c.flags : -ffunction-sections -fdata-sections を追加 \n> compiler.cpp.flags : -ffunction-sections -fdata-sections を追加 \n> compiler.c.elf.flags : -Wl,--gc-sections を追加\n\nを付けたときに、グローバルコンストラクタのテーブルが削除されてしまい、それに起因して実行時にエラーが発生していたようです。\n\nリンクスクリプトファイル \nArduino15/packages/SPRESENSE/tools/spresense-\nsdk/1.x.x/spresense/release/prebuilt/build/ramconfig.ld \nArduino15/packages/SPRESENSE/tools/spresense-\nsdk/1.x.x/spresense/debug/prebuilt/build/ramconfig.ld \nの .init_array を KEEP()で囲むことで、\n\n```\n\n *(.init_array .init_array.*) → KEEP (*(.init_array .init_array.*))\n \n```\n\n実行時のエラーがなくなりました。\n\n解決方法としてこちらの方が良さそうです。",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-23T16:52:11.763",
"id": "52266",
"last_activity_date": "2019-01-23T16:52:11.763",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "31378",
"parent_id": "51664",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51664 | 52266 | 51676 |
{
"accepted_answer_id": "51668",
"answer_count": 1,
"body": "列挙型には基本となる型を指定することができますが、 \n列挙型の値から基本となる型を取得することは出来るでしょうか。 \n出来るとすれば、どのように取得すればよいでしょうか。\n\n```\n\n public enum SampleEnum : long\n {\n Value1, Value2, Value3\n }\n \n```",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T00:25:08.573",
"favorite_count": 0,
"id": "51667",
"last_activity_date": "2019-01-03T00:50:14.200",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "3925",
"post_type": "question",
"score": 2,
"tags": [
"c#",
".net-core"
],
"title": "列挙型の基になる型を取得する",
"view_count": 102
} | [
{
"body": "[Object.GetType Method](https://docs.microsoft.com/ja-\njp/dotnet/api/system.object.gettype?view=netframework-4.7.2) して\n[Enum.GetUnderlyingType(Type) Method](https://docs.microsoft.com/ja-\njp/dotnet/api/system.enum.getunderlyingtype?view=netframework-4.7.2) や\n[Enum.GetTypeCode Method](https://docs.microsoft.com/ja-\njp/dotnet/api/system.enum.gettypecode?view=netframework-4.7.2#System_Enum_GetTypeCode)\nが使えるようですね。\n\n他参考 \n[Get underlying/derived type of\nenum?](https://stackoverflow.com/q/5305627/9014308)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T00:50:14.200",
"id": "51668",
"last_activity_date": "2019-01-03T00:50:14.200",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "26370",
"parent_id": "51667",
"post_type": "answer",
"score": 3
}
] | 51667 | 51668 | 51668 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "pinterestのapiを使ってアプリを作成したいのですが、access tokenの取得方法が分かりません。 \n<https://developers.pinterest.com/docs/api/overview/> \nドキュメントを読んだのですが、Postmanを使ったやり方しか理解できません。毎度アプリで取得して使いたいのでpythonのプログラムから取得したいのです。 \nhatenaのアクセストークンを取得するときに以下のコードを作成したのですが、これにどのようにpinterestの情報を入れたら良いのでか分かりません。 \n`appID`と`appSecret`の2つしかpinterestではないです。oauthのバージョンが違うなどでしょうか? \n一日中、探しても出てこなかったのでここで質問させていただきます。 \nよろしくお願いします。\n\n```\n\n import os\n \n from flask import Flask, request, redirect, session\n from furl import furl\n from requests_oauthlib import OAuth1Session\n \n app = Flask(__name__)\n app.secret_key ='????????????????'\n #urlをこんな感じにする。https://www.pinterest.com/oauth/?consumer_id=たぶん自分のappID&response_type=token\n OAUTH_CONSUMER_KEY = 'xxxxxxxxxxxxxxx' #pinでいうclient IDに当たる\n OAUTH_CONSUMER_SECRET = 'yyyyyyyyyyyyyy'\n \n TEMPORARY_CREDENTIAL_REQUEST_URL = '????????????'\n RESOURCE_OWNER_AUTHORIZATION_URL = '????????????'\n TOKEN_REQUEST_URL = '??????????????????'\n \n CALLBACK_URI = 'http://0.0.0.0:9000/callback_page'\n SCOPE = {'scope': 'read_public,write_public'}\n \n @app.route('/')\n def index():\n oauth = OAuth1Session(OAUTH_CONSUMER_KEY, client_secret=OAUTH_CONSUMER_SECRET, callback_uri=CALLBACK_URI)\n #以下のコードがよくわからん\n fetch_respone = oauth.fetch_request_token(TEMPORARY_CREDENTIAL_REQUEST_URL, data=SCOPE)\n \n session['request_token'] = fetch_respone.get('oauth_token')\n session['request_token_secret'] = fetch_respone.get('oauth_token_secret')\n \n redirect_url = furl(RESOURCE_OWNER_AUTHORIZATION_URL)\n redirect_url.args['oauth_token'] = session['request_token']\n return redirect(redirect_url.url)\n \n @app.route('/callback_page')\n def callback_page():\n #verifierってなんですの?\n verifier = request.args.get('oauth_verifier')\n oauth = OAuth1Session(OAUTH_CONSUMER_KEY, client_secret=OAUTH_CONSUMER_SECRET, resource_owner_key=session['request_token'], resource_owner_secret=session['request_token_secret'], verifier=verifier)\n \n access_tokens = oauth.fetch_access_token(TOKEN_REQUEST_URL)\n access_token = access_tokens.get('oauth_token')\n access_secret = access_tokens.get('oauth_token_secret')\n return \"アクセストークン: {}, アクセストークン・シークレットキー: {}\".format(access_token, access_secret)\n \n if __name__ == '__main__':\n app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=9000)\n \n```\n\nPostmanを使用する場合は以下の情報を入力するみたいです。 \n[](https://i.stack.imgur.com/AwV7V.png)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T03:20:50.303",
"favorite_count": 0,
"id": "51671",
"last_activity_date": "2020-07-27T05:33:53.087",
"last_edit_date": "2020-07-27T05:33:53.087",
"last_editor_user_id": "754",
"owner_user_id": "22565",
"post_type": "question",
"score": 3,
"tags": [
"python",
"python3",
"oauth",
"flask",
"webapi"
],
"title": "pinterest access tokenの取得やり方が分からない。",
"view_count": 302
} | [] | 51671 | null | null |
{
"accepted_answer_id": "51704",
"answer_count": 1,
"body": "カメラ機能が付いたActivity(TakePictureActivity)から写真のアップロードのActivity(Main5Activity)へと画面推移がしたいのですが、実機で実行するとアプリが停止してしまいます。コードは以下のようになっております。どなたか教えてくださると大変助かります。\n\n```\n\n public class TakePictureActivity extends AppCompatActivity {\n \n private Uri _imageUri;\n \n @Override\n protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {\n super.onCreate(savedInstanceState);\n setContentView(R.layout.activity_take_picture);\n \n \n Button tosend = (Button) findViewById(R.id.to_send);\n tosend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {\n @Override\n public void onClick(View v) {\n Intent in = new Intent(TakePictureActivity.this,Main5Activity.class);\n \n startActivity(in);\n }\n });\n \n }\n \n```",
"comment_count": 3,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T04:01:49.880",
"favorite_count": 0,
"id": "51672",
"last_activity_date": "2019-01-04T12:26:31.930",
"last_edit_date": "2019-01-04T12:26:31.930",
"last_editor_user_id": "3060",
"owner_user_id": "31592",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"android",
"java"
],
"title": "Activity間の画面推移の途中でアプリが停止してしまう",
"view_count": 62
} | [
{
"body": "Activity遷移の途中で実行時エラーということですので、症状を聞いた限りですと、AndroidManifest.xmlにMain5Activity.classの記載が抜けているように思えます。 \nこのケースではbuildは通りますがActivityの遷移部分で落ちます。(Logcatにエラー内容が表示されるのですが、ビルド時のエラーチェックのようにエラーがピンポイントで表示されるようなことは無く、大量に流れていっているエラーログの中に混ざっているので注意して見ないと見落とす可能性があります) \n他に落ちそうな部分としては、ご提示いただいたコード中にはありませんがonPause()等の途中の処理は問題ないでしょうか。\n\nキャッシュが悪さをしている可能性もあるため、一度、File→Invalidate/Caches\nResartを実行してみても良いかもしれません。(開発環境はAndroidStudioを想定しています)",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-04T11:48:42.263",
"id": "51704",
"last_activity_date": "2019-01-04T11:48:42.263",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "8795",
"parent_id": "51672",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51672 | 51704 | 51704 |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 0,
"body": "Android Webviewにてユーザーエージェントを変更&実行後サーバのアクセスログを見ると\nfaviconの読み込むときのユーザーエージェントが変わらない\n\n```\n\n webView = (WebView) findViewById(R.id.webview); //ブラウザ定義\n progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progress);\n //ユーザーエージェントを書き換えるところ\n //String userAgent = webView.getSettings().getUserAgentString();\n webView.getSettings().setUserAgentString(\"MyBrowzer777\");\n ---省略--\n webView.loadUrl(\"http://myinfo.info/info.php\");\n \n```\n\n上記コードを実行すると\n\n * ./info.phpのアクセス時には MyBrowzer777のユーザエージェント\n * ./favicon.icoのアクセス時には端末固有のユーザーエージェント\n\nになってしまいます。\n\n```\n\n 192.168.2.114 - - [03/Jan/2019:12:42:54 +0900] \"GET /info.php HTTP/1.1\" 200 663 \"-\" \"MyBrowzer777\"\n 192.168.2.114 - - [03/Jan/2019:12:42:54 +0900] \"GET /favicon.ico HTTP/1.1\" 200 5783 \"-\" \"Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Nexus 5 Build/KTU84P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/33.0.0.0 Mobile Safari/537.36\"\n \n```\n\nfavicon.icoのアクセス時も 同じユーザーエージェントで読み込むにはどの様な設定が必要か知っておられたらご教授下さい",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T04:51:53.187",
"favorite_count": 0,
"id": "51673",
"last_activity_date": "2019-01-03T06:07:05.287",
"last_edit_date": "2019-01-03T06:07:05.287",
"last_editor_user_id": "29826",
"owner_user_id": "29496",
"post_type": "question",
"score": 1,
"tags": [
"android",
"webview"
],
"title": "Android Webviewにてユーザーエージェントを変更後サーバのアクセスログを見ると faviconの読み込むときのユーザーエージェントが変わらない",
"view_count": 370
} | [] | 51673 | null | null |
{
"accepted_answer_id": null,
"answer_count": 1,
"body": "iOSでは,ハードウェアが画面へのタッチを検出するとUIGestureRecognizerのイベントがコールされますが,こうした実際の物理的なタッチなしに,コード上でタッチしたように見せかけて(偽装する)イベントを送ることは可能でしょうか?",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-01-03T05:41:54.123",
"favorite_count": 0,
"id": "51674",
"last_activity_date": "2019-02-12T12:03:04.797",
"last_edit_date": "2019-01-03T06:24:31.627",
"last_editor_user_id": "31650",
"owner_user_id": "31650",
"post_type": "question",
"score": 0,
"tags": [
"swift",
"ios"
],
"title": "Swift4でタッチイベントをコードで動的に生成したい",
"view_count": 239
} | [
{
"body": "UIControlクラスの継承クラスであれば、こちらのAPIが利用できそうです \n<https://developer.apple.com/documentation/uikit/uicontrol/1618237-sendaction>",
"comment_count": 0,
"content_license": "CC BY-SA 4.0",
"creation_date": "2019-02-12T12:03:04.797",
"id": "52732",
"last_activity_date": "2019-02-12T12:03:04.797",
"last_edit_date": null,
"last_editor_user_id": null,
"owner_user_id": "19889",
"parent_id": "51674",
"post_type": "answer",
"score": 0
}
] | 51674 | null | 52732 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.